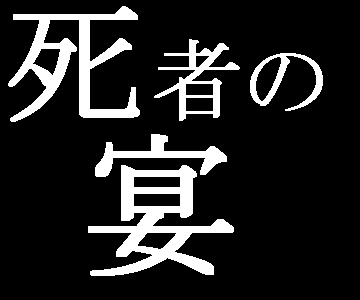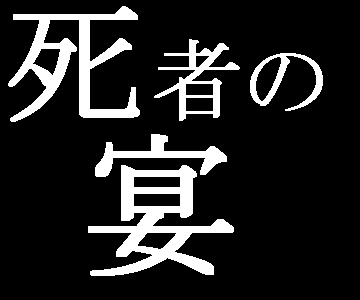
第9章:死者の宴
***
ねえ?私のこと、好き?
アスカは誰にともなくそう尋ねた。
「うん、僕はアスカのこと好きだよ」
シンジが答える。
「もちろん、好きだよ」
加持もそう答える。
「えぇ、私はアスカのこと好きよ」
ミサトも言った。
私のこと、好き好きだい好きって言ってみて。
「僕はアスカのこと好きだけど、アスカは自分のこと好きじゃないの?」
「アスカは、自分が嫌いかい?」
「私と同じで、自分が好きじゃないの?」
私のこと、好き好きだい好きって言って!
「そうしないと不安なんだね?」
「自分が好きだと思えないのね?」
言ってみてって言ってるでしょ!
「アスカはどうして自分のこと嫌いなの?」
うるさい!そんなのあんたも同じでしょ!だから私は自分を好きになるの!あんたとは違う!私は自分を好きになるため努力してる!
だからあんなに苦しくっても我慢したのに…
「苦しめば苦しむほど、作り上げた自分が嫌になる。他人の目に映る自分と自分の中の自分のギャップが苦しくなる」
黙れ!あんたはいいわよ!何もしてないのにEVAが動かせる。それだけでみんながちやほやしてくれるんだから!
「アスカだってそうだろ?」
そう、そう『だった』。
だから今、私には
何もない。
もうEVAはいらない。私には動かせない。
「動かせないと思ってるからだろ?」
私はそんな自分が嫌。何もいらないみたいな顔をしてる優等生も嫌い。シンジも憎い。
コイシテシカモニクンデルヨ
恋?違うと思う。でもそう名付ければそうなるのかな?
ハジメニコトバアリキ
「私はアスカが何をやってもいいと思ってるしどうしたっていいと思う。私はアスカがよくやったと思うもの」
そう、みんなにそう言って欲しかった。(でも言われたくない。みんなに役立たずと思われる。)
もう疲れたの。自分を作ってるのは疲れたの(でもそうしたかったのは私。本当の自分を見られるのが嫌だったから。弱い奴だ、つまらない奴だって思われるから。)。
「じゃ、本当のアスカはどこにいるの?」
本当の私はいつも泣いてただけ。ただそれだけが私。
「パパ、ママ…」
アスカの目に涙が光った。
***
「どうにも嫌な空気だ」
車の中でトードが呟く。時間的にはまだ宵の口と言った感じだった。雨は上がっていたが、生暖かい湿気を帯びた空気が不快感を誘う。
「トードさん、どうすいません。わざわざ」
シンジが助手席で謝る。
「別にいいさ。これもお仕事だからな」トードは何気なく言ったが、シンジの表情が一瞬曇ったのを見逃さなかった。不審には思ったが、あくまで無関心を装った。ギアをニュートラルにしてエンジンはかけたままにしておく。
「それじゃ、いってきます」
そう言ってシンジが車から出ていこうとするのを、「おい」と言って止める。
「こいつを持っていけ」38口径のアートマティックを、銃身を持って差し出す。
「え?」シンジがたじろいだように声を出す。
「念のためだ」短くそう言い沿える。「使わないにこしたことはないがな」
シンジはおずおずと銃を受け取ると、軽く頭を下げて車から駆け去って行った。
病院の夜間出入り口に向かうシンジの背中を見送ると、シートをリクライニングさせ、ラジオのボリュームを大きくした。
前世紀の軽快な流行曲がラジオから流れてきた。
***
病院内に入ったシンジは早々に異常を感じた。まず警備員がいない。多少良心の咎めを感じつつも中に入ると、事務の人間もいなかった。ただつい先ほどまで人がいたような気配がした。受け付け口から離れ廊下に出ると、そこは非常灯のみが照らす薄暗い空間だった。
ポケットからペンライトを取り出すと、それを点灯する。気休め程度の明りだが、ないよりはいいだろう。
三階へ行くつもりだったが、どちらの方角に行けばいいか分からず、迷う。取り敢えずつたない方向感覚に頼って歩く事にした。
頼りない灯りのみをたのみに人気のない廊下を歩いていると陰欝な気分になってくる。なにか得体の知れないものにふと背後からひきずり込まれる、そんな気分になる。
暗闇を見つめていると、何故か嫌なことばかりが思い出される気がした。
人間が暗闇を恐がるのは、闇の中では自分以外に見るものがなくなってしまうからではないか、自分の見たくない奥底を覗いてしまうからではないかと、そんな考えが浮かんできた。
それよりなぜ夜とは言え人一人見かけないのだろうか?気になって途中のナースステーションを覗く。無断で病院内に入っている罪悪感も手伝って、何か悪いことをしてるかのように覗いたそこには、やはり誰もいなかった。あからさまに変ではないだろうか?
しかし今さっきまで人がいた形跡は明らかにある。デスクの上の飲みかけのコーヒーカップを手にとると、やんわりと暖かさが伝わってきた。
書きかけのカルテの上にボールペンが転がっている。
これはどういうことだろうか?いずれにしてもアスカが気になった。
アスカの部屋へ急ごう…そう思い、エレベーターへ向かう。暗闇の中を急ぎ足で歩く。闇への恐怖は消えたわけではないが、だいぶ薄らいでいる。足の動きにあわせリズミカルに動くペンライトの灯りに集中する。
そのうちすぐにエレベーター前に着いた。しかしそこでも異常はあった。現在エレベーターが何階に止まっているかを示すランプが点灯していなかった。エレベーターを呼ぶための上向きの三角のついたボタンを押しても何も反応がない。もう一度押したが反応がないのは同じだった。
それでも反応がないかと、焦って何度も押してみる。そのため人が近付いてるのに気がつかなかった。
「だれ!?」
女の声とともに何者かのものと思われるライトがシンジの視界を奪う。声でかろうじて女と言うことが判るものの、ライトの灯りのまぶしさに目を奪われて、それ以外は一切判らなかった。ただ女だということで、反射的に看護婦だ、と思った。
「ごめんなさい、誰もいなかったので…」
シンジが言い訳じみた言葉を吐いた。ただその返事は意外なものだった。
「碇君!?」
不意に自分の名前を呼ばれたことでシンジは動転した。「え?あ、はい!」
そしてその時始めて相手の声に聞き覚えがあることに気付いた。
「ひょっとして…榊さん?」
相手は返事をしないで近付いてくる。しかしそのおびえのない足取りは、シンジの問いに対する肯定の返事の様だった。
暗闇に慣れたシンジの目に、ぼんやりと整った少女の顔立ちが見えて来る。
「碇君、ほんとに碇君なのね?」確認するその声には、安堵の気持ちが感じとれた。「よかった、誰もいないと思ってたけど、よかった…」
少女の肩から、緊張が抜けてくのが判る。
「榊さん、どうしてここに?」
シンジが驚いたように聞いてくる。
シンジの問いに、ユリは返答に窮した。まさか髪の白い男の子を追ってきました、とは言い出しにくかった。
「その…ちょっとね」言葉を濁す。「それより碇君こそどうしてここに?」
「その…」一瞬シンジも言葉につまる。この前気まずいまま別れてしまったのはアスカの病室でだ。それを思い出させるのは何か嫌だった。しかしシンジには誤魔化すというような器用なまねはできなかった。「…アスカの病室に、用事があって…」思わず視線がユリからそれてしまう。
「そう…」ユリも視線を逸し、力なく答える。やはり気にしてるのが見た目に判る。
しばしの間沈黙が支配する。お互い相手の出方を伺ってるようだ。
「あの…」沈黙を破ったのはシンジの方からだった。
「なに?」少し慌てた様子を見せてユリが答える。
「その…こないだはごめん」視線をそむけたままシンジが言った。
ユリは無言のままそれに首を振って応える。「いいの…悪かったのは私だもの…」
そう言った瞬間の彼女の顔から、今までの表情が消えたと見えたのはシンジの気のせいだったのだろうか?
「それより、用事はいいの?」
そう言われ、シンジはアスカの事を思い出す。
そうだ、アスカは大丈夫か?
どこかおかしなこの状況で、アスカの身の安全を確認しなければならない。そこまで考えて、シンジはユリもこの異常に感づいているかが気になった。
「榊さん、ここに来るまでに、誰かに遭わなかった?」
「いいえ」ユリは即座に否定する。「碇君に遭うまで、誰も見かけなかった」
そうだろう。ここには重要人物が入院している。もし誰かがいたらユリはここに入れなかったはずだ。
どうすればいい?アスカの身は心配だ。しかしユリをつれてこのまま行くわけにもいかない。それにやはりトードにも知らせた方がいいのだろう。
「いったん外に出よう」
シンジは思い切って言う。
ユリがはっと息を飲む。「でも…」未練げに言った。ここで外に出てしまうと、白い髪の少年を見失ってしまう可能性がある。そうしたらここに来た意味も…
迷うユリの姿を見て、シンジも不安になった。
「何か都合が悪いの?」シンジが聞く。
「ううん」慌てて否定する。見知らぬ男の子を追ってきた、などということを話すわけにはいかない。言ったとすれば、彼女の髪と瞳のことまで話さなければならなくなる。彼にはそのことを知られたくない、と強く思った。
「そう」シンジの方は大して不審がらずにユリの言葉を素直に受け入れる。ユリは詮索されないのにほっとする反面、自分のおかしなそぶりに気づくほどにはシンジが自分に注意してくれないのを残念に感じた。
「それじゃ行こう」シンジがそう言った時、ユリはふと頬を風が撫でる感触を覚えた。人の気配、それもすぐ近くを通った感覚だ。思わず後ろを振り向く。しかし誰もいなかった。
そんなユリをシンジが無言で不思議そうに見つめている。ユリはそんなシンジの視線に気がついて、悪びれずに言った。
「今、人が通った気がしたけど…」
シンジの体が硬直する。
「やだなぁ、そんな訳ないじゃないか」
表情がややこわばったまま言う。
「そうね、気のせいね」
そう言って再び歩こうと一歩踏み出す。その時、また何かの気配がした。今度は物音だった。微かに聞こえる何かの音。最初は耳なりとも思ったが、神経を集中すると人の声にも聞こえる。
「またどうしたの?榊さん」シンジが振り向いたその時、ユリは一瞬シンジの後ろをパジャマ姿の男性が通るのを見た。入院患者であるらしく、頭部に包帯を巻いている。
「碇君、後ろ」
「え?」シンジが後ろを振り向くと同時に男の姿もすっと消えた。しかしその姿は瞬間、シンジの目にも入っていた。
「見た?碇君」
ユリが言う。意外に落ち着いた声だ。
「見た…気がする」シンジが動転するのを必死で押えようと、考えながら言う。
今のは気のせいか?気のせいだと言えばそんな気もする。判らなかった。
「とにかく、早くここを出よう」
シンジがユリをせかす。取り敢えず当面はそれが最善の様に思えた。
駆け足で出口に向かう。先ほど入ってきたガラス製の夜間用の出入口だ。しんじが扉に手をかけ、そして思いっきり引っ張った。しかし扉はピクリとも動かなかった。両手をかけて渾身の力を込めて引いてみる。しかし少しも動こうとはしなかった。鍵がかかってる、というより扉そのものがその位置に固定されてる様だった。
「下がって!」
シンジはそう言うと、トードから預っていた銃を引き抜く。扉の金属部分の鍵の部分と思われる部分に狙いをつけ、引金を引く。轟音とほぼ同時に、鈍い金属室の跳弾の音がした。シンジはすぐにその部分を見る。しかし微かに傷がついてるだけだった。
「くそ!」
そう吐き捨ててガラスの部分目がけ、三度銃を撃った。いずれも硬質の音がしただけで、ガラスにはひび一つ入ってなかった。
重要人物の入院してる場所だ。このくらい想像してしかるべきだったのだ。
「仕方ない、別の出口を探そう」
シンジがそう言ってユリの方を見ると、ユリが表情を凍らせていた。そのはずだ、何時の間にか辺りは人々の雑踏で包まれていた。入院患者や看護婦もいる。普通の買いもの姿の主婦もいる。昼の病院と同じような、しかしどこかおかしな風景がそこにはあった。
「なんなの?これは…」
ユリがつぶやく。シンジは最初いきなり現われた人々をただ呆気にとられて見るだけだったが、そのうち何故奇妙に感じるかがわかりだした。まず人々の中に明らかにこの場に相応しくない格好の人間がいる。迷彩服の軍人なんて、野線病院であるまいしうろうろしてるわけがない。
そして二つめに、明らかに彼ら全員がシンジたちがそこにいないかの様に振舞ってることだった。病院内に銃を握りしめた少年が立ってる。このことに注目するどころか、そもそもシンジたちの存在にすら気付いてないようだった。
そんな中で一人だけ、彼らをじっと見つめてる視線があるのにやがて気がついた。
十歳くらいの少年が、じっとシンジたちを見ているのだ。
最初ただ偶然シンジたちの方を見てるかと思ってたが、しかしシンジたちを見てしきりにくすくす笑っている。
シンジは意を決して少年に近付いていった。彼に聞けば少しは状況が判るかもしれない、そう思ってのことだった。しかし少年の数m手前まで来て、シンジは急に足を止めた。暗がりで今まで判らなかったが、少年の髪と瞳の色に気がついたのだ。
白い髪、赤い瞳…それはシンジにある人物を思い起こさせた。
かつて唯一シンジに積極的に好意を寄せた人物、シンジに裏切りと罪を教えた使徒…
「カヲルくん?」
もちろんそんなわけはなかった。しかし容易に渚カヲルを連想させるその風貌は、シンジに心臓を掴まれるのにも似た痛みを与えた。
「人を捜してる…」
少年が口を開いた。誰が人を捜してるというのか、一瞬迷った。しかし次の瞬間、それが自分のことだと悟った。少年が意外な人物の名を口にしたのだ。
「惣流・アスカ・ラングレー?」
驚きで一瞬恐怖も忘れた。「アスカを知ってるの!?」
しかし少年はその問いには答えず、ただくすくすと笑うだけだった。
そしてシンジが再び同じ問いを発しようとしたその時、少年はコツ然と消えた。
ユリもシンジと別の意味で呆然としていた。あの少年、ユリが追ってきた少年は、いきなり目の前で消えたのだ。それはそういうことだろう?ユリの失った記憶と関連があるのだろうか?
「榊さん、ごめん!」シンジがいきなり大声で言った。「やっぱりアスカが心配だ、見てくるからここで待ってて!」そうとだけ言うと、いきなりシンジは駆け出した。
「碇君!」
後に残されたユリが叫んだが、シンジが振り返ることはなかった。
***
「始まったようだ」
布団の上で丸く蹲るように寝ていたシンハが言う。
「何がだね?」
同じ部屋に泊り込んで原稿を書いている大滝が聞いた。
シンハは今、大滝の所属する大学の宿泊施設に泊まっていた。大滝は自宅に泊めて色々話を聞こうとしたが、いかんせん狭いアパート暮らし、シンハを泊める部屋の余裕はない。だからこうやって大滝がシンハのいるところに泊まっているのだ。
「またいつもの、宴だよ」
「例のアダムとやらかね?」大滝が書きものの手を止め、大きく伸びをする。「夢ではないのかね?」
「いいや、違う。私には判る」シンハが断言する。
「しかし君の言うように、そんな大規模な行方不明事件があったとしたら、何かしら話題になるはずではないかね?」
そうは言いながら、大滝はこの前見た夢を思い出していた。あまりに現実感のない夢。しかし夢の中で出会った人物の一人が、妙に生々しい存在だったのを良く憶えてる。
あれはおそらくシンハが近くにいたから、見た夢だと思っていた。
「そうかもしれない。しかし私は自分の確信することの方を信じる」そしてシンハは言葉を一端切る。「そういえば、日本では原因不明の行方不明のことを、「神が隠した」ということにする俗説があるそうだね?」
「『神隠し』のことかね?昔ならいざしらず、今ではただの言い回しだよ」
大滝が言下に否定する。
シンハはため息をついた。「神隠し、か…」
***
今流れてる曲名は何と言っただろうか…流れてくる歌詞からAm I the same girl.という曲名を思い出した。
ふと、外に人の気配を感じた。シンジが戻ってくる時間にしては早すぎる。トードはベルトに挟んであるリボルバーを静かに抜き、安全装置をはずす。上半身を少し持ち上げ、窓の外の様子を横目で見たが、何も異常はなかった。気の所為か、そう思い直し再びシートに身を沈める。
「お隣、よろしいかしら?」
いきなり隣から女の声がした。思わず反射的に上半身を捻り、銃口を助手席に向ける。
助手席に現れた女は銃口を覗きながら、敵意はない、と言うように両手を軽く上に挙げている。
「夜這いかい?姐ちゃん」
そう言いながらもトードの口元は引きつっている。
なんだ?この女は?
何時の間にこの車に乗った?
そもそもドアの音なんかしなかったぞ?
体勢を直しながら疑問が浮かんでくる。トードは女を上から下まで一瞥した。
年齢的には若い、と言えるだろう。24、5に見える。着衣は革のタイトスカートに、上半身は赤のジャケット。ロングの髪は肩の下辺りまで伸び、目元はサングラスで見えない。ただ首から下げている十字架のペンダントが印象的だった。
「驚かせて申し訳ないとは思ってるわ」
女が手を上に挙げたまま口を開いた。
「おい、勝手にしゃべるんじゃねえ」
どこかで見た顔だと思いつつ、トードが銃身を突きつける。
女は銃には殆ど注意が行ってなかった。しかし明らかになにか焦ってる様子だった。
「ごめんなさい。でも急いでるの」女はそう言って挙げた手を下げ、トードの銃を持つ手に触れようとした。
その時トードは、冷静に考えればどうかしていたとしか言いようがなかった。銃身を突きつけられてそんな行動に出た女の方もどうかしていたと言える。が、トード自身もなんでもないはずの女の手に脅威を感じた。以前感じたことのある種類の、どうしようもないほどの脅威を。
引金を引いたのは脊髄反射と言っても良かった。女の冷ややかな指がトードの手に触れたのが先だったか、轟音が響いたのが先だったか。
女の背後のドアの窓に小さな穴が穿たれた。この至近距離から撃ったのだ。人体を貫通するのは当然だろう。
その発砲音に、むしろトードの方が−銃声など聞きなれてるはずの−トードの方が驚いてる様だったが、その結果も驚くべきものだった。
女は、銃口と窓の間に挟まれてるはずの女の体には傷一つついていなかった。
これはどう考えるべきだろう?弾が女を避けてったか弾が女の体を何もないかのように通っていったか、だ。どっちにしても有り得そうにない。が、その有り得そうもない話が目の前で展開されたのは事実だ。
「てめぇはなんなんだよ」
銃をさらに押し付ける。また発砲しても同じ結果であろう事は予想がついたが、他にとるべき行動が思い付かなかった。我ながら馬鹿みたいだ、と思った。
しかし女の方もおとなしく両手を挙げる。銃を恐れてる様子はない。あくまで敵意はない、という意思表示のようだ。
「あなた、シンジ君の護衛でしょう?」
女が口を開いた。
「だったら?」
女の口からシンジの名が出たことにまた驚きつつも、トードは平静を装う。
「シンジ君が危ないの、早く連れ戻して、ここから立ち去って」
女の口調はせっぱつまった様子だ。しかしいきなりそんな事を言われてもピンと来るわけもなかった。
「なんだよ、それは。第一アンタは何者だ?」
引金に掛かった指に力がかかる。
「私が何者かより、早くシンジ君を連れ戻しなさい!」
女が叱咤する。命令するような口調ですらある。トードは銃を握ったまま、シンジの去っていった方を見た。おかしいのは薄々気づいていた。いくら夜の病院と言っても静かすぎる。しかしこの静けさが何の予兆というのだろう。それに…
「アンタの事思い出したぜ。アンタ確か元NERVスタッフの葛城…」
そう言って振り向いた時、助手席の女の姿は消えていた。というより初めからそこにいなかったようだ。ただ窓にあいた穴だけが、先ほどの痕跡として残されていた。
トードはすぐさま後ろの座席から細長い革製のケースを引っ張り出した。ファスナーを一気にあけて開き中からショットガンを取り出す。銃のチェックをして、弾を込めた。
「何か知らねえが厄介なことになってきたな…」
闇を睨んでぽつりとつぶやいた…。
***
「碇君!」
逢魔ヶ刻の悪夢の中で、ユリは叫んだ。しかし駆け去っていったシンジには届かない。今逃げるだけなら簡単だ。そしてそうすべきなのも判ってた。しかしそうしなかった。できなかった。
今ここで逃げたらシンジをおいてけぼりにしてしまう、それだけでない。自分の正体についても重要な手がかりを失ってしまう気がしていた。
だから逃げるわけにはいかない。ユリは喧騒の中をシンジの後を追って追いかけていった。
ただ不気味という以外は別に害はない。恐れるほどのことはないのだ。そう自分を励ましてるところに、自分を無視していない、むしろ凝視するような視線を感じた。
ユリの進路の真正面にさっきの白い髪の少年がいる。
ユリは速度を次第に緩め、少年の前で立ち止まった。
駐車場側の壁全体が窓になっていて、採光するようになっている廊下だが、こんな真夜中ではかえってひたすら濃い闇に飲まれる気がした。
「あなた誰なの?」
ユリが彼に問う。
「アダム」
少年は答えた。
アダム?外国人の子?いや、違う。この名前にはもっと別の意味がある。アダム?最初の人類?
「あなたは何者なの?何故私と同じなの?」
思わず口をついて言葉が出てしまった。同じ?そう、同じなのだ。髪と瞳の色が同じと言うだけでない。彼は彼女と『同じ』なのだ。彼女の中の何者かがそう告げているのが判った。しかしその問いを聞いて、少年の顔からにやけた笑いが消えた。
「判らない」どこか淋しそうにつぶやいた。「あなたは僕を知らないの?」
知らない、普通ならそう答えただろう。しかしこの少年には何故か外見上の類似以外の、自分とのつながりをなにか感じていた。これは理屈ではない。
「わからない…ひょっとしたら知ってたかも…」
それを聞いて彼はうつむいた。
「そう、あなたも自分が誰か判らないんだね…でも、」少年がユリを正面から見すえる。「きっとあなたも僕の中に来れば、何か判るかもしれない…」
え?
ユリが疑問に思う間もなく少年がユリの方に手を伸ばして来た。
私には、何もないもの
自分の声で自分にささやく自分の言葉。でもこんなこと言った覚えがない。
生きるとは『死んでいく』ことなの…
また自分が自分にささやきかける。思わず耳を塞いでうずくまった。
だから、
シニタイ
「嫌!」
まぎれもない自分の声に叫び声であらがう。
この世に残るこの体が私。でも私は私でないの。
だから、
キエタイ
「嘘よ!」
しかしそう言う自分の言葉は空気の震動以上の意味は持ってなかった。抵抗の手段にしてはつたなすぎた。そうなのだ、相手は自分なのだから…
人と人とのつながりが、私が私であるということ。
でも私にはそれが
ない。
あるわ!心の中で否定する。父さん、母さん、クラスのみんな、劇団の人たち、みんな私が人である証拠、この世に生きてる証…
うそ
自分が否定する。
そう、そんなの嘘よ。私の中には本当は誰もいない。だから私は誰でもない。劇団に入ったのも人に勧められたから。少しは空虚な自分がいなくなると思ったから。
思った通り、恐怖を忘れようとするかのように演劇にのめり込んでいった。でも、役を離れればやっぱり虚ろな自分がいる。
あなたは誰?私は誰?
私は私。でも私がわからない。私って何?何のために生まれたの?
前に母に自分がどうして生まれたのか聞いたことがある。答えは保健体育の授業で習うような話、そしてどこかで聞いたような一億分の一の奇跡の自分の話。
違う、私が聞きたかったのはそんなことじゃない。
私が生まれるかもしれなかった、生まれないかもしれなかったのは確率。
今私がここにいるのは確実。
一億分の一はただの数字、私が知りたかったのは分母の大きさじゃない。
分子の、ただ一つの『一』の意味なのだ。
私、なにすればいい?どうすればいい?
生き方がわからない。
こうやって悩むこと自体に現実感が感じられない。痛みも夢の中の痛みのよう。
生きることと死ぬことはいっしょ?いいえ、でも私は死にたくない。でも何故か判らない。生と死の間で常にゆらいでる自分がいる。
あの急に現われた人々のことは言えない。自分も同じようなものなのだ。
そしてその生と死の狭間にあるのが
『孤独』
生まれるときも死ぬときも人は一人。でも、でも…
その瞬間、外から差し込んだ明るい光が目を刺し、現実へと引き戻す。
赤いランドクルーザー、それがライトを消すと運転席にトードがいるのがわかった。。ジャスチャーでその場を離れるように言っている。
はっとして少年の方を見ると、少年はただ不思議そうに車の方を見ていた。
ユリは慌ててその場から離れた。
一旦車はバックでずうっと下がっていく。そしてぴたっと止まったかと思うと、いきなり全速で加速しだした。
タイヤとアスファルトの摩擦音が悲鳴の様に響く。そのまま廊下の窓めがけ突っ込んで来る。スピードはゆるまない。ゆるまないどことかむしろ上げて来る。そのまま窓の手前の歌壇を乗り越え、こちら側の少年目がけ突っ込んで来た。
瞬間、
すさまじい衝突音、車のフロント部分のひしゃげる音。さすがに窓がたわんで悲鳴をあげた。
衝突の瞬間、運転席にエアバッグが広がっていた。トードはそれに手をかけると邪魔だとばかり一気に引きはがす。止まったエンジンを再始動する。
一度、二度とセルモーターの音がしたあとでようやくエンジンがかかった。
再度バックで下がり、もう一度車体で体当りをしてきた。再度の衝撃に、今度はさすがにガラスにひびが入った。もう一撃くらわせば砕けるのは確実だった。
トードはそうしようと、キーを捻る。しかし今度はセルの音がほんの少し鳴っただけで、エンジンは生き返ろうとしなかった。
少年はそんな様子を喜劇でも見るかのように眺めてる。
「くそ!」
トードは毒づいてコートとショットガンを引っ張り出して車外へと出ると、コートの内側から拳大の何かをとりだし、ピン、と何かを引っ張るしぐさをするとそれを窓の方目がけなげつけて来た。
それは一度窓に跳ね返ると、こん、と車のひしゃげたボンネットの上に落ちる。それは緑のパイナップルのような形をしていた。
少年が不思議そうにそれを見て近付いた瞬間、閃光と、轟音と共にそれが弾けた。建物全体が震えたような震動がし、ガラスが千々に吹き飛んで爆風が一気に流れ込んでくる。
その音と、爆煙にユリは視界と聴力を奪われた。
あの少年は!?トードは!?ユリは急いで煙の中にその姿を求める。
しかし中には何も見えない。独特の硝煙の臭いが鼻をつん、と刺した。やがて煙がはれてくると、うすらぼんやりと少年のものらしきシルエットが見えてくる。
無事?まさかあの爆風とガラスの破片の洗礼の中で?
その時、ぐおん、とうなるようなエンジン音がした。車のものではない。もっと軽いエンジン音だ。煙の中の少年がむくりと起き上がる。やはり無事なのだ。
しかしユリはなぜかそのことを喜ぶ気にはなれなかった。
少年がエンジン音に疑問を抱き、吹き飛んだ窓の方をぼんやりと眺めてた瞬間、その煙の中から何かがとびこんできた。
バイクに乗ったトードがめちゃくちゃになった車のボンネット上から病院内に飛び込んで来たのだ。バイクががくん、と床に着地する。オフロードのバイクだった。おそらく駐車場にとめてあったものを直結で動かしたのだろう。トードは着地してすぐさまショットガンを少年目がけ撃つ。
少年の体が後ろに弾かれ、そのまま背後の壁に叩きつけられる。しかしトードはそれを見ても攻撃の手を緩めなかった。
ショットガンのポンプ音と発射音がリズミカルに交互に繰り返される。
少年はそれを玩具の鉄砲弾を避けるように両手を顔の前で交差させてよけるようなしぐさをした。やがて弾が尽きる。と、同時に少年が何もなかったかのように起き上がった。
「やっぱり駄目か」
トードがつぶやいた。
「トードさん!」
少年の動きに危機感を抱いたユリが足を踏みしめ叫ぶ。足元で砕けたガラスの破片がじゃりじゃりと鳴った。
「くっ!」
トードはアクセルをふかし、バイクでユリの方へ走って来た。エンジン音が病院の廊下に響く。
「掴まれ!」
逃げる勢いのまま、トードはユリを拾って片手で抱え上げる。手が腹に当たった瞬間さすがに衝撃を感じたが、ユリもトードに必死にしがみついた。
そしてトードの後ろへ移動する。
「小僧は…碇シンジはどうした!?」
トードが叫び声でユリに聞く。
「病室へ、アスカさんが心配だって…」拾い上げられる時に腹に受けた衝撃に、苦しそうにしながら言った。
「やっぱり…しょうがねえな」
そう言ってバイクを止める。辺りを見ると、ユリたちがさっき見た人々がまだいた。しかしユリたちに気付いてないらしいのは相変わらずだった。
「なんだ?こいつらは」
トードが顔をしかめて言う。あれだけの騒ぎがあったのに、何も気付いた様子はない。その事実だけで不気味なものを感ぜざるを得ない。ショットガンの先をのばし、一番近くを通りかかってた人物に触れてみようとする。しかし触れてるはずなのに蜃気楼の様に手応えがない。向うも触れられたことに気付かない様だった。まるで悪い夢だ。
「判らない」
ユリは狐につままれたような表情のトードに向かって、首を振るしかなかった。
トードは奇妙な人々の雑踏を眺めるのを止め、後ろを見たが追ってくるものはいない。周りの連中も無害の様だ。取り敢えず安堵した。トードはエンジンをかけたままで、ショットガンの弾を詰め替える。無造作に上着のポケットに手を突っ込み、取り出したショットガンの弾を慣れた手つきで詰めていく。
「トードさん、このオートバイ、どうしたんですか」
ユリが聞く。この状況ならもう少し他に聞くことがあるのでは、と自分でも思うのだが下手に聞くとただ絶望的状況を知らされるだけの気がした。
「非常時の徴収だ。領収書は内務省にでも回してもらうさ」トードはショトガンを無造作にユリに渡した。「ちょっと持っててくれ」
ユリは無理矢理渡された銃を、こわごわ抱えるしかなかった。
トードはと言うと、そんなことに無頓着に辺りを眺め、階段の位置を確認した。「嬢ちゃんには悪いが送ってる暇がねえ。このまま小僧を迎えにいくぜ」そう言ってエンジンをふかす。
「え?」
ユリが聞き返そうとした瞬間、トードは階段目がけバイクで突っ込んで行った。
「喋るなよ、舌噛むぜ!」
「きゃあ!!」
ユリが悲鳴を挙げると同時に、バイクは勢いをつけて階段を駆け登って行った。
***
シンジは階段を登る途中で下の喧騒を聞きつけていた。
やはり戻ろうか?そうも思ったが、やはりアスカの無事を確認するまでは戻るわけにはいかない、そう思い直した。
銃を握りしめたまま階段を登り、三階へと至る。やはり誰もいない。シンジは嫌な予感を押え、アスカの部屋へ向かった。
「アスカ!」
シンジはアスカの名を呼びながら病室へ飛び込んだ。
しかしそこには誰もいなかった。窓ガラスがなくなり、蛍光灯も割れて飛び散っている。何か騒ぎのあったあとの様だが、今は不気味なほどの沈黙につつまれていた。
何があったんだろう?割れた窓の方に近付く。ベッドを見ると、シーツはめちゃくちゃで暴れた痕跡がある。手あたり次第にものが壊されているし、注射器が床に転がってもいた。
窓から外を見るが、月が輝いてるのが見えるだけだった。
「どうしたんだろ、アスカは…」
背後でクスクス、と笑い声がした。はっとして振り向くと、さっきまで誰もいなかったベッドの上に少年がいた。一階で会った、白い少年。
「君、アスカはどこにいるの!?」
シンジは問いつめようと少年に近付いていく、が、部屋の入口から急にライトで照らされた。思わず目をそらす。
エンジン音がする。
「小僧、こっちへ来い!」
バイクの上からトードが叫ぶ。シンジは言われるままにトードの方へ行った。
トードはバイクの後ろのユリからショットガンを受けとると、二人に下がれ、と言った。
「でもアスカが…」
シンジが言おうとするが、ユリがシンジの肩を掴む。
「とにかく今は下がりましょ」
シンジもそれで黙らざるを得なかった。今はそれどころではない、ということらしい。
シンジとユリは廊下に出た。
「もっと後ろに下がってろ」
トードにうながされ、更に下がる。トードの額には油汗が流れていた。
いきなり銃を構えたかと思うと、少年目がけショットガンをぶっぱなす。とにかく弾のつづくかぎり撃った。窓が割れ、チェストが砕ける。しかし少年はあいも変わらず平然としていた。
効果なしと見ると、舌を打ってショットガンを投げ捨て、おたけびを挙げてバイクで少年目がけ突っ込んでいった。
「うぉぉぉぉぉぉぉ!!」
少年にぶつかる直前、バイクから横へと身をなげ出す。バイクだけが少年に覆いかぶさる様にぶつかって行った。少年はバイクに巻き込まれベッドから落ちる。
「くっ」
少年はバイクの下から逃れようともがいたが、そのとき、バイクのクラッチに引っかけられている奇妙なものに手が触れた。緑の、パイナップル型のもの。
トードの方を見ると既に廊下の方へ逃げている。
病室が爆風に巻き込まれた。
***
ここはどこだろう?アスカは目を覚ました。
今のは何だったのだろう?誰かの声がした気がするが。
「大丈夫?アスカ?」
ベッドの外からママの声がする。
ううん、嫌な夢を見ただけ。
「そう、じゃ、もう一度ゆっくりおやすみなさい」
うん。
アスカはそう答え、再び眠りに堕ちていった…。
***
「トードさん、まだ中にアスカがいたかもしれないのに!」
まだ煙と粉塵が舞う中でシンジがトードに怒鳴った。
「馬鹿やろう!まだそんな寝言言ってるのか!?それどこじゃなかったのがわからねえかよ!」
トードが怒鳴り返す。
「だって、だってアスカが…」
うわごとのように繰り返すシンジに、トードは小声でくそ、と吐き捨てた。
「言いたかねえが、奴がいたってことはたぶん、惣流・ラングレーは…」
そう言いかけて、はっと煙の中を見る。中に誰か立ってる。あの少年だ。
「アスカは、アスカはどうしたの!」
シンジがそれに気付かず聞き返す。
「もう、いないよ」
少年がつぶやいた。
「え?」
シンジが始めて少年の存在に気付き、振り向く。
少年は片手で自分の胸の辺りを押えて、首を振った。
その仕草が何を意味してるかは判らなかったが、ただこの少年がアスカに何かしたということだけは判った。
一瞬、世界が静まり返る。心臓の鼓動だけが響く。それは段々と早まっていった。
「うわぁぁぁぁ!!」
鼓動が限界まで早まった時、シンジは銃を持って少年に突っ込んでいた。気がつくと少年を狙って銃を構えてる自分がいた。何故かためらいなく引金が引ける、そんな気がした。
が、引金に力がかかった瞬間、少年からシンジの方に飛び込んできた。あっと言う間もなく目の前に少年がいた。
少年はにやっと笑ってシンジの銃を持つ手を押える。
そして、文字通りの悪夢が始まった。
***
「お前は一体誰なのだ?」
ゲンドウが聞いた。
僕はあなたの息子のシンジです。
「今は何をやっている?」
何も。ただ普通に生活してるだけです。でも前はエヴァンゲリオンのパイロットでした。
「何故エヴァに乗っていた?」
父さんが、みんながそうしろって言ったから。乗らないと、みんな死んでしまうから。
「ではお前はもういらないな。なぜならもう使徒はいないからな」
そうやって人を物のように平気で捨てるんだね、父さんは。
「必要がなくなればいらなくなる。当たり前のことだ」
父さんはいつもそうだ。綾波さえいればいいんだ。いや、綾波すらも本当は必要ないんだ。父さんは、母さんだけが欲しかったんだ。
「そうだ、私とユイは愛しあっていた。だからユイの願いを受け継がねばならない」
違う、それは父さんの願いじゃないのか!?
「使徒はアダムへ還ろうとした。人もまた自らを生み出した存在へと還るのだ」
どうしてそう父さんはいつも勝手なことばかり…
「人は皆、母なる存在へと還ろうとするのだ」
母さんは、父さんの母さんじゃない!
シンジは叫んだ。
彼は彼の目の前にいる存在、自分の父親であり、母を奪う男である人物を睨んだ。
どうして父さんは僕から母さんを取り上げるんだ!
***
「ちっくしょう!小僧、返事をしろ!」
トードがシンジに向かって叫んだ。しかしその呼びかけにシンジは答えようとしない。リボルバーを取り出し、少年目がけ狙いをつける。
「駄目!碇君に当たる!」
ユリが絶叫した。
「大丈夫だ。この距離なら外さねえ」
そう言って、引金を引く。38口径が火を吹き、弾丸が少年を貫いた…はずだったがやはり何の効果もなかった。
今にも少年がシンジに触れそうになる。トードはいつぞやの黒猫のことを思い出してぞっとした。
とにかくシンジを奴から引きはがさないことにはどうしようもない。
一か八かだが…
準備もなく奴の精神攻撃に突っ込むのは危険だが、やるしかなかった。
「しょうがねえ!」
そう言って二人目がけ突っ込んでいった。
少年に近付くにつれ、脚が重くなっていく。誰かに脚を引っ張られるようだ。骨のような指の感触がはっきりと伝わる。
幻覚に違いないと思っていてもあまりのリアルさにぞっとした。
「ちきしょう!死人が生きてる奴の足引っ張るんじゃねえ!」
トードが吠える。
かっと顔面が熱くなった。同時に鋭い痛みが走る。とても幻覚とは思えなかった。
幻覚に違いない!
そうは思っても、この圧倒的な痛みにより呼び起こされる現実感は消しようがなかった。思わず顔に手を伸ばす。
顔に触ると、鼻の傷から血が吹いていた。見ると、目の前に迷彩服を着た女が、サバイバルナイフ片手に立っていた。女にしては筋肉質の体、短く刈り込んだ髪。緑の迷彩服で軍人であることが判る。
手に持つナイフから血がしたたっている。そうだ、あのナイフでこの女は俺の顔の傷を作ったんだ。
表情を映さぬ女の顔が、その沈黙がトードを責めていた。あの時は、ただ止めようとしただけだった。しかし顔面をナイフで薙ぎられ、かっとなった。しかし殺すつもりなんてなかった。
「ち、違う」トードはその女を見てうろたえ始めた。「俺はお前を止めようとしただけなんだ」
自分の足が一歩、また一歩と恐怖であとずさりしているのに、トードは気がつかない。
女は何も答えないで近寄ってくる。脇腹から血がにじんでいた。
何時の間にかトードの手にナイフが握られてる。そうだこのナイフで刺したんだ。あの女を刺したんだ。
「俺はアンタを殺す気はなかったんだ…」
トードがうわごとの様に言った。
「いいや、殺したのさ」
別の声が聞こえた。見ると見覚えのある顔が並んでる。
「お前は敵だけでなく、味方まで殺したのさ」
そう言った顔は、中米で半年前、奴と…アダムとあった時に一緒にいた仲間だった。
あの時逃げ込んだ小屋には全部で五人いた。しかし出てきたのはトード一人だった。
一人で逃げ出したのだ。
「なのにどうして、お前は生きてるんだ?」
そう彼らは言った。
***
どうして僕には母さんがいないの?とシンジは言った。
でも僕は母さんが恋しい、と言ったりはしない。
僕は良い子にしている。
なぜなら母さんが恋しい、と言って、みんなを困らせないからだ。
だからみんな僕を大事にすべきだ。
でも良い子ならそんなことを考えない。そんなことを考える僕は悪い子だ。
だからそんなことを考えてはいけない。
自分を罰しなくてはいけない。
でも悪い子なら自分を罰したりしない。
だから僕は良い子だ。
本当はどっちだ?
どうして誰も僕を安心させてくれないの?
ミサトさん?
リツコさん?
アスカ?
綾波?
加持さん?
母さん?
父さん?
みんないない。そうだ、アスカは?アスカはどこだ?
「あの女はもういないわ」
そう言ったのは綾波の声。
「あなたは彼女を救えなかったの」
嘘だ!どこかにいるはずだ!
「どうしてそんなにこだわるの?」
アスカには僕しかいないから。彼女を守れるのは僕だけなんだ。
「違うわ。彼女に碇君しかいないんじゃない。碇君には彼女しかいないの」
違う、そうじゃない!
「違わないわ。彼女を守る。それが碇君の大義名分に、依存になってたのに気付かない振りをしてるのね」
違う!
「おまえなどいらない、帰れ」
ゲンドウの声が言った。
やめてくれ、どうして僕を否定するんだ!?
「あなたを否定するのはあなたよ」
違う。
「あんたバカ!?私にあんたなんか必要なわけないじゃない!」
アスカの声が響いた。
違う…
「お前を必要とする者は、ここにはいない」
と、ゲンドウ。
ちが…う…
シンジは何時の間にかしゃがんで泣き崩れていた。
自分、自分。融けてしまった自分、何も出来なかった自分、逃げ出した自分、自分を好きになれなかった自分、父さんに捨てられた自分、そして虚勢を張らなくてはいけない自分…
もはや自分にはどこにも居場所はないことを痛感した。
だから泣くしかなかった。
「何をやってるの?」
綾波の声がした。ふと目の前を見あげる。そこには制服姿の綾波レイが立って、紅い双瞳がシンジを見下ろしていた。さっきまでの声だけの綾波とは雰囲気が違う。どこか、安らぐような気がする。
「何を恐がってるの?自分自身が恐いの?」
自分自身?
「そうよ、これらはあなたの声よ。あなたはそれを恐がってるの」
恐がってる?そうだよ、だって誰も僕を見てくれないんだ。
どこからか小さく目覚しのベルの音が響いている。
「良く目を開いて回りを見て。あなたの回りにも人はいるわ」
じりりりり…ベルの音が大きくなってきていた。
「目を覚まして、碇君」
ベルの音が耳障りな程大きくなっていく。いや、ベルの音ではない。何か澄んだガラスがひび割れてくような音。きれいだが、神経に触る。
碇君、碇君!
シンジは目を開いた。目の前に綾波の顔がある。
「綾波…」
綾波!?シンジはがばっと跳ね起きた。綾波は驚いたような顔をしている。いや、綾波じゃない。榊ユリだ。
「大丈夫?碇君?」
ユリが心配して聞いてくる。
「え?何が…」
記憶が混乱する。何があったんだっけ?
周りを見回すと、粉塵が立ち登り、廊下の内装が引きはがされてる。
そうだ、あの男の子。
何者?
アスカは?
トードは?
記憶が甦り、一辺に疑問が湧いてくる。
「うう…」
トードのうめき声がする。声の先で、倒れていたトードがゆっくりと上半身を起こした。
「何があったんだ?」
頭を振りながら言う。トードもさっきまで意識が不明だったようだ。
「わからない、いきなりあの子が…」ユリがそう言って廊下の奥を示す。そこには少年が驚いたような顔で立っていた。
意識のない間に何かがあったことは確からしい。しかしそれが何かわからない。
少年はじっとユリを見つめる。
「何をやったの?」少年が言った。
「判らない!私は何もやってない!」
ユリが半ば狂乱状態で叫んだ。
少年はユリの答を無視して、手を前に伸ばして広げる。
「こうやった?」
そう少年が言うと同時に、空気のひび割れる様な音がする。目の前に幾何学的な光の壁が発生した。シンジはそれに見覚えがあった。
「ATフィールド!?」
少年が手を前に押し出すと、光の壁もそのまま彼らの方目がけて押し潰さんばかりに飛んで来た。
シンジたちには避けてる暇もなかった。
「いやぁ!」
目の前まで迫った壁に、ユリが叫び声を挙げる。それとその壁が四散するのと同時だった。壁は空間がひび割れるような音を立て、霧散していった。
そんな馬鹿なはずはなかった。ATフィールドを無効化出来るのは、ただ一つのもの、ATフィールド自身しかないはずなのに。
恐怖を感じる暇もない。全ての出来事が現実味を帯びず、何か悪い夢の様だった。
「僕は、僕たちは一体何なの?」
少年が怪訝そうな表情でユリに問いかけた。
「判らない、私は何もしてない。何も知らない…」
ユリは泣き出しそうになっていた。
目の前で起きた悪夢、それを今引き起こしてるのは自分であるかもしれないというこのこと。その事実が自分を世界から引きはがす様な錯覚すら覚えた。
「お願い、私の側に来ないで!」
ピン、と何か針をはじくような音がする。
「女泣かせてるんじゃねえよ、ガキのくせに」
トードが、ピンのすでに抜かれている手榴弾を握り占めていた。その手榴弾を少年めがけて投げつけた。
少年には投げつけられたそれがどんなものか、もうわかっていた。はじけるもの。
別に少年にはどうということはないが、あの音と光にはびっくりする。だが、爆発するとさえ判ってれば…
少年はその手榴弾を受け止めようと、手をそっちに伸ばす。
と、同時にトードが38口径のハンドガンを引き抜き、あ、と言う間もなく引金を引く。
少年の手に触れるか触れないかのところだった。少年には発射された弾丸が手榴弾を貫くのが見えた気がした。
そして再び、轟音が病院中にとどろき、爆風が彼らを覆った。
***
「おーい、生きてるか?」
トードが瓦礫の下からコートの裾を引っ張りながら呼びかける。
さっき少年のいたところは完全に天井が落ち、瓦礫に埋まっている。
ま、これで奴が死ぬわけはないがな…
しかし、少年が再び現われる気配はない。とりあえずあきらめてくれたのだろう。
「ここです、トードさん」
ただよう塵のせいで視界の悪い、そんな中から声がした。ユリだ。
「大丈夫か!?」
トードが声の方へ近寄っていく。ユリは半泣きの状態ながらも、なんとか堪えていた。
「私は大丈夫、けど…」
そう言うユリの側から声がする。その声にも元気はないが、それと別になきじゃくる声がしていた。
シンジだった。
「どうかしたのか、小僧?」
トードの声にもシンジは答えない。
何故泣いてるのだろう?アスカを守れなかったから?約束を守れなかったから?
それもあるかもしれなかった。しかしそれだけではなかった。
どうしようもない孤独感が彼を襲っていた。
遠くでサイレンの音が聞こえる。しかし今更何をしようというのだろう?もう手遅れなのに。
彼はこの夜、3年前と変わらぬどうしようもない自分を見つけ出していた。
***
chapter 9:Twilight World
novel page|prev|next