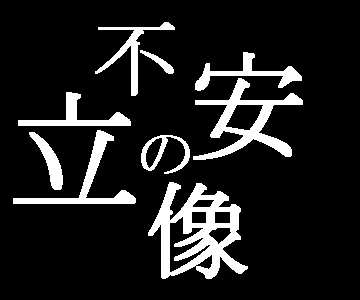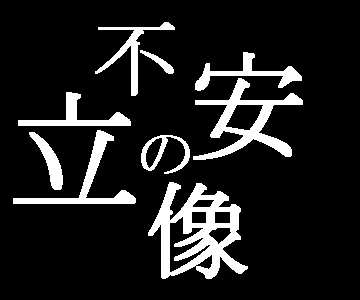
第7章:不安の立像(前編)
水の上に浮かんでる女の人…白い服を着て、頭から血を流してる。
黄色い水の海から上がった彼が最初に見たものはそれだった。
それから自分は何者なんだろうと考えた。
しかしそれは判っているのに気付き、次に何をすべきかを考えた。彼を迎える可き仲間は既に地上にいないのを、彼はいかなる手段を用いてか、知っていた。
しかし、このどうしようもない焦燥感はどうだろう?何かをせねば。しかし何をすれば?
彼は取り敢えず水に浮かぶ彼女に呼びかけた。
僕はどうすればいい?
すると彼女が答えた。
知らないわ。あなたが何をすべきかは知っていた。
でも今何をすべきかは知らないわ。
彼はもう一度尋ねた。再び彼女は答えた。
知らないわ。私は寒いの。私の心のすき間から私の命が洩れていくの。
彼は命の果てた彼女の体を取り込んだ。彼は彼女でもあり、彼女は彼でもあった。
彼女は、赤木リツコと言った。
次に彼は歩いていった。とにかく、この押し込められたような狭い空間にいるのは息がつまった。
途中で女の人がぐったりとしていた。赤いジャケットを着て、十字架のペンダントが下がった胸には赤いバラの様な血の跡がついていた。
誰?
彼女はまだ微かに息があった。
誰でもいいわ。
彼女は言った。
全ては終ったの。
彼女が何者か、赤木リツコという、彼である彼女も知っていた。
葛城ミサト。一人で寝るのが淋しい女。父親を求めつつ、父と共にいるのが不安な女。
一人はいや。でも誰かといて、裏切られるのもいや。
彼女はそう言った。
だから彼は彼女も取り込んだ。
どんどん歩いて歩いて、彼は何時しか地上に出ていた。空には光々と月が輝いていた。
彼はそれを見て、無性に悲しくなった。
あれだ。
彼は思った。
あそこに、僕の欲しいものがある。
そう思った。彼の名はアダムと言った。
***
「ちょっと、シンジ君見なかった?」
プリントの束を抱えた少女が掃除中の教室で聞いた。
「あぁ、東ならたった今、帰ったよ」
教室で掃除をしてた男子生徒の一人が答える。
「また、妹さんのお見舞なのかな…」
少女は不安そうに考え込む。
「なんだ、川津。またシンジの心配か」別の男子生徒が言った。「心配するだけ無駄だぜ。さっき彼女と一緒に帰っていったからな」
「彼女?」川津の眉がぴくっと跳ね上がる。「何よそれ?山本君」
「このガッコの生徒じゃなかったなぁ」モップによりかかり、彼は答えた。「ま、少なくともお前よりは美人だったしな」
「いままでそういうのがなかったのが不思議なくらいじゃないのか?」別の生徒が続ける。「性格は優柔不断だけど、顔はいいしな、東は」
「川津だって、そういうところにくすぐられたんじゃないのか?いわゆる母性本能って奴…」山本が最期まで言い終らないうちに、川津はモップを奪いとり、彼の顔に押しつけていた。
山本はモップを払いのけると、川津に掴みかかろうとした、が、その動きは彼女の涙目に気押されてしまった。
「うるさいわね!勝手なこと言わないでよ!」
半分涙声で言う。
「わ、わりぃ」
思わず謝る。
「でもさ、あの娘なんか変だったぜ」側で見てた同級生が場をまぎらわそうとするように言った。「あの娘、シンジのこと碇って呼んでたぜ…」
もし川津が「彼女」を見ていたら、彼女の顔に何かを感じただろうか?
「ごめんね、碇君。学校までおしかけちゃって」
「彼女」はシンジと一緒に歩道を歩きながら、シンジに謝った。
「いいよ、気にしてないから」シンジが言う。「それと、"シンジ"でいいよ」
「この前会った時、学校しか聞いてなかったから」
シンジがいいよ、と言ったにも関わらず少女は続ける。
「本当に気にしてないから。えーっと、榊さん」
苦しそうに自分の名前を思い出すシンジを見て、クスリと少女が笑う。
「ユリ、でいいわよ」
「う、うん」戸惑った様にシンジが笑いながら答える。正直、彼女が学校にシンジを尋ねて来た時はびっくりした。彼女とは一度きりの縁だと思ったからだ。
しかし、一つふに落ちないことがあった。彼女は学校名を聞いた、と言ってるが、あの時彼女には自分の名前しか言ってないような気がする。
だが絶対にそうか、と言われるとそうでない気もする。第一シンジに聞かずにどうして彼女がシンジの学校を知ってるというのだろう?
多分忘れてるだけだろう、とシンジは思った。
「悪いけど、これからアスカの病院にいくんだ」
学校に来たユリに、シンジはそう言った。しかしユリはそれで引き下がりはしなかった。
「じゃ、私も一緒にいくわ」
そう答え、半ばむりやりシンジについてきていたのだった。
「ねぇ」道を歩きながらユリが聞いてきた。「アスカって、誰?」
「え?い、妹だよ」ある程度予想していた問いに、しかし戸惑いながら答える。彼女に真実を偽るのは何かためらわれた。
そしてそっと彼女の顔を伺いながら付け加える。
「入院してるんだ」
「それはそうよ。でなきゃお見舞なんかできないもの」
シンジの言葉尻をとらえ、またクスリと彼女が笑う。
「え?あ、そ、そうだね…」
シンジはそれに愛想笑いで応える。そして彼女の横顔を眺める。
それにしても似てる。目の色、髪の色、そしていつも温和な表情を浮かべてる以外は瓜二つだ。
以前リツコがシンジに白子のことを話してくれたのを思い出した。先天的に皮膚や髪の色素を作る能力を欠いた個体。多分綾波がそういうものなのだろう、と思っていた。
母さんの顔は憶えてない。しかし、たぶん若い頃の母さんは白子でない綾波みたいだったのではないか、と綾波の正体を知る以前から漠然と思っていた。そう、目の前の少女の様に…
「どうしたの?私の顔、何かついてる?」
シンジの視線に気付き、少女がシンジの顔を覗き返す。
「い、いや。別に…」
何かやましい所があるかのように思わず目をそむけてしまう。そんな自分に軽い苛立ちを憶えた。
その時クラクションの音が背後からした。二人とも、何とはなしに振り返る。
赤いランドクルーザーが一台、シンジたちの後ろにとまり、中からサングラスをかけたトードが手を振っていた。
「いいんですか?僕を尾行してるんじゃなかったんですか?」
トードに勧められるままに車の助主席に乗り込んでから、シンジは聞いた。
聞かれたトードはいつもの調子で肩をすくめる。
「別に。俺の仕事はボウズの護衛だからな。こっちの方が好都合さ。それに…」バックミラーに映る一見サラリーマン風の二人の男を見る。一人があわててトードのランクルを指さし、もう一人が携帯電話をかけている。「ちょいと長瀬のおばさんへのいやがらせだな」
「トードさん、長瀬さんの味方じゃなかったんですか?」
シンジが意外そうに聞く。
「俺はお金の味方。長瀬のねぇちゃんとは、雇用主と被雇用者の関係にしかすぎんさ」
「ねえねえ、尾行とか、護衛とか、何?」
後ろの座席からユリの問いに、シンジはぎょっとした。うっかり彼女がいることを忘れていた。
しかしトードは慌てず答える。
「実はこのボウズは某国の王子様なのさ」シンジを目で示す。「で、俺は王子様を守るスパイって訳だ」
「何、それ」少女が笑い声をあげる。「第一護衛の仕事はスパイじゃなくて、ボディーガードがするものでしょ?」どこまで本気にしてるのか判らない調子で切り返してきた。
「ここんとこせちがらい世の中だからな。仕事を選んじゃおれんのさ」
トードは肩をすくめた。
「じゃ、スパイさん」少女は続けた。「もっと高報酬で雇われたら、裏切るの?」
「金額によるな」トードは答える。「端金で雇用主を裏切ると、あとあと困るんだよ、このギョーカイは」
「あの、トードさん」シンジが会話の輪に加わりにくそうに、言い出した。「トードさんって傭兵の人なんですよね?」
いきなりの真面目な話題に、トードは少し面食らったような顔をした。
「ああ、そうだよ。長瀬に聞いたのか?」
シンジは黙ってうなずき、そして続ける。
「その、聞いていいですか?」
「何を?」シンジの重苦しい雰囲気に、トードもつられ気味になる。
「どうして傭兵になったんです?」シンジが思い切った様に言った。
トードが一瞬声をつまらせる。そして口を開いた。
「他に選択肢なんかなかったからな」
そう言う表情には、どこか淋しげな笑いが浮かんでいる。
「選択肢がなかったって…」シンジが繰り返す。
丁度信号が赤になり、車を一時停止させた。その間にトードは話しだした。
「セカンドインパクトの時な…」トードは正面を見たままだった。「家族で旅行中だったんだよ。インドの方で。セカンドインパクトのその日は、ベナレスから帰りの空港へ向かう列車の中だったんだ。あとは何が起きたか大体判るだろ?あの状況で、日本政府の救援なんか期待できなかったしな。出来ることはなんでもやるしかなかったのさ」
一度そこで言葉を切り、そしてためらったあとに続けた。「生きるためには」
シンジがトードの傷だらけの横顔を凝視する。
「じゃ、家族の方は…」
「その時に、一人残らず、な…」
シンジはうつむいた。
「…すいません」
「いや、いいさ」返ってトードが慰めるように言う。「正直、俺も家族のことは良く憶えてないんだ」そうだった
と思い出す。一番最初の記憶は横転した列車の前で自分が泣き避けんでたところだった。
「記憶、喪失なんですか?」後ろから、急に重苦しくなった会話に沈黙していた少女がおずおずと口を挟んできた。
「いや、そういうわけでもない」信号は青になっていた。トードはギヤを入れ換え、クラッチを離した。「自分が日本人だってこととか、日本語とか、その時旅行中だったってことは憶えてるんだ。ただ色々ありすぎて、昔のことは思い出すことはなかったからな…10歳より前のことは、思い出せなくなっちまったのさ」
「10歳の時、事故にあったんですか?」
シンジの問いに、そうだ、と答える。
「セカンドインパクトが18年前だから…」少女が指を折って数え出す。「え?じゃ、オジさん、28歳なの?!」
「おじさんたぁなんだ、おじさんたぁ!」トードが後ろの座席に向かって哀願するように抗議する。「俺はこれでも若いんだぜ。お兄さんと呼べよ」
シンジもトードの顔を眺める。顔中に浅い傷跡が残ってるし、髪や肌は日焼けにまかせ、荒れている。とても28には見えない。彼と長瀬でどちらが若いかと言われれば、間違いなく長瀬を選ぶだろう。
今までどんな人生を歩んできたのだろうか?
「おい、ボウズ、何か言ってやれよ!」
いきなりトードがシンジに振ってきた。
「え?え?」慌てたシンジはしどろもどろした。「そ、そうですね!思ったよりお若いですね!」
トードががくっと肩を落した。
***
「他の生物を駆逐してまで、生きなければならないの?本当に?」
冬月の目の前の碇ユイの顔をしたものが言った。
「そうだ、手段など選んではいられない。我々には時間がないのだから…」
同様に碇ゲンドウの顔をしたものが言った。
「なんだこれは…」冬月はつぶやく。しかしそのつぶやきは目の前の二人には届かない。
二人ともそこに冬月がいないがごとく振舞っている。いや、実際に彼らには見えないのだろう。
彼らは冬月の知っている者の姿をしていた。しかし、それが本人でないのは明らかだ。冬月はこんな場面を過去、見たことがない。
「夢、なのか…?」
その現実感の剥離した感覚は、まさしく夢そのものだった。
「そう、これは夢なのだよ」
不意に隣に人が現れた。いや、今まで気がつかなかっただけかもしれない。中年太りのその男は、冬月の方を見た。
「これは確かに私の夢なんだが…でも、君は知らないな」
男が言った。冬月も男を知らなかった。
「夢は過去の経験の再構成にしかすぎんはずなのだがな…あるいは君はユング的解釈による、老賢者かね?」
冬月は夢の男の言葉にむっとした。
「君が私の夢の産物かどうかは知らんが、人を老人扱いとはひどいのではないかね?」
男が面食らった顔をした。
「これは驚いた。夢の産物にしてはエキセントリックな反応をしすぎるわい」
「だから私は私だよ。現実にも確かに存在してる私だよ」
冬月は言う。それに男も答える。
「しかし私も確かに現実に存在してる私だ。いや、実は私は君で、私はそれを夢の中で外から見てる私ということもありえるな」
「夢が醒めればいずれかが消えると?」
冬月が問い返す。
「ま、そうかもしれんという話さ。いずれにしても、コギト・エルゴ・スム、さ」
我思う、故に我あり、と男は言った。
「まぁ、いい」冬月も二人の方向に向き直った。
二人は芝居のようにやりとりを繰り返していた。
ゲンドウ「手段は選んでいられない。我々が滅ぶかどうかの瀬戸際だ」
ユイ 「だからといってこの星の原住生物をないがしろにしていいというものではないわ」
ゲンドウ「君の同胞は我々か?彼らか?君はB計画の主任だからと言って、原住生物に入れ込みすぎだ」
ユイ 「それとこれとは話が別です」
ゲンドウ「原住の生物群に対し人為的に進化に手を施し、その発生、生体、を調査するB計画、所詮は脆い器を持つ者達にすぎん」
ユイ 「いずれにしてもあなたのA計画は現行のままでは危険過ぎるわ。再検討を要請します」
ゲンドウ「その必要はない。全て予定通りだ」
急に舞台が変わった。一瞬閃光が走るのを見た後、何時の間にか彼らは地表にいるのを知った。熱と吹き荒れる風で地表が引き剥されていく。
そしてその爆心には、4枚の羽根が天に向かって突き立っていた。辺りに風のちぎ鳴りのような、悲鳴のような音が鳴り響く。
しかし不思議と地表が引き剥されるような風にも関わらず、彼らは平然と立っていられた。やはりこれは夢だと確信した。
「これは…セカンドインパクトか!?」
冬月の隣人が言った。
「いや、これは違うぞ…」そう言ってから冬月は男に振り向いた。「君はセカンドインパクトの真実を知ってるのかね!?」
「知人に聞いた」男はそっけなく答える。「それより酒は持っとらんのかね?喉が乾いてきた」
「そんなもの持ってる訳がない」冬月は呆れながら答える。「ここが君の夢だとしたら、自由に出せるのではないのかね?」
「うん、それもそうだ」冬月に言われ、男は着ているポロシャツのポケットに手を突っ込む。ぺしゃんこのポケットからポケットウィスキーの瓶がひきずり出される様はシュールだった。男は蓋をあけ、そのまま口をつける。そして冬月に瓶を差し出した。「あんたもどうだね」
冬月はさっき男が口をつけたばかりの瓶を見ると、眉をしかめて答えた。「けっこうだ」
「おや、そうかね」そう言って男は再び飲み始める。
「第一、夢の中で飲んで、酔えるのかね?」
奇妙なことに、冬月はこの夢の産物でしかないはずの男の人格を認めはじめていた。
「まぁ、酔った気分にはなれるだろう」
男は答える。
二人は目の前に再び目を向けた。
舞台はまた変わっていた。今度はゲンドウ、ユイに加えてキール・ロレンツの顔をした男もいた。
キール 「A計画の実験失敗により、地表の30%が焦土と化し、60%が吹き払われた。サンプルとしての原住生物は、そのおよそ90%以上が死滅している。更に重大な事には、事故に巻き込まれ我々の同胞2名が消失したということだ。何かいうことはあるかね?碇君」
ゲンドウ「実験は失敗したのではありません。成功したのです。2名の死者は予想外ですが、それとてたいした問題ではありません。貴重な一歩への殉職者なのですよ。ほぼ予定通りです」
キール 「委員会の決定を伝える。A計画は無期限凍結、今後はB計画をメインにする。碇ゲンドウの責任は重大だが、人材不足及び過去の貢献により、その罪は問わない」
ユイ、手を挙げる。
キール 「なんだね?ユイ君」
ユイ 「それではC計画はどうなるのでしょう?」
キール 「A計画による被害が甚大だ。今の所遅延が重なってるC計画にまで手を伸ばす余裕はない。計画再開の目度は立ってない。その他細かい処置は追って知らせる。以上だ」
ゲンドウ「はい」
ユイ 「はい」
舞台が変わる。
冬月は隣の男に聞いた。
「君は彼らを知ってるようだが?」
「彼らとは、彼らかね?」間の抜けた答を返す。「ああ、知ってる、というより知ってる人間の姿はしてるな」
「何時何処で碇やユイ君やキール議長に会ったのかね?」
冬月の言葉に男はけげんそうに振り返る。「何?」
冬月がもう一度繰り返す。
「碇やユイ君やキール議長と、どこで知り合ったのかね?」
「誰だね?それは」
今度は冬月が面食らった。
「誰って…君は知ってると言ったばかりではないのかね?」
「確かにあの三人は知ってるが、そんな人物を知ってると言った憶えはないぞ」
不満そうに男は言った。
「ちょっと待て、何を…」そう言いかけて冬月ははっとした。同時に男も気がついた様だった。
「…そうか、我々は同じものを見てるが、同じ様に見えてるとは限らないわけか」
男が自分に言い聞かせるように言う。
「どうも、そういうことらしいな」冬月も賛同する。「君が私の夢の産物でないということも信じかけてきたよ」
「私もだよ」男も言った。
二人は再び前に目を向けた。
ユイ 「アダム・カドモンは最初の一体を残して破棄。残る一体も爆心地であった極地の地下に封印。C計画の施設は地下施設ごと上空に避難させられた、か。これがあなたの望んだ結果なの?」
ゲンドウ「少なくとも君の望み通りではないのかね?」
ユイ 「どうしてあなたはそういう風にしか見れないの?私がA計画の凍結を喜んでるとでも?」
ゲンドウ「これで、君のB計画がメインになったのだからな」
ユイ 「…委員会では早々にA計画の凍結解除が上申されるそうよ」
ゲンドウ「だろうな。老人たちとて、アダムの強い生命力、学習能力、自己修復、及び進化の能力は魅力的だろうからな」
ユイ 「生き物としての強さは、肉体の強さだけではないわ。種は、一個体だけでは種ではないのよ。群になった生き物の強さ、を忘れては困るわ」
ゲンドウ「数理生物は君の本来の専攻だからな。だが奇麗事はやめたまえ。君のやってることとて、本来の種の進化をねじ曲げ、彼らを我々の都合のいいように作り変えようとしてることなのだよ」
ユイ 「……」
ゲンドウ「そう、我々の棺桶するためにね」
ユイ 「あなたのA計画では、アダムのジーン(遺伝因子)に含まれる我々のコードを解析する生物との遭遇の可能性、及びそれによる我々の種の再生の確立を全てかけあわせると、成功の可能性は10-34にも満たないわ。B計画の修正案では、彼ら自身が自己のジーンに含まれるコードを解析出来るようになる可能性を検討しても、10-32にはなるわ」
ゲンドウ「たった二桁の差にすぎん」
ユイ 「そう、でもその二桁の差は大きいのよ。でも今のあなたのA計画のプロットでは、両者が共に生き伸びることはないわ。だから凍結されたのよ。より可能性の大きい方を残すために」
ゲンドウ「弱いものが滅びる。当然の摂理だ。もし計画を修正しても同じだよ。この世の王は、世界でただ一人なのだからな。君も数理生物進化学を専攻したなら知ってるだろう」
ユイ 「しかし…」
ゲンドウ「本来ならC計画により我々の新たな肉体を築くべきだった。しかしもはや時間がないのだ」
また舞台が変わった。
「死海文書の記述通りだな…」冬月がつぶやいた。「起こった出来事は、勝手に我々の頭の中で既知の事に置き換えてるらしいが、話の筋としては合ってる」
「死海文書?」男が尋ねた。「あの死海文書かね?」
「まあな」冬月が受け流す。「しかし、どうやらA計画がアダム、B計画が我々人間、C計画というのが、あの月に眠る…」
冬月が言いかけたところで、男が興味深く冬月を見つめた。
「A計画にC計画?あんたには、そんな風に聞こえてたのかね」
どうも聞こえてるものも同じように聞こえてないらしい。しかし話の筋はどちらも一緒らしい、というのが面白い。
「君にはどう聞こえたのかね?」
冬月が聞き返す。
「そうだな、特に三つ目の奴、あんたの言うC計画は、ri na cruinneと聞こえたよ」
「ri na cruinne?」冬月が眉を寄せる。「なんだね、それは。聞き憶えのない言葉だ」
「ゲール語だよ。意味は"King of the Universe"。すなわち…」男は静かに目を閉じた。「世界の王、だ」
「ゲール語?君は一体誰なのだ?」冬月があまりに予想外の答えに思わず言った。
「民俗学の助教授をやっておってね、名は大滝という…」男はまた一杯、ウィスキーをあおる。もう空になってもおかしくないが、夢の産物だけあってまともに常識が作用しないらしい。「そしてこれは、我々の夢ではないらしいな」
novel page|prev|next