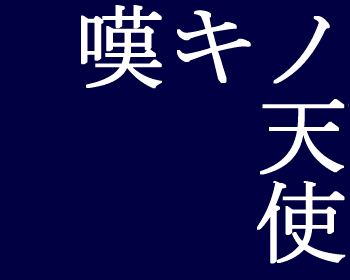 第
第
三
章
:
嘆
キ
ノ
天
使
***
「始めまして、碇シンジくん」
女はそう言った。
「誰なんですか、あなたは」
かろうじてそれだけ言う。声が震えているのに気づき、もっと平然と言えればいいのに、とそんな思いが頭をよぎる。
女はシンジの震えを見てか、微かに笑った。シンジには自分の顔がカっと熱くなるのが分かった。
「今それを言うつもりはないわ。でも私があなたをここに呼んだの」
「うそだ!あの手紙は綾波の…」そう言いかけてはっとし、口をつぐむ。女は薄笑いを浮かべたままだ。
「いいえ、あれは私が書いたの。あなたがここへ来るかどうか、あなたが本当に碇シンジ君かを確認するためにね」
顔が一層熱くなるのを感じる。確かにあの手紙には第三新東京市のことなど書かれてなかった。
つまりシンジはここに来ることで自分の身元を明かしてしまったのだ。
「でも、あの手紙を持ってきたのは…」
シンジはそう言いながら、女の全身に目を走らせる。カジュアルな薄着姿で武器は携帯してるようではない。
「あの手紙を持ってきた娘?あれは綾波レイに比較的似た子を探して、変装をさせたの。劇団の娘だったから演技は上手かったでしょう?」
女が得意そうに話すのを聞くふりをしながら、シンジは出来るだけ自然にポケットに手を突っ込んだ。「もっともその娘、自分がどんな役を演ったかは自分じゃ知らなかったでしょうけど…」
「動かないで!」
女が言いおわる前に、シンジはポケットから手を出し、叫んだ。女に向けた手には小型の拳銃を握りしめていた。
女の笑いが消える。
「物騒な物を持ってるわね」女は一瞬面食らったようだったが、すぐまた平然と言った。
「動けば撃ちます」シンジは狙いを女につけたまま少しずつ後ずさった。「脅しではないです」
「そう、ちゃんと安全装置は外してある…?」
女はまた薄笑いを浮かべた。シンジはその表情にどこか見下されてるような圧迫感を感じていた。
「安全装置は外してあります。弾も入ってますよ」
「でも君に私は撃てないわ」
「撃てます」シンジは不快感を顕わに反駁した。
「無理よ」女はそっと髪に手をやる。「だってその前に君、死んでしまうもの」
女がそう言うと同時に、チャッとこみかめにに何かが押し付けられた。
横目でそちらの方を見ると、この暑さに不似合いな緑のコートからはだけた、Tシャツに包まれた男の厚い胸板があった。
何時の間に…突然背中を取られた驚愕が大きく、その瞬間は戦慄を感じなかった。
さらに視線を上にずらすと、サングラスをかけた、黒く日に焼けた男の顔があった。
「よう」
男はシンジと目線があった瞬間そう言った。
***
「ようこそ」大滝を迎えた黒人の男は意外にも知的そうな声の青年といってもいい男だった。「どうぞ中へお入りください」薄暗いバラックの奥から声だけで大滝とガイドを招く。
「では失礼させていただくよ」
大滝は躊躇もせずに中に入り込んだ。
「さて」青年の前へ座り改めて青年を見た瞬間、ぎょっとして思わず声をつまらせた。
青年の肌はこの市場にいる殆どの人と同じく黒い。またその顔立ちはケニア族の特徴をはっきりと現していた。が、その髪のみは白い…どちらかといえば青年は元々白く、髪だけ色を塗り忘れたと言う感じすらする。
しかし大滝はその一瞬の驚きを押さえ、再び青年をまじまじと見つめた。まだ若く、皮膚に張りがある。半眼でどこを見るともない表情だが、声と同様にどこか知的なインテリ的雰囲気を漂わせてる。
これが探していた「狂った男」か!大滝は驚愕した。
「どうなされました?この髪がお気に?」
青年は大滝を見て微かに笑って言った。
「いやそれも驚いたが…」大滝は青年の微かな表情の動きも見守っている。「あんたが例の「狂った男」だというのが信じられん」
「私を疑うのですか?」相変わらず静かな口調だが、その響きには幾分失望が含まれてるようにも感じた。
「そういうわけではない」大滝はきっぱり否定する。「あんたのどこが狂ってるのか分からんだけだ」
青年の口から微かな笑いが漏れる。
「狂ってる、狂ってないは所詮主観の違いにほかなりません」静かな口調のまま語り出す。「浜辺に生える草にとってはステップの草や木は狂ってると言えるだろうし、その逆もしかり。あなたがた西洋文明の者と私たちの習慣の違いだってそうです」
「面白いことをいう」大滝が身を乗り出す。「つまり君は自分が他のものと土壌の違うものだというのかね?」
「否定はしません」
「つまりその…」適当な例えを思い浮かべようと必死で頭をめぐらす。「君は呪術師の様に別の世界を見ている、と?」
「いえ、違います」それには青年ははっきりと否定の意を表した。「呪術師とは、他人の見ているものを引き出してる者にすぎません。例えそれが一見不条理に見えようとも、同じ土壌に立つ者です。しかし…」青年は手の平を自分に向けた。「私は違うのです」
「アンタが狂った現実とやらを見たからかね?」
「そうです」
青年は臆面もなく答える。
呪術師でもないのに呪術師に関してこれだけ忌憚なくいえるということに大滝は軽いショックをうけた。普通ならば幾分の尊敬、恐れ、嫌悪のいずれか、あるいはどれもがこもってるはずなのに、この青年にはそれがない。
この青年ならかなり突っ込んだ話をしても大丈夫だろう、と踏んだ大滝はいきなり本題を切り出した。
「それはあの巨人かね?」
大滝がずばり、と言う。
青年がじっと大滝を見る。「巨人を見たのですか?」
「あの巨人のことなのだね?」
大滝は青年の反応を見ようとさらに一押しした。
「違います」
青年があっさりと答えた。
あまりにはっきりと、あっさりとした答えだったので大滝は青年の真意を却って測り兼ねた。しかし嘘ではない様子だ。
「私が見たのは「神」です。いや、神の内部です」
「神の中?」
大滝が聞き返す。
「はい、そのために私は神の一部を奪ってしまい…」
そう言いながら青年は初めて目を見開いて大滝を見た。その見詰める目を見て、もうさすがに驚くまいと思った大滝もぎょっとした。瞳が赤い、血の色をしていたのだ。
「その代償として私は私の一部を失ってしまったのです」
目を見開いたままの大滝を赤い瞳で見続けて青年は言った。
「私はそれを求めて日本まで行かなければならない」
***
「よう」そう言った男はその姿勢のまま開いている手でポケットからチューイングガムを出した。「食うかい?」
この人は何を考えているんだろう、と思った。殺す気なのだろうか、それが第一の疑問。
銃口は頭に付いたまま。その引き金にかかった指は適度に緊張しており、シンジが指を動かす前にシンジのこみかめに鉛玉をプレゼントしてくれそうだ。
しかし、かと言ってすぐ殺す気配もない。殺気がない。
男の顔を見た。一目見た時は日本人かどうか迷った。骨格のためというより肉付きが厚いためにそう見えるのだ。さらに鼻は少し不自然に平たくなってる。まるで押しつぶされたようだ。その鼻には斜めに傷痕が走ってる。よく見るとそれ以外にも顔に浅い傷痕が幾つか残っていた。
「冗談はおやめなさい、ミスター・トード」女が言う。
そう言われて男は舌を鳴らしてガムを差し出した手を引っ込めた。
「シンジ君」女が今度はシンジに話し掛ける。「私たちはあなたに危害を加えるつもりはないわ」
今のところはね、そう付け加えた。
「とにかく銃を引っ込めなさい」
女の声を合図にしたかのように男がシンジの手から銃をもぎ取る。シンジはそれに抵抗しようともしなかった。
シンジは無言で女を睨んだ。年は30くらいだろうか?先ほどは気にしなかったが切れ長な目にどことなく残酷な光りが宿る。彼女もどことなく日本人離れした容貌の持ち主だ。
ただ男と違い、彼女のそれは骨格の為だ。全体的に彫りが深く、肢体のバランスも欧米人のそれと言っても過言ではない。髪の色もやや赤茶けている。欧米人の血が混じってるのかもしれない。
シンジの視線が気になったのか、女は目で男に合図を送る。それと同時に男はシンジの頭から銃を引いた。
「何か言ったら?だんまりを決め込むつもり?」
自分の優位を確かめるように女が言う。
シンジは女を睨んだが、女の向ける冷ややかな視線に思わず目をそらした。
「僕を…どうするつもりですか?」
逡巡した後の言葉。自分でも間抜けだな、とシンジは思った。
「別に。どうもしないわ、今日のところは」
女が足元の小石を踏み鳴らし、シンジに歩み寄る。女はシンジの目の前まで来ると、シンジの顎に手を掛け、無理矢理自分の方に顔を向けさせた。
嫌でも女の顔が目に入る。意外とシンジと身長はそれほど変わらない…威圧感がそうは見せなかったのだろう。それに美人だった。
シンジは不謹慎にもどぎまぎするのを止められなかった。
「ただ知っておいて欲しいの。私たちがあなたを…あなた方を手中に入れたことを」
シンジの鼓動が早まる。アスカもか?考えれば当然だ。彼らはこの三年間、行動を共にしたのだから。
そしてひょっとしたらレイも?いや、だったら多分偽者は使わない。しかし本当に…?
相手にこちらの情報を与えないで、相手から情報を得る質問をシンジは必死で考えた。
「貴方は…政府の人ですか?」
質問につまったシンジは一番無難と思える質問をした。
「否定も肯定もしないわ」女が手を組んで答える。「そのうち分かるわよ」
シンジはそれを肯定ととった。内務省の人間。ほぼ間違いない。
女が顎をしゃくる、と男がシンジから離れる。女も湖畔から上がる道へと向かう。
「僕を、捕まえなくて…いいんですか?」
シンジは去っていく二人に背を向けたまま尋ねた。
「逃げたければどうぞ」
女の答えはあくまで冷淡だ。絶対の自信が口調に含まれていた。
シンジはその言葉に壁を感じた。自分を押し込めてどこにも逃がそうとしない見えない壁を。
「おい」いきなり今まで黙ってた男が呼びかけた。そして何かをシンジめがけ放り投げる。
それは振り向いたシンジの頭に当たり、足元に落ちた。
封は切ったものの、殆ど手付かずのチューイングガムだった。
「もう一つだけ…」シンジは体を震わせながら、息を呑み込んだ。震えてるのは恐怖のせいのみではなかった。「あなた方は僕がEVAのパイロットだったから必要としてるんですか?」
女が足を止めた。そしてシンジの方を向く。
「いえ…」女は目を細めてシンジを見る。初めての無表情。その目には何の感情も浮かんではいない。「EVAのパイロットであるから必要とするのよ」
***
「お母さん、お母さん」
少女は家に帰り、玄関で靴を投げるように脱ぎ捨てると、駆け足で台所に向かった。
「ねえねえ、昨日ね、仕事してきたんだけど、その仕事がすっごく変わってるの」
いきなり台所に入り、勢いをつけてまくしたてる少女にパート帰りの母親は呆れた様に目を向けた。
「お母さん、何か食べるものないの?」そう言いながらも、戸棚に煎餅があるのを目ざとく見つけ出していた。
「ユリ、ちゃんと手は洗った?」早速煎餅を口にほうり込もうとしていた娘に母親が呆れ顔で言う。
少女は煎餅を口にくわえながら照れ笑いをした。そして笑いながら「まだ」と答える。
くりくりとした茶褐色の瞳がよく動く。
「もう、ちゃんと洗ってからにしなさいよね」
「もう…子供じゃないってば」拗ねたように少女は言う。「でさ、さっきの話の続きなんだけど…」
「はなし?なんだったかしら」
包丁の音をさせながら母が聞き返した。
「仕事の話よ…なんだかさ、劇団の方から”是非に”って言われちゃってさ…」
「まぁ…役が付いたの?」
母の口調には秘められた嬉しさが込められていた。しかし少女は首を振った。
「ううん、違うの。手紙を持ってってくれ、って頼まれたんだけどね、松高の生徒になんだけど、そのときに変装してけって言われてね…」
「変装?」
少女はやけにうきうきした様子で続けた。
「そう、それがさ、赤のカラーコンタクトつけて、白いカツラつけてけって言われ…」
急に母親が向き直った。その表情は険しい。
「ちょっと!まさか…」
娘は少したじろいだ。
「いや、私も最初バレタと思ったんだけど、違うみたい。なんか私そっくりの娘がいて、その娘の真似をしてくれってことらしいの…」
「そう…」母親は納得したようにまた後ろを向いた。しかし内心は穏やかでなかった。
「大丈夫、ばれてないって。心配いらないよ、お母さん…」
「注意しなさいよ、前の学校じゃあなたのソレがバレていじめられたんだから」
母親はきつい口調で言う。
「平気よ。私、いじめなんか恐くないから…」ユリは努めて明るく言う。
「ユリ!」
母は思わず怒鳴る。が、本当は不安なのは自分なのだ。三年前、娘が、いや彼女が突然現れたのと同様にまた消えてしまうのではないかと…。
「じゃ、コンタクト外すから」
「今夜はもう外出しないの?」
「うん」少女はそう言って右目のあたりをまさぐっていたが、やがて手を顔から離すと、その指の先には茶褐色のコンタクトがくっついていた。
「大丈夫、母さん。心配しないで…」
彼女は右目の、赤い瞳で母を見つめながらそうつぶやいた。
***
chapter 3:A Crying Angel
novel page|prev|next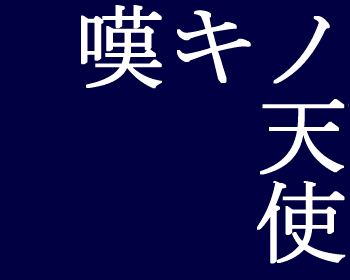 第
第