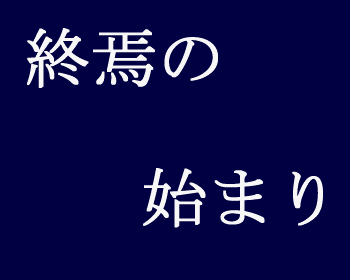 第2章:終焉の始まり
第2章:終焉の始まり
粗末なバラックの壁板のすき間から日の光が洩れてくる。
そんな中で彼は夢を見た。
とても満たされていたころの夢。
苦痛もなく、悩みもなく、あらゆる欲望から解放された世界。
あらゆる痛みが存在しない世界。しかし自分自身も存在しない世界。
それは確かに彼がかつてかいま見たものの片鱗だった。
だから彼は拒絶した。
あの時の気持ち。全き世界の支配者であった赤子の頃、無理矢理母親の胎内から敵に満ちたこの世界へと送り出された感触にも似ている。
自分と言う器など所詮ちっぽけなものだ。しかし人はみなその器にしがみつき、生きている。彼もそんな人類のひとりにすぎない。
”自分は後悔しているのだろうか?”
彼の中に疑問が浮かぶ。あの時のことを。全き世界を拒絶したことを。
その時、どこからかビートルズの"IMAGINE"が聞こえて来た。どこかで誰かがラジオを聞いているらしい。彼は耐え切れなくなって想いを別のことに馳せた。
もうすぐ彼の待ち望んでいた人物が来るはずだ。彼には合わなければならない人物がいた。その人物は海を越えた遥か先、日本にいるはず。そこへと彼を誘う人物がやがてあらわれる。
そう、もうすぐ。
***
「今日は珍しくお兄ちゃんが来ないわね」
看護婦がベッドの上から外を見るアスカにそういう。
そう、この女性が看護婦だということは判る。ではここはどこ?
どこでもいい。それでも困らないから。
看護婦は”お兄ちゃん、と言っていた。それは何?
言葉、単語、名前、人を指す言葉。
兄
Brother
Bruder?
毎日の様にアスカに会いに来る少年。回りの人は彼を”お兄ちゃん”だと言う。
だから彼は”お兄ちゃん”という人なのだろう。
(でも”お兄ちゃん”てそういう意味だったかしら?)
時々”シンジくん”と呼ばれてる。”お兄ちゃん”は”お兄ちゃん”なのに。変なの。
とても良く知ってるはずの人。でもそれはどうでもいい。
大事なのは彼の言葉、カタチ、触れる指先、そして唇のぬくもり。
唇?あの人の唇に触れたことなんかあったっけ?
あった の?あ
った?ある?あった
の か
しら ?あ
るは ?あ
るべき ?ある
とき?あらねば?
あるだろう?
すぐに疑問は中身を持たない空虚な言葉になって頭の中をぐるぐる回る。
「どうしたの?あすかちゃん、どこか痛いの?」
看護婦という人がそう言った。
何を言ってるのだろう?どこも痛くない。そんなことがどうして判らないんだろう?
彼女がハンカチを取り出して彼女に近付いて来る。
白くて細い指、
光沢のある爪先。
手、
前肢、
道具を使う肢、
人に触れる為のもの、
”お兄ちゃん”に触れる指。
”お兄ちゃん”と話す時の彼女の顔。
笑ってる。
嬉しそう。
瞳が輝く。
大人の女の目。
欲情してる。
いやらしい。
彼女の中に誰かがいる。白い顔。動かない口。声を立てて笑ってる。
声だけたてて笑ってる。無表情なまま笑ってる。
笑ってるのは私のこと。
口を開けないで、赤い口腔を見せている。その目と同じ、真っ赤な口のなか。
『命令があればそうするわ』
うるさい!
『あなたは人に褒めて貰いたくて……に………るの?』
うるさい!
『心を開かなければ、……は動かせないわ』
黙れ、人形のくせに!
床に叩きつければ砕けて粉々になるセルロイドの人形のくせに!
『……には心がある、わかってるはずよ』
自分こそ心なんか持ってないくせに!
今度はこの”看護婦”になって、また私を苛めるのね!
みんな奪って気ね!
パパも、ママも、……も、……さんも、………も、みんな私から奪ったのに、まだ持ってってしまう気ね!
顔にハンカチを近付ける看護婦の手を払いのける。彼女が驚いた顔をする。
気持ちいい。
ざまあみろ。
あんたの思い通りになんかならないわ。
「どうしたの?怒ってるの?急に泣いたりするし」
泣いてる?頬の上を暖かいものが転がる。
泣いてる。どうして?
”お兄ちゃん”のことを考えたからだ。
辛いのだろうか?
”お兄ちゃん”のことが?いや、”お兄ちゃん”だけど”お兄ちゃん”でない人のことが、だと思う。
そうかもしれない。
考えると泣いてしまうのだ。
なら考えないようにしよう。
忘れてしまおう。
簡単なことだ。
私を苛めるものは、世界からはじきだしてしまおう。
だって私が世界なのだから…
***
「よう、久しぶりだな」
大滝はその白い診療所の中に入るとまずそう声をかけた。
「なんだ、お前生きていたのか」
中にいた白衣をつけた、目に知性的な光を讃えた黒人の男が答える。しかしその顔は言葉と裏腹に嬉しそうだ。
その男はその姿から医者であることは明白であったが、首からカラフルなネックレスを掛けてるのがなんとも奇妙に見えた。診療所の壁の棚に並べられた瓶の中には様々な植物を乾燥させたもの、木の実、動物の骨が入っているものもあった。
その薬用性が怪しいものも多い。
その男がいわゆる呪医、ウィッチドクターであることは、見るものが見れば明白であった。
「悪運が強いのはお互いさまだ、マキノ」
そう言って大滝とその男は再開を喜び合うように抱きあった。
「この15年でたくさん死んだからな」マキノ、と呼ばれた呪医は感慨深げにつぶやく。「それにしてもお前がセカンドインパクトで死ななかったとは、お前についてる悪霊はよほど強力とみえる」
「なに、そんなことでくたばるような悪霊だったら、こんなところまで来て科学者なんかやってられんよ」大滝は笑って見せた。「それより診療中だろう?」
患者が不満の声をあげているのを指してみせる。
「構わん、待たせとけ。どうせ今すぐ死ぬほどの奴なんていない。いたらどっちにしても手遅れだ」
「おいおい、医者が言うことじゃないな」
大滝の言葉にマキノはかけらけらと笑った。
「それよりいつからこっちに来ていたのだ?」
「うむ、一週間ほど前からだ。二月は腰をおちつけようかと思ってる」
「そうか、まぁ今夜はワシの所に泊まっていけ。つもる話もあるしな」
「それなのだが…」大滝は歯切れ悪そうに言葉を切った。「実はお前に聞きたいことがある」
「どんな?」大滝の雰囲気の変化を察知し、マキノは姿勢を正した。
「笑わずに聞いてくれ、実は…」大滝は少し間をおいて続けた。「巨人を見た」
マキノの表情が険しくなる。
「ひょっとして、お前があれについて何か知らないかと思ってな」
「忘れろ」突然、冷たく言いはなった。
「何?」突然の言葉に、思わず聞き返す。
「お前が見たものは全て忘れることだ」
そう言って患者に向きなおる。
「さもなくば、一生そのことは口をつぐんで生きることだ」
「一体いきなり何を…」旧友の態度の突然の豹変に流石に面食らった。
「ワシにできるアドバイスはこれだけだ。悪いが今診療中で忙しいからあとでまた来てくれ…」
「待て、いきなり『忘れろ』と言われて、はい、そうですか、と出来るもんか、子供の使いじゃないんだからな…」
そのやりとりをみて、アバラの浮き出た患者がきょとんと二人の顔をのぞき込む。
「子供はもっと聞きわけがいいものだぞ…」
「理由くらい教えろ」
マキノは深くため息をついた。「お前が見たのは狂った現実だ」
「狂った現実?」大滝が聞き返す。
「そうだ。もしそのまま狂った現実を追い続ければ、お前がそれに捕らわれてしまう。忘れてしまうのが一番だ」
しかし大滝はなおも食い下がった。
「狂ってても、現実は現実だろう。現実を追い詰めるのが学者というものだ」
「お前が太陽を見つめ続ければそのうちお前の目が焼けてしまう。それは学者だろうがなんだろうが人間である限り変わらんよ…」
「ならサングラスをかけるさ」
呪医はゆっくりと頭を振った。
「だからお前たち西洋人や日本人は愚かものだというのだ。ちっぽけな力をすこし操れるくらいでいい気になって、より大きな禁断につぶされる。丁度人についてるノミのようなものだ」
親指と人指し指で丁度蚤くらいの大きさをつくってみせる。そしてそれをつぶすしぐさをしてみせた。
「その相手がいつでも自分をつぶしてしまえるということすら気付かない…」
「つぶされる前に逃げるよ」
おどけて両手を広げて見せる。
「どうしてもいくのか?」マキノは聞き返したが、返事は聞くまでもなかった。
うきうきしたような大滝の視線に、深いため息をつく。眉間には深いしわが刻まれていた。
「もしあの巨人について知りたければ、市場にいる「狂った男」を訪ねろ」
「狂った男?」
「そうだ。そう言えば子供にでも誰のことか判る」
「それだけでいいのか?」
マキノは視線を大滝からそらした。
「狂った現実に触れて狂ってしまったのだ…」
狂った?狂人?話はできるのだろうか?ともあれ手がかりは手に入った。
「すまんな、マキノ。この礼は必ずする…」
大滝は今にも小踊りしそうな様子で言った。,br>しかしマキノは荒々しく手を振った。「いらん!もし礼が出来るとしたらワシがお前に話したこと全てを忘れること、そしてワシのまえで「あれ」の話を二度とせんことだ!」そして呆気にとられる大滝を前に、マキノはうめくように続けた。「たとえこの世が悪徳と苦痛に満ちていたとしても、ワシはこの現実のほうがいいよ…」
***
シンジは湖畔にたたずんでいた。今は第五芦野湖と化した第三新東京市。かつてもこんなことがあった気がする。しかし何時のことかはよく覚えていない。
今はさびれるにまかせられ、復旧作業すら行なわれていない。地下のNERV本部も現在は封鎖され、立ち入りは一切禁止されている。
かつてここであったことが脳裏に浮かぼうとする。しかしそれから逃げるように記憶を脳裏の片隅に追いやる。
あの手紙…綾波がいるならここだと漠然と感じていた。
ここに来る前に、入院中のアスカに会ってきた。どこか虚ろな笑顔で「おにいちゃん」と笑いかける…その笑顔を見る度胸が張り裂けそうだった。
自分のことを周りから教えられるままに兄と呼ぶアスカ。彼女が治る?彼女にとっての真実など何一つない世界で?そんなことはあり得ないように思えた。
失踪工作の都合上、便宜的に兄弟ということにした。これはシンジがアスカを目の届くところに置いておきたいという希望を述べたからだった。これには賛成も反対もあった。
完全に我を失ったアスカを一人にすることは危険がある。何時身元に関することを口走るかもしれない。しかし、二人一緒では、あまりに目につきやすいのではないか?
しかし結局はシンジの希望を通す形になった。
あの時覚悟してたはずなのに…足元の砂をじっと睨む。半ば結晶化した小石が混じっていた。瞬間的に高熱に晒された結果だ。
再び綾波のことを思い出す。綾波…綾波レイ。最後に会った彼女はシンジの知ってる彼女だったのだろうか?それすらもわからない。彼女は母さんだったんだろうか?
会えるかどうかもわからない、しかし会っても何をしたいというのだろう?なにもわからないままここに来てしまっていた。
「あら、珍しい」不意に人の声がした。その声に思考を中断し振り向く。
髪の長い女の人がそこにいた。薄く色のついたメガネをかけ、こざっぱりとした身なりをしている。「こんにちは」
「こんにちは」シンジは少し緊張しながら答える。この場所で人と遭遇することは嫌でも警戒心をおこさせた。
「君も旅行中?」
「ええ、まあ…」シンジは言葉を濁す。この場を離れた方がいい。しかしこの人になんて言って誤魔化そう?自分の話し下手を今更ながら悔やんだ。
「この辺って、ほんとに何もないのね…新しい首都の予定地だったってのに」
「それは、あの災害のあとですから」水面の方を見ながら言った。
「あれで殆んど死傷者が出なかったってのは奇跡よね」
その言葉にかすかに胸がうずく。
「ところで君は何しにここへ?」
「別に…次の電車までの暇潰しです」もうそろそろ時間だから…、シンジはそう言って立ち去りたかった。実際そうするつもりだった。
「へぇ。てっきり待ち合わせかなにかだと思っちゃった」女はそわそわしてるシンジに構わず続ける。「彼女かなんかとね」
身体の震えを懸命におさえる。この人が知ってるわけはない。しかしやはりそれでも身体中に緊張、いやむしろ恐怖が走っていた。
「すいません。もう時間だから」シンジはかろうじてうめくように言うと、逃げるように視線を遠くにそらした。湖畔と道路を結ぶ細い道へ向かおうと、女とすれ違ったとき、ぽつりと彼女がつぶやいた。
「綾波レイを待たなくていいの?」
一瞬言葉の意味が理解出来なかった。無意識に解釈を拒否する。しかししだいに染み渡るその意味が身体を凍り付かすのを感じた。
恐怖に思考力を奪われつつも、かろうじてシンジは横目で女の方を見た。薄い笑いを浮かべてシンジを見つめていた。
「はじめまして、碇シンジ君」
***
chapter 2:The Bigining of the End
novel page|prev|next
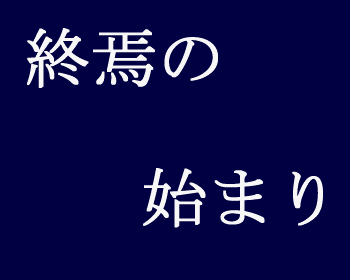 第2章:終焉の始まり
第2章:終焉の始まり