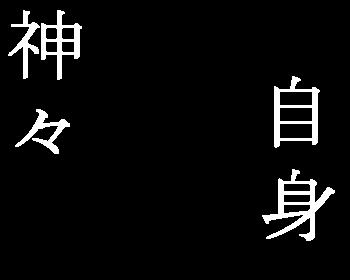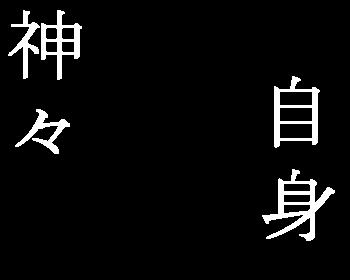
第1章:神々自身
トード、と呼ばれた男は確かにその少年に恐怖を感じていた。
今までどんな戦場でも感じたことのない種類の恐怖。
あえて言えば戦場の現実に耐え切れず、麻薬に溺れていく仲間を見るような嫌悪感に近かった。
「よう久しぶりだな」
トードは言った。そう言いながらも手の中には汗がにじんでいる。少年はきょとんとした様子で赤い瞳を彼に向けた。
やっぱり覚えてないか、そう内心思いながら、少しずつ近付いていく。
ふと少年の足元を見ると、さっき逃げた黒猫がまたすりよって来ていた。
「誰?」いきなり少年が口を開いた。トードはびくっとして足を止めた。「誰なの?僕を知ってるの?」
トードはその場に留まったまま、コート下に忍ばせたパレットライフルにゆっくりと手を伸ばした。
「僕を知ってるんだね?」少年はなおも続けた。異常を感じたのはその時だった。言い知れ様のない恐怖感が突然彼を襲った。
”殺さないでくれ”どこからか声がする。”俺も連れてってくれ…”
足元がぐいっと引っ張られる感覚がした。ふと足元を見ると、迷彩服姿の男が足にしがみついている。迷彩服の胸元からは血がにじんでいて、額にはポッカリと銃そうがあいていた。しかし何より恐怖を覚えたのは、その男はトードの知っている顔だった。
”俺はまだ動ける…”
頭の中がかっと熱くなった。
「やめろ、お前は死んでるんだ!」
逆上するあまり、あまりに非現実的なその光景に思わず叫び声を挙げ、足元にパレットライフルの台尻をうちつける。
”おちつけ!”彼の中の冷静な部分がそう囁やいた。”おちつけ、幻覚だ”
目を少年の方に向けると少年は再び猫を抱えていた。しかしその猫は顔が完全に少年の胸にめりこんでいる…そして段々取り込まれていっていた。
その異様な光景が引き起こす別種の恐怖が彼に高度を促した。
銃を構え、少年目がけ引金を引く、しかし少年は何ともない。
もう一度撃つ。今度は猫の体がはじける。少年の表情が曇る。しかしやはり少年はなんともない。
「バケモノが!」トードはうめいた。その瞬間、例の足を引っ張られる感覚にバランス感覚を崩し、その場に尻もちをつく。
”頼む、つれてってくれ…”
死人が口を開かずに言った。
「うるさい!死体はおとなしく死んでいろ!」
思わず、悪態をつきながら死人目がけ銃を乱射する。
『何やってるの!落ち着きなさい!』
耳元に響く長瀬の通信ももう聞こえていない。
『精神安定剤、投与、急いで!』
長瀬がOFFし忘れた通信から、そんな声がした瞬間、首の頚動脈のあたりに違和感を感じた。首に巻き付けてあるバンドに仕込んだ無針注射からトランキライザーが投与されたのだ。
幻覚が消え、心臓の鼓動が見る見る落ち着いていくのが判る。
『落ち着いて、現状を確認しなさい!』
忌々しい長瀬の声が聞こえる。
「現状?」
ふと少年の方を見ると、少年がすぐそばに立っているのに気付いた。
何故、急にトードが落ち着いたのか、猫のように自分に取り込まれないのかが判らない、といったふうだった。
「…!」声にならない叫びをあげて、銃を乱射する。
しかし、弾は当たってる、はずなのに、少年に変化は見えない。
少年はトードのそばにゆっくりと寄っていった。
トードは銃を撃つのを止めた。
「お前…何者なんだ!?」
恐怖を押えて尋ねた。
少年はふっと目を細め、淋しそうな表情をした。その表情にトードは一瞬恐怖を忘れた。
そして少年は口を開いた。「…アダム」
「!?」呆気にとられたトードの前で、そして少年は…消失した。今確かにいたその場から消えて失せた。
トードは暫く事態を飲み込めなかった。
やがて通信を回復させると、淡々とした様子で報告を開始した。
「こちらトード、目標と交戦後に喪失、現時点をもって作戦続行を断念。なお当方に被害なし。目標精神攻撃に対する精神安定剤の有効性を確認。処理班の出動を要請する…」
***
「始めまして、青葉一尉」部屋に入ってきた女性は開口一番そう言った。「私は内務省調査部所属の長瀬ヒロコです。現在は諸事情から戦略自衛隊にも籍をおいてはおりますが」
青葉シゲルは女性の階級証を一瞥すると、敬礼した。二本線の階級証…三佐、階級的には彼より上だ。
「本日は、自分に何の用でありましょうか?」姿勢を正しつつも、その目は明らかに警戒の色を見せている。
長瀬はその質問にすぐには答えない。「あなたの経歴は見せてもらったわ…2010年防衛大学卒業後、自衛隊入隊。2012年、自衛隊からNERVに移籍、その後2016年のNERV解体後は戦自に再度籍を移してるわね。御立派な経歴です」
「恐れ入ります」しかし目からは警戒の色が消えない。
「さて、取り敢えずお掛けになって」自分も座りながら青葉に席を勧める。青葉が椅子に座るのを待ってから続けた。「さて、私の用ですが、貴方の経歴に一部不審な点があるので、それを直接貴方の口から説明して欲しいからです」
「それは内務省調査部としての質問ですか?」青葉が言う。声の響きは変わらない。つとめて平静をたもとうとしている。
長瀬は何の感慨もなくそれに答えた。
「質問するのは私です、貴方ではありません」ぴしゃりとはねのけると、やや間を置いて続けた。「戦自への移籍前、NERVの行動に関しての査問があったはずですが、それに関する貴方の答え、どう見ても不十分なものと思えます。情報の隠蔽の可能性があります」
「それに関しては、自分は情報部の人間でしたので組織全体を把握できる立場ではなかったからです。また、査問の時には自分の籍はまだNERVに置かれておりましたので、仮にそうであったとしても、自分の知ってることを全て話す義務はないと了解しております」
長瀬は青葉に冷やかな視線を投げつけた。「ま、いいでしょう。この件は取り敢えず置いておきましょう。しかし他にも…」そう言いながら手元の資料を繰った。「NERV解体直前、貴方を含めたNERVの構成員若干名に、不審な行動がみられます」
「不審な行動、と言われますと?」
顔色一つ変えずに聞き返す。
「この時期、エヴァンゲリオンパイロット三名の所在が急につかめなくなっています。彼らの失踪に貴方が手を貸した疑いがあります」
「まさか。身に覚えがありません」
嘲笑まじりに答える。内心、自然な笑い方に見えればと思っていた。
「貴方がなんと言おうと、事実貴方が戸籍、その他身分証明書類の偽造に手を貸したと思われる形跡が残っているのです」
「なんと言われようと身に覚えのないことです」
「しかし私の手元の資料は、貴方がクロであることを示しているのですが…御覧になりますか?」そう言い、資料を差し出した。
「いえ、結構です」差し出された資料をそっと押しやった。「何と言われようと覚えのないことです」
「そう、あくまでもしらを切ると?」
青葉は無言のままで女を睨んでいる。
女はため息をついて差し出した資料を引っ込めた。
「でもね…」押し戻された資料を再びめくりだす。「疑いがかかってるのは貴方だけではないのよ。貴方の奥さん、なんと言われたかしら…マヤさんでしたっけ?」
明らかに青葉の表情が険しくなった。眉間にしわがよる。
「旧姓伊吹、NERV在籍時技術部所属二尉。解体後は戦自に移籍なされたけど一年前、貴方との結婚を期に退官なされてるわね。今現在妊娠中…あら、今御解妊なされてるのね」青葉の眉間のしわを見ながらからかうような口調になった。「おめでとう」
その言葉に、青葉の顔に苦渋の表情が浮かんだ。
「もし貴方が一切口をつぐむというなら、彼女に聞くことにしましょう。彼女もあなたもだんまりを続けるというのならそれで構いませんが、事情調取が長引くと身重にはきついでしょうね」
「嫌疑は自分にかかってるのでありましょう?彼女には関係ありません」青葉がうめくように言う。
「公文書偽造は立派な罪です。もしそれを彼女が在官時に行なったとするなら、戦自としても黙っている訳にはまいりません。それに…」長瀬は嬉しそうに目を細めた。「この件に関する調査は内務省の方に正式に委託されておりますので」
「汚いぞ、脅しのつもりか?」青葉が睨みつける。視線で人が殺せたら、と思っただろう。
「人聞きの悪い。尋問ですわ。でも内務省の尋問を甘く見ないことね。もっとも…」
彼女はもったいつけて一端言葉を切る。
「貴方が私達に協力して下さるというのならその限りではありませんが」
「お前たちの目的は何だ?」
「御協力いただけますか?」燃えるような青葉の憎悪の視線を受けながら、彼女は笑った。
***
「…だからね、それで私は言ってやったんだよ。自費で行けば誰にも迷惑はかけんだろうって…」
中年太りしたその男はそう言うとまたポケットウィスキーの瓶に口をつけた。
それをガイドのンドゥールは呆れた顔で見ている。
「どうだね?君も一杯やらんかね?」瓶を差し出しながらそう勧める。
「いや、いいよ大滝サン。わたし、運転中…」
一応謙遜するように、しかしへきえきした様子で答える。かつてはサバンナと呼ばれていたステップ地帯、今は少なからず密林化したこの場所で酒盛りをする気はない。第一急がないと夜までに夜営地に辿りつかない。オンボロのランドクルーザーを駆りながらそう考えていた。
「いやいや、私は20年以上前にもこの辺にフィールドワークに来たことがあるんだがね、やっぱりセカンドインパクトのせいで丸っきり変わってしまったよ。それだけじゃない。その時世話になった知合いは8割方死んじまってね。あの時に世界人口の半分が死んだって言うがね、そのうち実際に天災で死んだのは何割かねぇ?ほんとはそのうち半分近くはその後の暴動、内乱、民族紛争で死んだんじゃないかと思っとるよ。いやいや、天罰も恐ろしいが、人間も負けず劣らず恐ろしいからね…」
一期にまくしたてるとまたポケットウィスキーに口をつけた。
ンドゥールは合槌をうちながらも上の空だ。とはいえ、この御時世に観光でこの辺りを訪れる悠長な客はそうそういる訳ではない。ガイドの彼としては客のえりごのみなどしてはいられない。
第一、日本人に本当にセカンドインパクト後の地獄が本当に判るのだろうか?あの時は世界中がひどかったが、日本などはまだましだ。貧しい国は更に貧しくなっていた。それに引き替え、日本では内乱もない。民族紛争もない。今では食うに困ることもない。
このアフリカで年にどのくらいの餓死者が出てるか知ってるのだろうか?
が、別にそんなことは今は関係ない。自分と、それと家族の食い縁を稼ぐだけだ。
「ところでね、今度のフィールドワークで期待してるのはここら辺で新しく発生してる振興宗教のことなんだよ。えーっと、たしか世界を創った巨人をあがめているはずだったな」
「大滝サン、その話、聞いたことあるネ」彼が大滝、というとき、むしろオタキ、というふうに聞こえるが大滝もさほど気にしてる様子もない。
「うむ、ざっと彼らの神話を聞いた所、世界中に広がってる巨人解体神話に近いもののように思えるのだよ。まぁ有名なところでは中国の盤古とか、北欧のユーミルとかがあるがね。不思議なのはこの近辺でそれに類似した神話はかつてなかったということなんだよ」
ンドゥールはうなずく。確かに人づてに聞いた話は、むしろどこか外国の神話の様に思えた。
「まぁそれも不思議だがね、原始宗教の発生過程という見地からもとても面白いことだと思ってるんだよ」またポケットウィスキーに口をつけ、続けた。「日本でも最近面白い噂話が色々あってね。第三進東京市建設予定地の壊滅事件、えーっと君は知ってるかね?」
「知ってます」三年前、彼が日本にいたころそれは大変なニュースとして流れた。まるでえぐられたかのように半径数十キロのクレーターがTVのニュースで流れたのを覚えている。確かあれはイン石の落下が原因だったはずだ。
「あれがね、大変面白いことに巨大ロボットのしわざだ、という噂が中高生を中心に流れとるんだよ」
「はぁ、ロボットですか?」
「そう、まるでマンガかSF小説だろう?これも一種の都市伝説の変形と言えなくもないかもな。巨大ロボットというのは巨人、すなわち巨大な力という解釈もできるしな」
その時、急に森がざわめき出した。どこからか地響きがし、鳥の群が見事ともいえる位にぱぁっと飛び立つ。
突然のことに車を止める。
「なんだ?地震か?!」
思わず叫んで車の外に出たが、地震ではない。しかし、低い、うなる様な地響きが続いたかと思うと、突然森が大きくざわめいた。
そして彼らは見た−森から頭をもたげる、巨大な人影を−。
それはこの世の光景とはおよそ思えなかった…大滝の足元でウィスキーの瓶が割れる音も、何処か遠い世界のことのように感じた。
ンドゥールは突然はっとして車の中からカメラを持ち出すと、巨大な人影にレンズを向け、フィルムが切れるまで狂ったようにシャッターを押しまくった。
夕日の逆行に映えたそれは全身をくすんだ灰色に輝かせ数歩ゆっくりと歩んだかと思うと、再び森の中へと吸い込まれるように消えていった。
しばらく呆然とそちらの方向を眺めていた。
…あれは何だ?目の錯覚?いやいや、だったらこの森の喧騒はなんなんだ?それにあの巨人の姿…あれはどこか人工のものの様にも思えたが気のせいなのだろうか?
しばらく大滝はぶつぶつとつぶやいていたが、やがてンドゥールに呼びかけた。
「あれのことは誰にも言ってはいかんぞ…」さっそくこの件の金勘定を始めたンドゥールが不満そうな表情をする。大滝は慌てて手を振って訂正する。「いやいや、言ってもいいが、わたしは一緒にいなかったことにしてくれ。もしこんな話大真面目にしたら、それこそ学会から追放されてしまう…」
そしてうつむいたまま黙っていたが、やがて再び口を開いた。
「ところで」足元のウィスキーの染みを見つめながら言った。「酒は持っとらんかね?」
***
「東君」そう廊下で呼び止められ、シンジは立ち止まった。振り向くと、声の主は同じクラスの女子生徒だった。
「何?」
「あのさ、これ」そう言って手紙を差し出した。
「なんだ、ラブレターか?隅におけないねぇ」さっきまで一緒に雑談を交わしていた友達がはやす。
「ち、違うわよ!」女子生徒は頬を朱に染めて怒る。「少なくとも私のじゃないってことだけど」
「どうゆうこと?川津さん」
「ん、あのね…」川津と呼ばれた女子生徒は、この手紙を預った経緯を説明した。
今日、彼女は少し遅れて学校に来た。ここの所肌にアトピー性の湿疹ができ、その薬をもらいに病院によってきたのだった。正面玄関に入ると、下駄箱の彼女のクラスの所に見なれない制服の女子生徒がいた。制服も見なれなかったが、それよりも目を引いたのは彼女の容貌だった。年の頃は彼女たちと同じ位、顔立ちは美人と言え、肌は透き通るくらいに白かった…そして髪の毛も。その女生徒は川津に気付いて彼女の方をふっと向いたが、その目は血のように赤かった…。
その目に見つめられてることに気付き、一瞬ぎょっとした。
「あなた…」いきなりその少女が話しかけてきた。「シンジ君と同じクラスの人?」
「え?うん…」すぐに少女の用事が少し変わった所のあるおとなしいクラスメートにあると判った。
その返事を聞くと少女は手紙を差し出し、これを碇シンジに渡すように、とだけ言うとさっさと出ていってしまった…
「え?碇?」話を聞いて、けげんそうにシンジの友人が聞き返す。
「うん。たぶん私が東と聞き間違えたんだと思うけど」
シンジは少し躊躇した。まさか、ひょっとして、そんなばかな?
しかしやがて手紙を受け取った。「有難う」
「でも結局ラブレターなんだろ?あけて見せろよ」
そう言った男子生徒の耳を川津が引っ張る。「山本君!デリカシーないわね!」
シンジは上の空で封筒をじっと眺める。ただの白い、真っ白な封筒。宛名も何も書いてない。
封を切って、中の手紙を広げる。これも何の色気もない白い便箋。
そしてその中には
God's in his heaven,All's rigt with the world.
そして行を換えて、
カミハ目覚メヌ、審判ノトキ近シ。
と書かれていた。そして最後の行に
エデンノ東ニテ、待ツ
これで全てだった。
「なんだ?こりゃ?」手紙をのぞき込んだ山本がすっとんきょうな声をあげる。
「さあ?」シンジは冷汗が流れるのを感じながらポケットに手紙を突っ込んだ。
「何か怪しい宗教にでも絡まれてるんじゃないのか?」
「そ、そういう訳じゃないよ…」
「なんか困ったことがあったらなんでも相談してね。いろいろ大変なんだろうから」
川津が心配そうにシンジの顔をのぞき込む。
彼女の言う”いろいろ”とはアスカのことを指している。
「なんだ、川津はやっぱ東に気があるんじゃないか」そう山本が言ったとたん、川津が思いっきり山本の足を踏みつける。山本の悲鳴が響いた。
「へ、へ、変なこと言わないでよ!わ、私はただ学級委員として…」
真っ赤になってしどろもどろに釈明してる川津にシンジが尋ねる。
「この手紙を持ってきた娘、さっき川津さんが言った通りで間違いないの?」
「え?うん…だってそんな変わった娘、一度見たら見間違えようがないわよ」そう答えてからけげんそうに眉をひそめる。「やっぱり知合いなの?」
「いや、ただ珍しい娘だなと思っただけだよ」そう言いながら、シンジは心の中で自問をしていた。
どうして?
何故彼女が?
もう三年前に全て終ったことではなかったのか?
しかしいくら考えても答の出る質問ではなかった…
***
Chapter one:Gods themselves END
novel page|prev|next