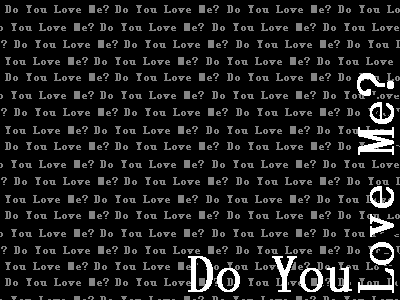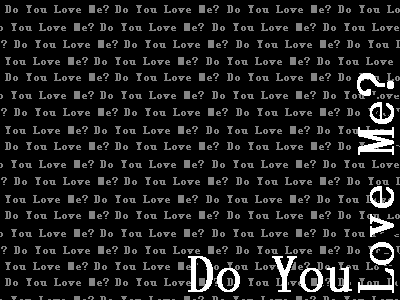
第十三章:好き?すき?大好き?
***
××日午前7時17分
北アリフカ某所にてエヴァンゲリオンとおぼしき巨大人型兵器発見。
同日午後10時48分
N2作戦により目標を殲滅。
***
「おたくの娘さんは」担任の唇が動く。「勉強の方は優秀ですし、素行にも問題はないのですが、何というか、もう少しお友達との協調性を…」
また担任がくだらないことを言っている。わざわざ親まで呼び出して面談したかと思うとこんなことだ。隣では母が涙目になりながら聞いている。
下らない。本当に下らない。小学生のことでこんなに取り乱す親も親だし、教師も教師だ。当の本人である私が良いと言ってるのだから良いじゃないの。
「やっぱり女手一つで育ててきたから…」
何を言ってるの、母さん。今時母子家庭なんて珍しくもないわ。私がこうなのは、私とあなたの責任よ。人の所為にしないで。
「やっぱり父親も一緒でないと…」
「やっぱりいけ好かないわね、今度転校してきた長瀬って娘」高校の廊下で、本人がすぐ後ろにいるとも気付かずクラスメートたちが陰口を叩いてる。私はノートと教科書を抱えていた。「向うで飛び級で大学入学の資格があっただかなんだか知らないけど、お高くとまった顔して嫌なカンジ」
「そうそう、そういえばさ、三組の藤沢があいつにオトコ取られたんだって」
「えー?マジ?」
「そーそ。ちょっと見てくれいいからって、調子くれてるよね」
あれは勝手にあっちから言い寄って来ただけだ。あんなつまらない男、相手にする気にもならない。
「取ったんじゃなくて、寝取ったんじゃないのー?」
「あ、ありがちありがち。優等生面して、サセコちゃんだったりして」
「そういえばドイツにいたんでしょ?なんかビョーキ持ってるんじゃない?」
どっと笑いが起こる。
「やっぱイッペン締めなきゃダメだよね」
「うんうん、シメちゃおか」
「ホント、場違いだよね、アイツ。さっさとドイツにかえれーって」
「だったら」あまりの下らなさに私は口を開く。「こそこそと陰口叩いてないで本人の前で堂々と言ってみたら?」
私の陰口を言ってた連中はぎょっとして私の方を見る。まさか当の本人がこんな所にいるとは思ってなかったのだ。さっきまでの勢いはどこに行ったのか、無言のまま、立ち去っていく。
本人を目の前にして自分たちの下らない自尊心を崩されたくないのだ。他人を貶めることで相対的に自分の自己評価を高めるしか術をしらない連中。本当に下らない。
そんなことをするうちに、少しでも自分で努力してるのかしら?元の出来が良いということはあるが、今の私の容貌も、才能も、私が努力して磨いたのだ。悔しければ自分も努力すればいいのだ。つまらない奴ら。
「だからアンタのはさ」彼女は居酒屋でコップ半分ほどになった日本酒を片手に私に言った。「演技じゃないのよ」
彼女はかなり酔ってる。演劇サークルの部長をつとめてる彼女は今日のリハーサルのことを言ってるのだ。このサークルに入ったのは高校の時から一緒にいることの多かった彼女の勧誘があったればこそだ。大学に入っても下らない奴が多い中、彼女はそうでもない。芸術学科で、演出等を勉強しながら将来を見据えてしっかりと地に足をつけている。しかしもうすぐ大学を中退するそうだ。某実力派俳優の主催する劇団への入団が許可されたらしい。親からは勘当同然の身になったわ、と笑って言っていた。彼女が自分の目標に前進するのは喜ばしいが、いなくなってしまうのは寂しい。
そう、寂しい。
オトコの噂も絶えないが、彼女は頭がいい。相手はそうは思ってないかもしれないが、私は彼女が好きだ。会うとケンカすることの方がむしろ多いから、向うは私がそう思ってると思わないだろう。
何時の間にか彼女はつぶれていた。私の方が酒量が多いのだが、欧米人の血が入ってるせいか私の方が酒に強い。
「アンタのは演技じゃなくって本気なのよ」ほとんどうわごとの様に彼女は呟いた。「人を殺す役で、本当に殺しかねないのよ」
「だからさ、これ以上一緒にいるとお互いの為にならないと思うんだ」
テーブルを挟んだ男の唇が動く。さっきアイスコーヒーを置いていったウェイトレスは、気を利かせて関心が無いような振りをしていたが、一瞬の目の動きが彼女の好奇心を示していた。
たしかに他人にとって痴話話は面白いだろう。当の当事者以外は。
「ヒロコと一緒にいると、なんていうか疲れてくるんだ。いつでもお互いの生活を支配しようとする。君だって疲れるだろ?」
自分の立場を正当化したいという本心が覗く。確かにこうなってしまったのはお互いのせいだ。どっちのせいでもない。しかし彼は別れ下手な方らしい。
「嫌いになったわけじゃないけど、このままじゃどっちも駄目になる」彼はやっと本題を切り出しきてきた。「別れよう」
手をつけてないアイスコーヒーの氷が、かたん、と音を立てて崩れた。
「本当にいいのね?」長瀬は契約書をトードと名乗るその男に差し出しながら言う。「一応あなたは外部の協力者ということになってます。銃器などはこちらの許可の範囲内での使用が出来、また所定のものであれば必要な時にこちらの許可を得ずして発砲が出来ます。もちろん後で報告書等を提出してもらいますが。その他勤務時における負傷等の保証の規定等も全てこの書類に書いてあります。目を通してください」
トードは受け取って軽くざっと目を通しただけで手早くサインをして突き返す。
「ほらよ」
長瀬は不真面目そうなトードの態度にややむっとしながらも、契約書類を受け取った。
「これにサインをしたからには」長瀬は警告するように言った。「あなたと私は運命共同体というわけです。くれぐれも忘れないでね」
長瀬はやっと目を覚ました。ブラインドの隙間から朝日の光が漏れてくる。彼女が上半身を起こし、リモコンでブラインドを明けると窓から光があふれてきた。
「まったく、なんであんな夢見たのかしら…」
昔を懐かしむ歳でもないのに。
ぼやいていると、ベッドからはみ出した手に猫が擦り寄ってくる。
ベッドを出て、冷蔵庫から牛乳のパックを取り出しミルク皿と、ついでにコップに入れた。ミルク皿を床に置くと、三匹の猫がキッチンに入ってきて長瀬の方を見る。
「タロ、ジロ、ポチ、おいで」三匹の猫は仕方ない、というふうにミルク皿へ近付いてくると、頭を寄せてミルクを舐めだした。
長瀬はそれを見て自分もビスケット状の高機能食品をほおばり、ミルクで飲み下す。
味気ない朝食が終ると、受話器を取って母親の所へ電話をかけた。
最初は当たり障りのない世間話と近況。
「ええ、大丈夫よ。ちゃんと食べてるってば。子供じゃないのよ。仕事も今は忙しいけど、そう、重要な時期だから。詳しくは言えないけど。うん、それでまた一週間ほど家を空けることになると思うから、うちの子たちをまたお願い。ごめんなさい、母さんも仕事があるのに。わかってるわ。気をつけてるわよ。うん、仕事が一段落ついたら遊びに行くわ。それじゃ」
受話器を置くと、ライターとタバコ、灰皿を取り寄せて新聞を広げて一服やりだす。目新しいことは何もない。一通り目を通すと、新聞をたたみまだ中ほどまでしか吸ってないメンソールを消し、朝の支度を始めた。
おそらくこの一週間のうちに辞令が下る。もっと感慨があっていいと思うのに、自分でもあっけないと思うほど何も感じなかった。
「世はすべて、事もなし、か…」
***
「部長、それで先日アフリカで殲滅した例のものですが…」移動の車中でエージェントが長瀬に資料を渡す。「被害等の概算が出ました」
長瀬は資料に目を通す。「国連も思い切った事したわね。北アフリカの一国が、壊滅的打撃を受けてるわね」
「投下地点は砂漠だったのですが、その後の政情不安による被害の方が大きいようです」
「第三世界への見せしめかしら?」
「おそらくアフリカ、中南米の発言力を弱めたいのでしょう。正式な発表はまだ後日になると思いますが…」
「取り敢えず世論はどう動くか、まだ様子を見なくてはいけないけど…日本もこうなってたかもしれないと思うとぞっとするわね」
「しかしまだ予断は許せませんね」
「国連側はもう手を出せないわよ」長瀬は笑った。「でも、理事国がこのまま手をこまねいて見てるとも思えないわね。注意はしとかないと。それとネルフ関係者の移動は?」
「ネルフ関係者およびその家族の移動は殆ど済んでます。マギの稼働率も67%まで行ってますし、エヴァンゲリオン初号機の回復作業も順調です」
長瀬はあくまでそれを事務的な態度で聞いていた。
「そう、もうすぐなのね」
***
からからと銀色のホイールを転がして遊ぶ子供たち。どこかで見た懐かしい風景。気がつくとアスカは公園で一人たたずんでいた。
世界を照らす夕暮れ。永遠に続く倦怠。子供たちは一人、また一人と家に帰っていった。最後まで残ったのは、アスカと砂場で遊ぶもう一人の子供。
その男の子はアスカの方を見るとにこっと笑って近付いてきた。アスカもなんとなく微笑み返す。
「ボクは帰らないの?」
アスカが口を開く。
「帰るよ。お姉さんは?」
もちろん、と言いかけて口をつぐむ。私の帰る所はどこだっただろう?何か帰ってはいけない、帰れないところに家はあるような気がする。
「帰らないの?」
その子は不思議そうにアスカの顔を覗き込む。
「帰るわ、もちろん」
アスカは口だけで、そう答える。ここが私の帰る場所だというのに。でもここは本当に私の家?奇妙な違和感と郷愁とがないまぜになっていた。
「ワタクシトイフ現象ハ…」子供がいきなり声をあげて朗読しだした。「ワタクシトイフ現象ハ、有機交流電燈ノ…」
「それ、何?」
アスカが子供に尋ねた。
「わからない」子供は答える。「でもこれが僕の家なんだ、きっと…」
この子は何を言っているのだろう?さっきの朗読とこの子の家と、何か関係があるのだろうか?
「お姉さんは幸せ?」また急に尋ねてくる。
「え?」
思わずアスカは聞き返した。
「お姉さんは幸せなの?」
アスカは少し考える。
「多分」
「本当に?」その子はアスカの顔を覗き込むように言う。
「ええ」
「どうして?」
「だって不幸ではないもの」
「不幸でないと、幸せなの?」
その問いかけに一瞬どきっとした。彼女も確信していない部分を、ずばり突かれている。しかし子供はあくまで無邪気に聞いてきていた。
「そう。不幸でなければ幸せなのよ、きっと…」そう、深く考えてはいけない。子供の罪のない質問だ。「ボクは幸せ?」
アスカはささやかな復讐のつもりで聞き返した。
「わかんない」その子は首を振った。「嫌なことはみんなどこかに行ってしまうし、痛くもない。きっと幸せなんだろうね、お姉さんの言うとおり…」
どこかで、タカシ、と子供を呼ぶ声がした。
「お姉さん、もう行かなきゃ」
「そう?気をつけてね」
そう言ってアスカは立ち去る子供に手を振る。子供は手を振りながら駆け去ろうとしたが、途中でアスカの方に戻ってきた。
「お姉さん、これあげる」
子供が何かをアスカに手渡した。アスカはそれを受け取るが、それがなんだかわからない。見て、触って確認しようとするが、感覚は解けるようにしてどこかへ消えてしまう。
これは見てはいけないものなんだろうか?
「僕の大事なもの。お姉さんにあげるね」
そう言うとその子はアスカが止める間もなくどこかへ駆け去ってしまった。
アスカは一人、公園に残された。
***
「やあ、あんたかね」
ネルフ本部の一室で帰り支度を始めた大滝を尋ねてきたのは他ならぬ冬月コウゾウだった。
「今日で事情聴取が終って帰るというので来てみたのだが…やはり君だったのか」
冬月は実際に生身で会うのは初めての男にそう言う。
「実際に会ってみるまで、本当にいる人物と言う気がしなかったが…夢の中より大分肉付きがいいようだな、アンタは」
大滝がそう言って笑う。
「君も私が夢で見たのよりはまだ太ってる」
冬月もそう答えた。
「夢の中で会ったのが一昔前に生物学の進化論の分野で一世を風靡した異端の天才、冬月先生だったとはね…アンタと会ったら一緒に飲みたいと思ってたんだが」そう言ってちらと時計を見る。「そう言うわけにもいかんらしい。時間があまりないしな」
「正直なところ、私は人と飲むのはあまり好きではないのだよ」
冬月が肩をすくめて言った。
「そりゃぁいかん」大袈裟に大滝が言う。「一緒に飲むからこそ酒も楽しい。これ人生の楽しみというやつだよ」
「まあ、いずれ機会があったらね」そう冬月は受け流した。
「ところで今日来たのはそんな用ではあるまい?」
大滝がいきなり真面目な顔になる。
「うむ、実は君と一緒にいたあの人物について…」
皆まで言い終る前に、大滝はやっぱりという顔をした。
「まあわたしの所に用なんて、他にないだろうからな」
「妙に気にかかるのだ。何でもいい、君の知っていることを…」
「わたしの知ってることなどたかが知れてる」大滝は首を振る。「むしろ君らの方がよく調べ上げてるくらいだろう」
冬月はあの”シンハ”と名乗る人物の事について思い出していた。厳格なカトリックの神父の家で育つ。父親は教区の信者から尊敬される神父だったが、反面息子には相当厳しい育て方をしていた。折檻を受けていたという噂もあったらしい。成長して神学校を卒業。その後研究と信仰に熱心に勤め、バチカンに勤めるまでに至った。しかし彼の人生の華やかな部分はそこまでだった。
いつ頃かははっきりしない。おそらく2、3年前に”アダム”と接触する。数少ないアダムと接触をしつつも生還を果たした人間の一人となるが、変わり果てたその容貌、また言動に教会から破門を言い渡され今日に至る。
バチカンからは完全に記録そのものが抹消され、そこまで調べるのはかなり時間を要した。
「しかしそれだけならただの変わり者と言えなくもない」冬月は大滝に言う。「しかし妙に不安なのだ。アダムの記憶を持つと言い、アダムとの接触を試みようとしている。彼とアダムが接触した時、何かが起こるのではないのかね?」
大滝はため息をついた。
「わたしはアダムとやらについては君ら以上の門外漢だ。そんな事を言われても判るわけがない」冬月がやはり、と肩を落とした。「だが…」
「だが?」
「これはわたしの勘に過ぎないのだが」前置きする。「わたしにも嫌な予感がするのだ。彼の望みをかなえさせてはいけない、そんな気がね」
「何故?」
「わからん」怪訝そうな冬月に無責任に答える。「ただの勘だと言っただろう?だが敢えて言うなら彼が熱心なクリスチャンということが理由かな?」
冬月は一層怪訝そうな顔をする。「言ってる意味がまるでわからんが…」
「わたしも突っ込まれても困るんだよ」大滝は本当に困ったように頭を掻いた。「もっとそれらしくこの予感の解析をすると、あの男は自分の父親に対しかなり強いコンプレックスを持っている。しかし同時に敬謙な神父としての父親を尊敬もしなくてはならないという観念から抜けきれていない。神学者としての道をひたすら精進することは彼にとっての逃げ道だったのだろうよ」
「……」
「加えて民俗学者からの視点を言わせて貰うなら、現在のキリスト教というのは土着信仰の女性神を殺して来た、父神の宗教なのだよ。彼が敬謙なキリスト教徒たろうとし、神に身をささげていたのは神、すなわち父との絶対的合一を望んでいた、そういうことではないかと思うのだ」
「それとアダムの事が何か?」冬月はいらついて聞きかえす。
「わたしは無神論者だ。民俗学などという分野で自分の視点を中立に保つにはそうでもなくては駄目だろう。私自身は神秘だの奇跡だのということは信じていない。科学とは神秘や奇跡のタネ明かしをすることだからね。しかしそれを否定しているわけでもない。神秘や奇跡は、要はそれらの別の方面から見たものだから。だから彼がアダムを神と言うなら彼にとってはそうなのだろう。しかし私は私の視点で彼とアダムの関係を見る」
「彼が何故アダムに吸収されずにすんだのか、何故アダムから奪ってしまったか、ということか?」
大滝はうなずく。
「彼は神=父との合一を望んでいた。しかしその奥底には父親への強い拒絶があった。そしてアダムは記憶を捨てたがってた。わたしには理屈は判らんがそういうことではないのかな?」
「あるいはな」冬月はそう言う。「だが違うかもしれん」
「そうだな。まるっきり違うことを言ってるのかもしれん。しかしわたしには納得行かないのだあの男の全てを諦めたような心境、そのくせ敬謙な態度、父親というキーワードにのみ正常に反応する…それに君も見たはずだ。本来のアダムを」
「ああ」冬月にはうなずくしかない。「最初のアダムはまるで月と自分を作った何者かに対する憎悪の塊の様だった…異常な執着を示してる。しかし今の彼にはそれがない。まるで目的というものがないような行動だ」
「あるいは何者かに動かされてるような、だな」
大滝が付け加える。冬月は口をつぐんだ。
何者か?そんなのは一人しかいない。あの男しか!大滝はそんな冬月の態度に気付いたか気付かぬか、ちらと一瞥しただけだった。
「しかも生物なら本来持っている生存欲求、生殖欲求ですら希薄のような気がする。あるいはそれすらも捨て去ったのか?唯一、碇シンジという少年にのみ何故か執着を示してるが…それも何故かわからない」そう言って大滝は冬月をもう一度ちらと見た。一見何も反応を示してるようには見えない。しかし彼は確信した。冬月コウゾウは全てを知っている!「まああんたたちが三年前に何をやったかなんてわたしには関係ないがね」
「で、どうするつもりかね?これから」
冬月は声色を殆ど変えずに言った。
「別に。いつもどおりさね」大滝は何でもないというふうに答える。「全てを忘れて生活する…という訳にはいかんが、喋っていい時が来るまで黙ってるくらいの頭はあるさ」
そこで言葉を切りため息をつく。
「どうしたのかね?」冬月が聞いた。
「いや、シンハと会う前に会った友人の言葉を思い出したんだよ。世の中、知らなくて良い事がある、とね。わたしなどは無神論者だからまだいいものの、人間が神にとって必要な存在ではないと知ったら、世界中とんでもないことになるからな。案外バチカンもそのために彼を破門したのかもな」
「私も科学者だが、科学が人間にとって唯一絶対の神、とそこまで傲慢になるつもりもない」冬月は言った。「しかし、人間にとって神とはそんなに必要なものかね?」
「神でなくともよいのさ」大滝は苦笑した。「精霊でも、先祖でも、それこそ父親でも。いきなりこの世に襁褓一つでこの世界に投げ出され、目的も、存在意義も、自分の地位も何も与えられてない子供たちには、いや人間には何かすがる存在が必要なのさ。たとえ虚像、偶像でもね」
***
どうしてだろう、と彼は思った。どうしてあの少年のことがそんなに気にかかるのだろう?
自分の存在意義?
全ての人間を
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め取り込め
ひたすらに繰り返す頭の中の言葉。一体なんなんだ?何時からなんだ。その声に重ねて現れるあの少年の姿。碇シンジ。
この頭の中の命令と、あの少年に何の関係があるんだ?あの大きなのが眼前に迫った時もそうだ。誰かがあれを拒絶しろと言った。僕自信じゃない。
僕の中の誰か?
僕は誰かにいいように動かされてるのに、僕自身は自分が何の為に生まれたか、どうしてここにいるのかも知らない。
きっとたくさんの人が僕の中に入れば孤独も消えると思ってた。でも消えない。皆貪欲に自分を求めてはくるが、誰も僕のことを知らない。教えてくれない。
孤独は影を増しただけだった。
僕は何者なんだ?
それを知るために会いに行くのだ…碇シンジのもとへ。
***
「あら、冬月先生」ネルフ本部の廊下を歩く長瀬が向うから歩いてきた冬月に声をかける。「どちらにいらしたんですか?」
「うむ、友人のところにな…」
冬月は言葉を濁す。
長瀬は側にいたエージェントに席を外すように言い、冬月と二人きりになった。
「冬月先生」最初に声をかけたのは長瀬だった。「ここには残ってくださらないんですってね」
「ああ」冬月はややばつが悪そうに答える。「もはやこんな老いぼれの出る幕はないよ。学校を放り出してもう大分たつしな」
「残念ですわ」意外にも長瀬は本当にそう思っていた。「冬月先生にはまだまだ教えていただかなくてはいけないことがたくさんあるのに…」
「私がいたネルフはすでに存在してないのだよ」そう言って冬月は背を向ける。「これから作るのは、君の作った、別の組織だ。私の居場所ではない」
「先生のポストの話でしたら、もちろんそれなりに…」
「地位や名誉の話ではないのだよ」冬月は笑って答える。「私の生きる術も、目標もそこにはないのだよ」
「あの小さな島の学校にあるとおっしゃるのですか?」
長瀬が理解できない、というふうに言う。
「それはわからんよ」また長瀬の方を向く。「定年も近いしな。ただ、今の私にはそれで十分なのだよ」
長瀬は少し寂しげにため息をついた。「先生は、自分の月を見つけられたのですね」
「月?」
冬月が怪訝な顔で聞き返す。
「ええ、人生という闇を照らす月。自らのゆくべき道を照らす明りですわ」
「月、か…」冬月はその言葉を反芻する。「かもしれんな。だが君とて見つけているのだろう?」
「と、思ってたんですけどね」長瀬は寂しげな微笑みのまま答える。
「思ってた?」
「ええ。この世の中で、権力と牽制を掴む。それこそが私の欲しい全てと思ってきたけど、いざそれが目前に迫って一息ついてみると…」
「怖じ気づいたのかね?」
「いいえ」長瀬は首を振る。「でもね、なんだかブリキの玩具のようにたいしたことのないものの様に思えるんですの。どうしてあんなに欲しがってたのかってね」
「泣き言を言うとは君らしいとも思えんが…」その言葉には皮肉は含まれてなかった。
「別に泣き言を言うつもりはありませんわ。でもね、自分が月だと思ってたものは実はただ水面に落ちた月の影を見ていたんじゃないかって思う時があるんです。本当の月は別のところにあったんじゃないかって」
「で、だったらこれからどうするのかね?」
「どうもしませんわ」長瀬は顔を上げて微笑んで言う。「私は今まで通り突き進むだけ。他に生き方なんて知りませんもの」
「強いな」
「強いって?」長瀬が聞き返す。
「君は強いと言ったのだよ」冬月は少しうらやましそうに言った。
長瀬は首を振って否定する。
「いいえ。強くなんかありませんわ。自分の欲求のために、他人を踏みつけ、踏み潰して生きてく。そんなことしか出来ない人間なだけです」
その弱い自分と向き合うことができることが強いということなのだよ、冬月はそう思ったが口には出さなかった。
「そう言えば、残念だったね。お父上のことは」
唐突に冬月が言う。
「え?」長瀬が戸惑って聞き返した。
「君の父上のことだよ。あの8号機の…」
長瀬はようやく冬月の言ってる意味を悟った。
「知ってらした…のですか?」
長瀬がショックを受けて言った。あまりに意外で出し抜けだった。
「思い出したのはつい最近のことだよ。昔ゼーレの事を調べてる時にたまたま君たち母子の写真を手に入れた」冬月は昔手に入れた一枚の写真を思い出していた。赤子を抱いた日本人の母親と、彼女の座る椅子の後ろに立つ男の写真。記録にも残ってない彼ら親子の、唯一の絆を示す写真だったろう。もはや今は失われてどこにもない。「それっきり忘れてしまっていたのだが」
「そう、ですか」長瀬はそうとだけ答える。
「君に見覚えがあったわけだ。君は君のお母上の若い頃によく似てる」
「そう」長瀬は他に答える言葉を思いつかなかった。ただ小さな声で、静かに呟くのみだった。
***
「碇君?」
シンジを呼び止めたのは聞き覚えのある声だった。
シンジは反射的に振り向く。
「やっぱりそうだ。碇君ね?」
そこに立っていたのは洞木ヒカリだった。
「洞木、さん?」髪型が変わり、体つきがいくぶん大人びたかつての同級生をまざまざと見る。どうして彼女がこのネルフ本部内にいるのだろう。「どうしてここに?」
「どうしてってよく分からないけど、昔のネルフ関係のことじゃないかしら?呼び出されただけなの」ヒカリは少しだけ考えるポーズを取る。「それに来てるのは私だけじゃないのよ。二年A組のほとんどみんな。碇君が見当たらないからみんな心配してたけど、やっぱり来てたんだ」
「来てるって…みんな?」
「うん。綾波さんと、碇君とアスカ以外は殆ど全員。そう言えば碇君はあの二人見なかった?」
アスカは…言おうとして言葉を詰まらせる。もうこの世にいないなんて、どうやって言える?レイにしてもそうだ。何も説明できるわけがない。
「ごめん、知らないんだ…」
シンジは視線を地面に向けて言う。
「そっか。碇君なら知ってると思ったのに」
シンジの言葉をそのまま信じるヒカリの言葉が痛い。どうしてこんなに恐いんだ?どうしてこんなにつらいんだ?傷ついたわけでも、痛むわけでもないのに。
自分はどんなに弱い人間か思い知らされた気分だった。
しかしシンジはそんな自分を否定するように口を開いた。
「みんな来てるって、ケンスケや、その…トウジも?」
元気よくヒカリは答える。
「うん、相田も鈴原も…」言いかけてヒカリははっとしてシンジを見る。「その、鈴原君も来てる」
言葉の最後は声のトーンがかなり落ちていた。
「そうか、来てるんだ」シンジは心ここにあらずといったふうに繰り返す。
ヒカリは努めて明るく振る舞った。
「みんな元気そうだよ。相田も、鈴原も」
「そっか、よかった」
シンジは少しだけ、笑みを浮かべて言う。
「ね、みんなに会いに行かない?」
ヒカリが言った。
「え!?」シンジはびくっと身体を揺らす。会いに行く?トウジ達に?いったいどの面下げて会いに行けというのだろう。僕は、僕は…「ごめん。僕は…」
そう言いかけた時、小動物の足音がした。大きさは犬くらい?でも足音が全然違う。何か湿ったもので地面を叩いてるような音。
「クェ?」
聞き覚えのある声の主をシンジの視線が追った。
「駄目じゃない、ペンペン!」
同時にシンジの視線の先を追ったヒカリが叱り付ける。声の主のペンギンは、不思議そうにシンジとヒカリを見た。
ヒカリはペンペンの元へ走っていき、少し重そうに抱きかかえるとシンジの方へ歩いて戻ってきた。
「ペンペン、洞木さんの所にいたんだ」
シンジが戻ってきたヒカリに言う。
「うん。最後に葛城さんから預かってから、そのままだったから…」抱きかかえられたままのペンペンが羽をばたつかせ暴れる。「まったくもう!鈴原の奴、ちゃんと見ておいてって言っておいたのに!」
「おーい、こっちみたいだぞ」
廊下の向うから声がした。聞き覚えのある声。相田ケンスケのものだ。誰かに呼びかけているみたいだ。二人の足音と、それに併せたような杖のかつん、かつんという硬質の音が近付いてきた。
見覚えのあるケンスケとトウジの顔が近付いてくる。
途中でケンスケがヒカリの側にいる人物に気がついて立ち止まった。
「なんやヒトがちぃっと便所にいっとる隙に…っておいなんやケンスケ!急に止まるな…」
そう言いかけてトウジの視線がシンジに向いた。思わず視線が合う。シンジには視線を外すことが出来なかった。それは恐いことだからだ。
暫く金縛りに遭ったように二人とも動かなかったが、やがてトウジが松葉杖を突きながらシンジに近寄って来る。
「鈴原、あのね…」ヒカリがトウジに話しかけるがトウジは無視してシンジにぴたっと寄ると立ち止まった。シンジも息苦しさを表情に出したまま、トウジを見つめていた。
「あの…」シンジがたまらなく声を出そうとする。何か言わなければ押しつぶされて泣き出してしまいそうだった。
そんなシンジの肩を、ぴたーん、とトウジの手が叩く。「なんや、シンジ!久しぶりやないか!」笑顔で言うトウジに、シンジは戸惑ってきょとんとする。「三年間なんも音沙汰なしやったから心配しとったで!」
「いや、その…」シンジは先ほどまで言おうとしてた言葉を飲み込み、しどろもどろになる。
「なんだ、碇も来てたんだ」ケンスケもトウジに続いて言う。「これで殆ど全員揃ってるわけだ、我らが二年A組のクラスメートは」
「水臭いやないか、手紙も電話もよこさんと何しとったんや!」
「あ、そうだ、鈴原!この子の様子ちゃんと見といてって言ったでしょ!」
憑き物が落ちたようにヒカリも喋り出す。
「なんや、いいんちょ。ちょっと目ぇ離しただけやないか」トウジが眉をしかめる。「そないにすごい顔せんかて…」
「鈴原!」
一瞬シンジは自分が三年前の日常に舞い戻ったような錯覚を覚えた。しかしすごんだヒカリに気おされてよろけたトウジの足元に目が行き、はっとする。左足の動きが普通の動きではない。足音も変だ。
トウジはシンジのそんな視線に気付いた。「ああ、これか。これはあの時、な…」
トウジは言葉を選び、言葉少なに語ったつもりだった。しかしそれだけでシンジには十分だった。
シンジはぎゅっと目をつむり、泣きそうな顔になる。慌てたのはトウジの方だ。
「な、なんやシンジ、そんな顔せんでもええって!そんな顔されたら、まるでワシが惨めな目におうたみたいやないか」
笑顔で言ったその言葉にシンジは呪縛される。そうだ。シンジよりも傷ついたはずなのは、トウジの方なのだ。ここで泣いたら泣くことで自分を正当化しようとしてる、そんな思いでぐっとこらえた。
「第一お前が思ってるほど難儀しとらんで。ほら、なんなら触ってみ」
「え!?」
シンジが拒絶する間もなく、トウジはシンジの手を取り、左足をよいしょと上げてそれに手を当てさせる。固い義足の感覚を予想したシンジの手に、幾分弾力のある感触が伝わってきた。肉の感触ではない。何かプラスチックの感触の様だ。
「最新の技術で、ホンマもんの足みたいに動くんやで」そう言ってトウジは足首を伸ばしたり曲げたりして見せる。その動きは幾分ぎこちない、少し機械的な動きだった。「すごいやろ?ま、飛んだり跳ねたりいうわけにはいかんけんど、リハビリが終れば杖もいらんようになるって、医者も言うとったで」
トウジの意志を汲みとって、ヒカリも口を挟む。「最近鈴原にしては真面目にリハビリ通ってるのよ。医者の先生も、最近は熱心だって感心してるの」
「委員長、鈴原のリハビリについていってるんだってさ」ケンスケがからかうように言う。
「ちょ、ちょっと!相田君、何言うのよ!ち、違うのよ、碇君!私はたまたま今も鈴原の家の近くに住んでるから昔のよしみで仕方なく…」
トウジが苦笑した。
「なあ、シンジ、解るやろ?こないなうるさいのがついてきよるんで、ようさぼられへんのんや」
「ちょっと、鈴原!」ヒカリが顔を真っ赤にして眉をつり上げる。「誰がうるさいのなのよ!」
トウジはわざとおどけて脅えてみせた。
「おおこわ。だからな、シンジ」シンジに向き直って優しげな笑顔になる。「お前が気にすることは何もあらへんのや」
シンジは友の思いやりに言葉をつまらせた。駄目だ、ここで黙ってしまったら卑怯者になる。
「でも、僕は…」
「そらな、ワシかて何も感じへんのんと違う。けどな、考えてみい。考え様によってはワシの命も、シンジ、お前の命もなくなるところがこの足一本で済んだんや。おまけにワシの妹もきちっとした病院に入って、今は元気に普通に生活しとる。ワシは死んでへんのんや。ワシとお前と、妹の命の代償が、足一本なんやったら安いものやないか。な?」
そう言ってシンジの肩に手を置く。シンジは泣き出しそうになる。が、必死でそれを押さえた。しかし体が支えきれないというふうにトウジの胸にかじりついた。
「僕は…」
どんな傷も、時がきっと癒してくれる。
「トウジ、僕は…」
必要なのは、あとほんの少しの勇気だけ。
「ごめん」その瞬間、シンジの目から涙がこぼれだした。泣いたら卑怯だ。トウジにすまない。そう言い聞かせながらももう止めることができなかった。もう後は崩れるように全てを吐き出すしかなかった。「トウジ、ごめん…ずっとずっと言わなきゃって思ってた…!」
「謝らんでええ」
トウジはシンジの肩に手を置いたまま言った。
「トウジを傷つけて…でも会う勇気がなくて…ずっと謝らなきゃいけないって思ってた…思ってたのに…僕は、僕は…」
「解ってる。お前が悪いんやない」
「ごめん!トウジ、ごめん!」
その後、シンジの言葉は鳴咽で聞き取ることが出来なかった。ヒカリの胸に抱かれたペンペンが、目の前の人物を思いだそうとするように覗き込み、触ろうと羽を伸ばした。
シンジにはそれがシンジを迎え入れようとする手のように思えた。
シンジは手を伸ばし、ペンペンの羽にそっと触れた。
「…ただいま…!」
***
novel page|prev|next