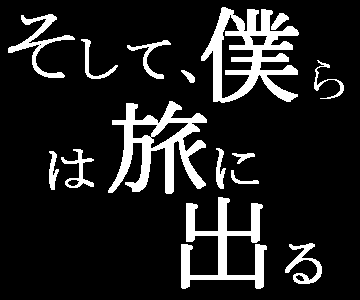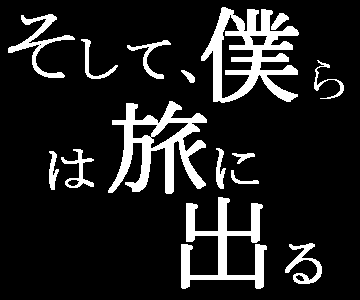
第十三章:そして、僕らは旅に出る
***
18日午前8時03分
「正直、あなたには失望したわ」トードがオフィスに入ってくるなり長瀬は言った。「もう少し常識ってものをわきまえてると思ったけど」
トードは何も答えなかった。
「幸いあなたが両耳ふきとばした相手とは司法取引が成立して、起訴はされないけど、私たちを快く思ってない連中がここぞとばかり苦情を言いたててきてるわ。私に無駄な仕事をさせないで頂戴」
「奴を釈放させるのか?」トードがやっと重い口を開いた。
「釈放?逆よ」長瀬が答える。「拘留期間の延長があちらの提示した条件よ。理由はどうあれ、口を割ったんだから報復を恐れて当然ね」
「他に俺に言いたいことは?」トードは後ろに手を組んで直立したまま尋ねた。
「狙撃手を逃走中に射殺したそうね?」
「ああ。抵抗したので仕方なかった」
トードは表情を変えずに答える。
「本当に?」長瀬がトードの目をじっと見つめる。トードは何も答えなかった。「そのことはまあいいわ。サードチルドレンも無事だったし。でも先のあなたの行動に対し、私の越権行為を申し立てる者が多いの。今はつまらないことで事を荒立てたくないわ」
「どうしろと?」
「しばらく休みなさい。あなたも疲れてるのよ」
「謹慎か?」トードがずばりと言う。
「形式上はね」長瀬はため息をついた。「丁度あなたもサードチルドレンの護衛の任から暫く外して欲しいと言ってたでしょ?少しは羽を休めなさい」
トードは無言でそれを聞いていたが、また何も言わずに部屋を出て行こうとした。しかし扉の前で足を止め、背を向けたまま長瀬に問い掛けた。
「そう言えば、テロリストどもはやけにあっさり碇シンジの居所を突き止めたな?」
「そう?」長瀬は知らぬ顔で答える。
「それに比べて榊ユリの方は、現在目立つテロに狙われてない」
「偶然でしょ」長瀬は椅子を回転させ、窓の方を見た。「あるいはテロリストに情報をリークした機関が榊ユリの事までは掴んでなかったか…」
「あるいは」トードが話の腰を折る。「テロの目を碇シンジの方に集中させるためにわざと碇シンジ側の情報のみをリークし、狙いやすくしたか…」
「何が言いたいの?」長瀬はにらめつけるような視線を窓に映るトードの影に向けた。
「別に。アンタたちも敵の標的が絞られてる方が守りやすい、そんなことを考えたんじゃないかと…」
「ミスター」長瀬はトードの言葉を最後まで待たなかった。声には険が含まれていた。「口を開く場所に気を付けることね」
「そうかい」トードはドアノブに手をかけ、扉を開いた。「悪いね。疲れてるんだ」そしてそのまま出ていった。
ドアが閉まった後、長瀬は苛立ちをぶつけるように窓ガラスを思い切り拳で叩いた。
***
18日午後9時34分
シンジは目を開けると、自分が拘束されて床に転がっているのに気がついた。息を吸い込むと当て身をくらった首筋の部分が少し痛んだ。
ここは何処だろう?部屋の中、灯りが煌煌と点ってるが、外は既に日が落ちて久しいらしい。虫の音が周り一帯で鳴り響いていた。山中の、廃棄されたかで無人のロッジか別荘だろう。
碇シンジは後ろ手に縛られたまま、その廃棄されたロッジの部屋の片隅からじっとトードを見つめる。トードは肩にライフルをもたれかからせ、寝ているように俯いていた。
シンジは隣に、同じようにされたまま床に転がっているユリを見る。一瞬息がないかのような錯覚を覚えるが、胸元は静かに上下している。シンジはそれを確認してほっとした。
一体何が起こったのかまだはっきりとは掴めていない。しかしトードが彼らをこんな目に合わせたのは間違いなかった。意識が途切れる直前のことまでは覚えてる。
何故かは判らなかった。しかしこの場をどうにかするのが先決だった。
シンジは物音を立てないように、静かに立ち上がろうとした、と、寝てるとばかり思っていたトードの身体が動く。
「…起きたか、小僧」顔を起こしてトードは呟いた。
シンジは何も言わずにトードを睨み続けた。
***
18日午前8時17分
「長瀬部長、碇シンジ及び榊ユリを連れてまいりました」トードとほぼ入れ違いに情報部のエージェントが入ってきた。しかし長瀬の穏やかならざる雰囲気に圧倒される。「部長?」
「何でもないわ」長瀬は平静を装った。「それより車の方の準備は出来てる?」
エージェントはすぐに気を取り直し、口を開いた。
「はい、すぐにでも例の名所に出発できます」
長瀬はそれを聞いて上着を取り、すぐさま部屋を出た。
そして応接室でソファに座って長瀬を待っていた二人を見た。榊ユリは長瀬が入ってくるのを見て、すぐに応接テーブルに目を戻したが。碇シンジはぐっと長瀬を見上げる。
「よく来てくれたわね」自分で呼んだにも関わらず、長瀬はそう言った。
「今日は何なんですか?」
シンジはややとげとげしさを感じる口調でそう聞いた。先日ここに来るように言われていたがその内容は一切知らされてない。その苛立ちと、あの先日のトードの行動のショックがまだぬけきらず、押さえようとしても感情を押さえ切れずにどこかに表してしまう。
「あなたたちに見て欲しいものがあるのよ」
長瀬はシンジの口調の棘に気付かないような振りをしてそう答えた。
***
18日午後9時42分
碇シンジと榊ユリが拉致されたという情報が入ってきたのは、実際に拉致されてから一時間程経ってからだった。
「護衛は何やってたの!」
長瀬は感情を顕わにして怒鳴った。
「申し訳ありません、要人警護用の特別車だったのですが、タイヤを打ち抜かれガードレールに激突した跡があり、半壊した状態で谷底に捨てられてるのが発見されました。発信機も壊されてましたので、工事ということで閉鎖された山道を通ったのが裏目に出たようです。防弾製の特別のドアも、強烈なバーナーで溶接されてこじあけられた跡がありまた」
「ダミーの警護車は?」
「そちらはまるで無傷です。所定のルートを通り、帰還が確認されてます」
「で、載っていた碇、榊両名と護衛、運転手らは?」
「車中にはそれらしき人物の遺体等は見つかってません。現在山中を捜索してますが、まだそれらしき遺体も人物も…」
「そう…」長瀬は俯くようにして考え込んだ。何処かの組織か?CIA?KGB?MI6?それにしても向うがかなり正確に情報を掴んでいるらしいのが気になる。「ともかくすぐさま非常線を張りなさい。同時に捜索地域の拡大を。地元警察にも出動を要請、マスコミ報道は全てシャットアウトなさい!」
***
18日午前10時07分
トードは自分の宿舎に帰る前に、先日エヴァンゲリオンの槍投下地点にいて連行された二人の男が拘束されているホテルに寄った。警備をしているエージェントは少しトードを胡散臭そうに見たが、何も言わずに通した。
トードが彼らとの面会を求めると、間もなく彼らの部屋へと案内される。トードが部屋に入った時、大滝は大欠伸をした瞬間で、シンハは瞑想してるように目を閉じていた。
「悪いね」トードは開口一番、そう言った。
「なぁに」大滝が口を開く。「こんなところに十日以上缶詰状態じゃ刺激が足りんくてな、訪問者は歓迎だよ」
トードは部屋に入ると断りも無しに椅子にどかっと座り込んだ。扉の側にはエージェントが見張るように張り付いていた。
「よう」トードはシンハに向かってそう言って手を挙げた。日本語でではない。シンハが喋ってたのと同じ言語だ。シンハの眉が微かに動く。「アンタ、調子はどうだい?」
「アンタ!」驚いたような声を上げた。「その言葉、喋れたのか!?」
「ああ」トードは何気なく答える。「昔アフリカのあの辺には仕事でいた事があるんだ。俺の唯一の才能でね」トードは自分の耳を指差した。「一週間もいれば大体その国の言葉は話せるようになるんだ」
そう喋る間もトードは日本語ではない。
「驚いたね」大滝が両手を挙げる。
「驚いたろう」トードがおどけて答える。「で…俺の用なんだが…」
「私だろう」シンハが突然口を開いた。
「まあね」
「そりゃそうだろう」大滝が言う。「私のここ数日の仕事はシンハの通訳だよ」
「俺が聞きたいのは一つだ」トードは真面目な顔で迫った。「アンタとアダムの関係だ」
「それならこれまでにも何度も聞かれ何度も答えた」大滝が代わりに口を開く。「彼はアダムとの融合過程で何らかの理由により融合を妨げられ、その時のショックでアダムの記憶を奪ったらしい。これ内務省の連中に何度も説明したよ」
「俺が聞きたいのはそういう事じゃない」トードは首を振った。「どうしてアダムが記憶をアンタに押し付けたのか、それがアンタでなきゃいけなかったかということさ」
「それは」シンハが口を開いた。「人は誰でも忘れたい過去がある、そういうことだ」
「あのバケモノにも忘れたい過去があるってことか?」
トードは皮肉を込めて答える。
「あれの精神構造は人間より遥かに深遠だ。しかし衝動は人間のそれに極めて近い…」
そう答えたきり、後は口を閉ざした。トードはこれ以上の質問は無理と見て、話題を切り替えた。
「じゃ、それはいいとしてもう一つの質問は?どうしてそれを押し付けるのがアンタだったんだ?他の誰かじゃなく?」
「それは」シンハがたちまち口篭もる。大滝は驚いたような顔をした。シンハのこの様な表情を見るのは初めてだ。「恐らく私側の問題だと思う。私は若かったのだ。私は自らが神に近くあることを望んだ。その報いがこの髪と目だ」そう言って自分の髪を指差す。
「それだけで?」トードは意外そうな顔をする。
「あちらの要求とこちらの要求が一致したのだろう」
そう言って再び口を閉ざした。トードは最初おかしな話だと思ったが、考えて見れば奴と会った状態では、自分はそんな事を考える余裕はなかった。たまたま神との合一の欲求の強い人間と会った、だからそうなった、というのはまるっきり否定できる事でもない気がした。しかしトードの心の中に妙なシコリが残った。本当にたまたま?
しかしもはやシンハはそれ以上質問に答えようとしない。トードは諦めて席を立って出口に向かった。
「あ、そうだ」トードは立ち止まり、シンハに振り返る。「アンタの父親ってどんなだった?」唐突で、思い付きにすぎない質問だった。長瀬、碇シンジ、彼らはどちらも父親に対する拘りがある。そんな所から思い付いた、関連性の薄い連想に過ぎない。
「父は」シンハが答える。「皆から尊敬される神父だった」
シンハはトードの方を向かずに言った。
「そうかい」トードはシンハが父親の人となりを言わず、職業を答えたのに引っかかりながらもそこを離れた。
***
18日午前11時01分
「ATフィールドとは」
長瀬は碇シンジらとは別に、空路で目的地に向かいながら技術班の報告書をめくる。
「ATフィールドとは通常物理で言われる『場』の概念ではない。わずか数フェムトメートルから数ミリメートルの空間で、あらゆる量子波束を急速に減衰させる。すなわち量子力学的にはその勾配をエネルギーに置き換えることで計算できるが、その実体は謎である。
概念的にはエネルギーより更にランクが上の概念ということになるだろうが、このような示量性の概念は他には存在し得ない。現在の物理概念では解明は不可能なものだろう」
つまり訳わからない、ってことね。長瀬は端的に頭の中で翻訳する。次のページをめくった。
「このような超エネルギー場(なんて安易なネーミングかしら!)の導入は現在の物理体系をも根底から破壊しうる。しかし現在この高次の概念の導入以外による解析のアプローチも幾つかあがっている。その中の代表的な物がハウエル,E.の提案した変動確率場の概念の導入によるアプローチである。(2016年)これはいわゆる「シュレディンガーの猫のパラドックス」をひっくり返すことにより、観察者が空間における量子的確率を決定しうる、という考え方であり、発表当初は否定的な見解が多かったが、近年この理論を元にした研究も幾つか発表されている」
長瀬は頭を押さえた。物理は苦手というほどではないが、さすがに以下に羅列された数十ページにも及ぶ確率場の計算式を理解する気にはならない。
「つまりこれはどういうことかしら?」長瀬は目の前に座った冬月コウゾウにその資料を手渡す。
「ああ、これかね?」冬月はその数式をざっと一瞥する。「これはすなわち「シュレディンガーの猫」のパラドックスで言われるような…」
「それは読みました」長瀬がうんざりした顔で言う。「門外漢にも解りやすい様に説明してくださいと言ってるんです」
「そうだな。つまり、君が観察者だとして、自分に向かってくるボールを見て、「ボールはこっちに来ない」と思うと本当にボールは向きを変えるということだ」
「そんな…むちゃくちゃだわ」長瀬は頭を抱える。「まるでATフィールドじゃない」
「そりゃそうだ。ATフィールドを説明するために考えられた理論だからな」
冬月は平然と答えた。
「心が物質を支配する、とでも?」
「あくまで可能性の一つの示唆に過ぎんよ」冬月は答える。「そもそもこの理論では条件の拘束が厳しい。完全には程遠いよ。まあ全ての粒子は微視的には確率波でしか表せんというの事実だがね」
「つまり私はここにいないという可能性もあると?」
「そもそも君と言う存在はここに君がいる確率に過ぎないという言い方も出来るのだよ」冬月は面白がって説明した。「君がいきなりこのVTOLの床をすり抜けて地面へと落下する確率も、君の身体を構成する物質の分子結合がいきなりほどけて君が霧散する可能性も零ではない」
「ゼロでないだけですけどね」長瀬はむっとしたように言った。「あいにくですが、私はそういう有り得そうにない話で机上の観念論を語るつもりはありませんわ」
「ほう、そりゃ残念」
冬月は面白そうに答えた。
(でもなぜ)
長瀬は思った。
(なぜ使徒だけがその様な力をふるえるの?彼らが本当に神に選ばれた種族とでも?)
その考えは長瀬を不快にしただけだった。
***
18日午後9時56分
「ん…」軽い声をあげてユリが覚醒する。
「榊さん…」シンジがユリを見つめてる。「よかった…」
「碇…君?」
にっこり微笑むシンジの顔を一瞬何処かで見たような気がした。しかしすぐにそんな思いなどふきとんでしまう。自分の両手が手錠か何かでつながれてるのに気付いたからだ。
「何!?これ!」
シンジは首を振ってトードの方を見る。トードはただじっと銃を持ったまま何ともいえない薄気味悪い目の色で二人を見ているだけだった。
「これは一体どういうことなんですか!?」ユリがトードに言う。
トードは何も答えないで、オートマティックのスライドを引く。がちゃん、というその音にユリはびくっとした。
トードはそんなユリを見ようとせず、器用に銃を分解して掃除し出す。よく見るとトードの回りにはハンドガン、ライフル併せてかなりの数の銃が同じように掃除されて、床に置かれていた。
「お前らには…悪いと思ってる」トードがいきなり口を開いた。「だが俺がこうするのはどうしようもないことなんだ」
「トードさん、一体何で…」
シンジが息を呑みながら口を開く。
「許して貰おうとも、理解してもらおうとも思ってない」トードは分解した銃を再び元どおりに組み立て直す。「これが奴と戦うラストチャンスなんだ」
***
9ヶ月前、トードを連行中のヘリの中で
「正気?」移動するヘリの中の嘲るような口調のその言葉が、長瀬の第一声だった。
「当たり前だ!」トードは怒鳴りかえす。
しかし長瀬の口から笑い声が途絶えることはなかった。「今までいろんな馬鹿に会ってきたけど、奴と戦わせてくれ、なんていう間抜けはあなたが初めてね」
「奴との戦いに参加できるんならなんだってする!」
「例えば私の靴の底を舐めろと言っても?」長瀬はからかい口調のままそう言った。
トードはじっと長瀬を睨んでいたが、やがて立ち上がり、つかつかと長瀬の方に歩み寄ってきた。トードは怒りに燃えたような目でじっと長瀬を見下ろした。「あら、怒った?悪かったわね」長瀬は明らかに侮蔑を込めてそう言った。
しかしトードはその言葉に反応しなかった。す、と身体を静かに静めて、足を組んだ泥だらけの長瀬の靴の裏へと顔を近づけ…
「止めなさい!」思わずぞっとした長瀬が叫んだ。トードの動きがぴたっと止まる。長瀬の足がそのままトードの横っ面を張り飛ばした。「そこまでして人におもねりたい!?自分の自殺に他人を利用したい!?」
長瀬は思わず顔を上気させながら、立ち上がって怒鳴った。
「俺は…」トードは赤く腫れてきた頬を押さえようともせず答える。「死にたいから奴と戦いたい訳じゃない」
「ほお!?じゃあ何のためよ!金?名声!?」
長瀬は感情に任せて口走りながらも、自分でも何故これほど動揺してるのか分からなかった。
「違う!」トードは怒鳴った。そして下から睨み付けるように長瀬を見上げた。「生きるためだ!」
その時見せたトードの目つきに、長瀬は思わずぞっとした。さっき靴を舐めようとした時と同じ目つきだ。長瀬をひるませたのはトードの行為ではない。他ならぬその目なのだ。
「いいわ」長瀬はややしてそう言った。「それほど奴と会いたいなら死ぬほどデートさせてあげる。あなたが嫌だって言ってもね」
「ちょっと!長瀬部長!」回りにいたエージェントが止めようとする。しかしそれを聞くような長瀬ではなかった。
「対チェシャキャットに関する全ては私に任されてます!余所に口は出させません!」
「…ありがとう」トードは呟いた。
「感謝することないのよ」長瀬は動揺したのを隠そうと不敵な笑みを浮かべた。「死ぬほど後悔することになるのだから」
***
18日午後10時21分
「奴って、あの子ですか?」
シンジがトードに聞く。トードは答えないがその沈黙が肯定を示していた。
「無茶です!」シンジは身を乗り出して叫ぶ。あれが使徒なら生身の人間にかなうわけがない。「それにどうして僕と榊さんが…!]
トードは無言でサバイバルナイフを研いでいた。ナイフに顔を映し、砥ぎあがりを確かめるように刃先を見つめる。
「奴と戦うには、戦って勝つにはどうしてもお前らの力が必要だった」
そういってナイフをタオルで拭うと皮製の鞘に収めた。
「どういうことなんですか!?」
「答える必要はない」
トードは取り合わない。
「自殺行為です!」シンジは叫んだ。そう、勝てるわけがないのだ。
「いいや、違うな」トードはすくっと立ち上がった。「生きるためさ」
***
18日午前10時44分
(使徒の目的はアダムとの接触、あのエヴァンゲリオンの目的も恐らくは同じ)
シンジは移動の車中で先日の第二東京市の戦闘を思い出していた。カヲルそっくりな子供の背後から現れた巨大な首。そして全ては槍投下の衝撃波に包まれた。
(あれが、あれが本当にアダムというのなら、一体何故他の使徒やエヴァンゲリオンと接触しようとしないんだろう。それが彼らの目的のはずなのに…)
『生き続けることが僕の宿命だからさ』カヲルはエヴァの…シンジの手の中でそう言った。『結果人が滅びるとしてもね』
全ての使徒は、エヴァはアダムへと向かう。ならばアダム自身は何処へ向かおうというのだ?
***
18日午後11時45分
「それでは二人を拉致したのはトードだと!?」
長瀬が報告に来たエージェントに怒鳴りつける。
「はい。こちらの通過経路を知り、なおかつ襲撃にこちらの支給した装備を使う」現場から集めた銃弾や化学検査の結果を示した。「トード氏に間違いないと思います」
「どうなってるの!?」長瀬はデスクを思いっきり叩いた。「まさか飼い犬に手を噛まれるなんて!」
「トード氏に連絡を入れようとしましたが、連絡がつきません。その目的も不明です」
「緊急に全国の空港を閉鎖、海外便は全て停止、長距離渡航のできる船舶の出港も同様に。いままで海外便で国外へ出た中からそれらしい人物がいないかチェックしなさい。それと捜索地域の拡大及び全国に非常線を」
「はい」エージェントは答えてからまた口を開いた。「それにしてもトード氏の目的は何なんでしょう?海外の諜報機関に彼らを売り飛ばすつもりでしょうか?」
「或いはね」長瀬は答える。「でも多分違うと思うわ。トードの宿舎の家捜しもするように」
***
19日午前00時13分
「わたくしという現象は…」トードが声を出して詩を朗読し出す。シンジはぎょっとしたようにトードを見た。手には宮沢賢二の詩集があった。「仮定された有機交流電燈のひとつの青い照明です」
わたくしといふ現象は
仮定された有機交流電燈の
ひとつの青い照明です
(あらゆる透明な幽霊の複合体)
風景やみんなといつしょに
せはしくせはしく明滅しながら
いかにもたしかにともりつづける
因果交流電燈の
ひとつの青い照明です
(ひかりはたもち その電燈は失はれ)
そこまで読んでトードは読むのを止める。もともとただこのロッジに置いてあった本を何気なく手に取っただけだった。トード自身は自分は詩心とは無縁だと思ってはいるが、この作者の言いたいことはなんとなくわかる。
自分という存在の不安定さに、皆悩まされているのだ。そしてトード自身も。
奴と会った時感じたのはどうしようもない不安、恐怖、そしてどこか懐かしい安らぎ。今になってみればそれは全てあれの精神攻撃の産物と解るが、トードはそんなものを感じ、逃げ出した自分に深く嫌悪していた。
しかし彼があれと戦おうというのはそれを雪ぐためではない。嫌悪以上にあれの存在はトードの世界を根底から覆していた。
死なない存在。
どうしてそんなものが存在しているのだろう?トードは今まで多くの人間の死を目の当たりにしてきたし、そのうちの何割かは自分で殺してきた。
生きるためにあがくには殺すしかなかった。それは彼の中で自然の摂理と同じに成立してたし、疑うことはなかった。目の前で戦友が地雷を踏んで、下半身が消え去った事もある。もし一歩トードの方が早ければトードがそうなってたはずだ。また銃を向けてきたゲリラの子供撃ち殺したこともある。もし躊躇してれば、死んだのは彼だ。
彼は殺すことを楽しんだことはなかったし、夜な夜な死者に夢の中で足を捕まれないことはなかった。しかし彼はそれを後悔しようとは思わなかった。
後悔したらどうだというのだろう?誰か生き返るのだろうか?それよりも、後悔するということはそれはすなわち自分の非を認めることになる。自分の行為が悪いとすると彼らが手にかけた人はどうなるのだ?無駄死にではないか。
だから自分は生き残らなければならない。死に対する恐怖と共に、今まで死んだ人間の死が無駄にならないように。
死の前においてのみ、全ての人間は平等なのだ。
しかし奴は違う。そんな人間の俗世のしがらみとは無縁な、まるで高みから人間を見下すような存在だ。
あるいは本当に神の使いかもしれない。しかしそうであっても、そうであればなおのことその存在を許すわけにはいかなかった。
人間は神様の玩具じゃねえんだ!
トードは憤らずにいられなかった。人間が欠陥品だろうと何だろうと、その生存を否定されるのは堪らない。だから殺すのだ。奴も、神も。
***
19日午前1時28分
「トード氏の目的が判りました!」
エージェントが長瀬の元へ駆け込む。
「彼の目的?」長瀬は聞き返す。「何なの、それは!?」
「これを見てください」
エージェントは長瀬の机の上で地図を広げる。第二東京市の地図だった。
「これが何?」
「これはトード氏の部屋にあったものと同じ物で、同じように印をつけてあります」エージェントが指す指先には、所々丸がペンで書かれ、日付と時間と思しき数字がその丸の右上に書かれてる。丸同士は線でつながれ、まるで何かの軌跡のようになっていた。
「それで?」長瀬がいぶかしげに聞き返す。
「これを見て、何かに気づきませんか?」
よく見ると、丸の軌跡は二本あり、赤と緑で色分けされていた。別々の丸はそれぞれかなり近いところに同じ日付、時間で存在している。
そしてある丸は全く同じ場所に書かれていた。長瀬は何気なくそれを見過ごそうとして、はっとした。そしてその場所の丸の日付を見る。
そこは第二東京市市庁舎、日付は先にエヴァンゲリオンが襲撃した日だった。
「まさかこれは…」長瀬はようやくそれが何かに気付いた。
「そうです。ここ一月あまりのアダムの出現ポイント、及び同時刻に碇シンジのいた場所のプロットなのです」
「どういうこと!?トードはこれで何に気付いたというの!?」
「トード氏は我々より先に気がついたのです」エージェントは答えた。「アダムの出現ポイントと、碇シンジのいる場所に何らかの因果関係があるということに」
***
19日午前2時02分
その電話は突然かかって来た。彼はいつも通り何気なくその電話を受けたが、しかしそれは彼にとって宿命的なものであることがやがてわかった。
電話の相手の人物が、誰であるかもすぐわかった。
『頼みがある』
その相手は出しぬけに言い、彼の返事を待たずにその用件を告げた。その内容は彼には信じられない内容だった。
「そんな!」彼は叫んだ。「何で僕に…無理です!」
『これはお願いなんだ』相手は哀願するような声で言った。『それにあんたにはそうしなきゃいけない負債があるはずだ。碇シンジに対して』
その一言に絶句した。相手はあの事を知っている。しかしそれも相手の立場を考えればそれも不思議ではなかった。
「僕を、脅してるんですか?」
『いや、その事を誰かに言うつもりはない』相手は答えた。『だがアンタはいずれそのことにけりをつけなきゃいけなくなる。だからアンタに頼んだ。警察へ通報したって構わない。全てはアンタに任す』
暫くの沈黙の後、彼は口を開いた。
「…卑怯です、あなたは」
『わかってる』素直に認めた。『しかし俺にはこれしか方法が見付からなかった。だから頼む』
そう言って電話は切れた。あとはつー、つー、という電話の受信が切れたことを示す音が、受話器から漏れるだけだった。
「自分でけりをつけろ、か…」トードは携帯電話を切った後、呟いた。「俺もだな」
***
18日午後06時10分
シンジは帰りの車中で信じられない思いでいた。今まで見てきたもの、あれは想像してたより遥かに…
ちらと隣にすわるユリを見る。何を感じてるのか、考えてるのか判らない表情だ。あまりに与えられた情報量が多いのかもしれない。
「榊さんは、これからどうするの?」
シンジは聞いた。何か沈黙を破るきっかけが欲しかった。
「碇君は?」
反対に聞き返す。
「僕は…」一瞬口篭もりながらも再び自分の決意を確かめるかのように勢いをつけて言う。「僕は乗る。僕には他に道がないんだ」
「そう、碇君は強いのね…」
シンジは思わずどきっとした。シンジが昔綾波に言ったことを、まるでこの同じ顔の少女に言い返されてるようだ。
「で、榊さんは…?」
動揺するのを押さえて再び聞く。
「私も乗ろうと思う」彼女は俯いて言った。「でも私のは多分、誰かを守るとか、そんな理由じゃないの。私は自分が誰か知りたい。私がもし本当に綾波レイという人なら…」
そう言ったきり黙ってしまった。シンジも沈黙してしまった。シンジは自分に問い返していた。自分がアスカのため、みんなのためと言い聞かせて乗ろうとしてるのはただの自己欺まんではないのか?実際のところ、エヴァに乗ってみんなに大事にされる都合のいい自分を見つけだそうと…
そう思った時、急に山中を走る車が大きく横に揺れた。
「きゃあ!」
ユリの悲鳴が走る。そのまま横滑りに滑った車はガードレールにぶつかり、ようやく止まった。
「う、う…」
シンジは窓ガラスにおでこをぶつけ、突然の衝撃で位置関係を見失いそうになりながらも首を振ってなんとか頭を覚醒させようとする。運転手とSPが銃を抜いてスライドを引く音がした。
襲撃!?まさか…
シンジの頭にようやくその可能性が浮かんだ。
エージェントたちが銃を構えて一斉に外へ出る。そこには一人の男がライフルを片手に立っていた。迷彩服を着、顔にはガスマスクをつけていて誰かがわからない。男は銃を向けるではなく、自分の足元に転がってる何かを彼らの中に蹴り込んだ。
エージェントはぎょっとしてそれを見る、とたちまちそれから白い煙が吹き出した。
シンジは車中から煙に包まれた全員が涙を流し、咳でむせ返ってるのを見た。催涙ガスだ。幾つか銃声がしたが、それもすぐに止んだ。全てハンドガンの銃声だった。
突然、窓の外にガスマスクの男が顔を出す。こんこん、と窓を叩くがシンジもユリも開けるわけがない。しかし男は背中に背負った高圧のボンベと、ガスバーナーを下ろすと二人に下がるように、というジェスチャーをする。
シンジに何をしてももはや無駄だと言うことが判った。ドアの可動部分が高圧のガスレンチによってたちまち焼き切られていく。
男がドアを外すように開けた時だった。シンジははかない抵抗をしようと、男にタックルをかました。しかしシンジのどちらかといえばか細い体型のタックルが、いかにも頑丈そうなその男に効くわけがなかった。シンジは首の後ろに当て身を食らい、たちまち意識を失っていた。
しかし意識を失いかけながらも、男の素顔を見ようとガスマスクに手をかける。シンジが倒れ込むのと同時にガスマスクの留め金がはずれ、男が素顔を現した。
「トード、さん…?」
まさか敵に回るとは思ってなかったその男の顔が、シンジが意識を失う前に見た最後のものだった。
***
novel page|prev|next