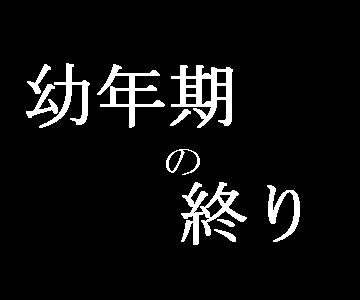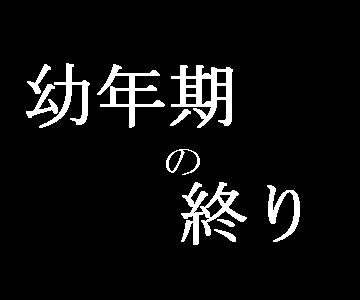
第十二章:幼年期の終り
***
「何で俺達にいきなりそんな事を話すんだ?」
トードが長瀬に言った。
「別に理由なんか特にないわ」長瀬はそう答える。「強いて言えばなんとなく誰かに話したかっただけ。たまたまあなたたち以外に丁度良い聞き手がいなかったのよ」
「まあ、俺には関係ないが」トードが鼻の頭を掻く。「アンタの行動原理は親父への復讐か?親父の作った組織と、兵器に対する」
「いいえ、違うわ」長瀬は穏やかな口調で否定する。「内務省に入った時、まさかネルフ、そしてゼーレに関わることになるなんて思いもしなかった。まあ拘りがあるのは認めるけど、でも私怨で行動してるつもりはないわ」
「本当に?」トードが念を押す。しかし長瀬はそれに答えようとはしなかった。
「人類補完計画の全容については、私たちもわからないわ。でも、もし三年前に人類が共通に見た、あの夢がそうなら、あんな母体回帰願望の権化のような事が補完計画なら私は否定する。私たちは自分でつかまなければいけないのよ、幸せも、自分の居場所も」そう言って背を向ける。「人間の王国はね、空の上にはないわ。この世界こそ人間の唯一の王国なのよ」
***
「王国は汝の中にあり、ね…」トードはシンジの部屋の扉の前で壁に寄りかかりながら、ナゲットを口に放り込んで呟いた。「ま、死んだら「ハイ、ソレマデヨ」なんてことはわかってはいるんだがね…」油の付いた指を意地汚く舐める。
長瀬は否定してるが、長瀬の行動の基盤には明らかに父親の影が色濃く影響している。だがそれ自体はおかしなことではないだろう。親の影響を受けずにいない人間などいない。むしろ親父のことで拘れるのは幸せだと彼は思った。
彼には拘ろうにも、その肝心の親の記憶がない。生きるのに必死で、思い出すこともなかった。
(ま、この平和な国で育ってたらちっとは事情が違ったろうがね…)
何の事はない、親の影をまだ引きずってるという点では、長瀬もシンジも大して違わないのだ。だがあの女の行動には確信がある。一旦動き出したら迷いがない。しかし碇シンジは違う。本当にこれでいいのか、迷ってしまう。性格の違いと言えばそれまでだろうが、この違いはなんだろう?
(考えても詮無いことか…)
トードは苦笑した。人のプライバシーにずけずけ立ち入ると言う点では、今部屋の中に二人きりで話しをしている碇シンジと榊ユリの会話を何処かで盗聴している内務省の奴等とおっつかっつだろうな、と思った。
「プライバシーもへったくれもあったもんじゃないな…」
自分が外に出たところで誰かが二人の会話を盗み聞いてるなんてことはわかっていた。しかしそれでも彼は外に出る。そういう性分だからしかたない、そう思いまた苦笑した。
最初シンジは、彼女が急に部屋を訪れて来た時、どうしたらいいか戸惑った。しかし無論中に入るのを拒むわけにはいかない。しかし一緒にいても何を話せばいいのかわからなくなるのは目にみえていた。
しかもトードも余計な気を回して部屋の外へ出てしまった。せめて彼がいてくれれば場が持つのに、そう思ったが口に出していう暇もなかった。もっともあっても言えるわけがなかったが。
しかしそんなシンジの考えも、杞憂に終わった。部屋に入るなりユリがしゃべるしゃべる、部屋の掃除は毎日するの?とか、食事は自分で作るの?食べ物は何が好き?私はいまダイエットをしてるんだけど。部活には入ってるの?あれが碇君の楽器?バイオリンのお化け?え?チェロって言うの?ふーん、ね、聞かせて聞かせて、CD何持ってるの?クラシックとポップスばっかだね。私イージーリスニングとか現代音楽なんかが好きなんだけど、パガニーニとかはいいよね。ロックとかも時々聞くけど、何が好き?え?ロック聞かないの?じゃ、今度貸してあげるね。
「ちょっと待って!榊さん!」
シンジがやっとのことでしゃべりまくるユリを押しとどめた。
ユリが二三回瞬きする。「どうしたの?」
「いや、その…」真っ正面から見つめられてシンジが戸惑う。「今日は何の用?」
「碇君、どうしてるかなーって思って」ユリが笑顔で答える。
「え?」直球なセリフにシンジの方がとまどう。
「って言ったら嬉しい?」からかうようにそう付け加えた。「やーね、冗談よ冗談!」
笑いながらそういう様子は本当に冗談なのか本気なのか、まるで掴めない。シンジ一人がユリに振り回された格好になり、急に疲労感を感じた。
「で、何しに来たの?」
「ん?暫く会ってなかったから顔を見たかったってのは本当。でもそれはついでで、今度ね、碇君を家の夕食に誘おうと思ってそのお誘いに来たの」
「でも、それだったら電話でも…」
「電話だと、碇君何のかんの言って来ないでしょ?」図星だ。正面切って言われるから断りきれない。シンジの心の内を読んだかのようだ。「じゃ、明後日だから、絶対来てね!」
「ちょ…!そんな急な!」シンジは何とか断る口実を見つけようとした。
「あのね、その時に話したいことがあるの…」急にユリの態度が豹変し、真剣な口調になる。
「話したいことって…」
「だから絶対来てね!」また元の口調で言うとすぐに帰り支度をし、玄関へ向かう。
「ちょっと待ってよ!」シンジもその後を追った。
「じゃ、またね」
手を振って玄関から外へ出る、と、外で待っていたトードとばったり出くわした。
「ちょっと!トードさん、こんなものばっか食べてちゃ駄目じゃない!」
ユリは会うなりトードの手からナゲットの袋を奪い取った。
「おい!俺の晩飯!」袋を奪い返そうとするトードの手が空を掴んだ。
「じゃ、トードさんも、明後日来てくださいね!」
「は?」何の事かわからないトードは呆気に取られるばかりだった。
「おやすみなさい!」
ユリがトードの手に袋を押し戻し、足早に階段に向かうと後を追ってきたシンジがようやく玄関から出てきた。
「ちょっと!榊さんってば!」
しかしシンジの声を背に、ユリはさっさと帰っていってしまった。
「…なんだ、振られたのか?」
トードがナゲットに食いつきながらぽつりと呟く。
「トードさん、悪趣味ですよ」
シンジがトードを睨んでそう返事をした。
ユリはシンジのアパートから出てくると、彼女に付きっ切りのSPの車に乗った。
車内で、ユリの顔から表情が消える。しかし心臓はそれとは裏腹に早鐘の様に打っていた。彼女は予定してた通りの『榊ユリ』の役をやりとおした。入ってから話すことも振る舞いも、殆ど考えとおして前もって決めていた。さっき彼女はその通りに動いてたにすぎない。おそらく、シンジよりも緊張してたはずだ。
もしただ行けば、何を話していいかわからなくなる。シンジの世界における位置づけがないまま、そしてその溝はどんどん深くなっていく。そんなのは耐えられなかった。ひょっとしたら昔の自分を知ってるかもしれない、唯一人の人物なのに、今は彼にすがるしかないのに。
何時の間にか彼女は自分が小刻みに震えてるのに気が付いた。
***
「あら、いいじゃない、行ってくれば」意外な言葉が長瀬の口から出る。
「おいおい本気か?」長瀬のデスクに腰を下ろしてトードが聞き返す。
「そこ、ふまないで」長瀬がトードの尻の下敷きになった書類をつつく。トードは慌てて飛び降りた。「ここの所、外出もままならないしね。学校も休ませてる訳だし、ガス抜きはどこかで必要よ」
「意外だな…」トードが思わず呟く。
「何が?」長瀬がずり落ちかけた眼鏡をまた押し上げて聞く。
トードは少し戸惑った。
「アンタがそんな他人のことを気にかける奴だと思わなかったんでね…」
「失礼ね」長瀬は心外そうに言った。「メンタルのケアにも注意を払うのは管理職にある者として当たり前のことです。精神論ですべて片づけようとする杜撰な日本の管理体制とは違うわ」
「アンタにしては偉くまっとうな意見だな」
「私はいつだってまっとうなことを言ってます!」長瀬は眉間に皺を寄せてデスクを叩いた。「それはそうと、二人の会話内容、後で報告して頂戴」
トードの表情が曇る。「俺にスパイしろってか?」
「プロでしょ?仕事はきちっとしてもらうわよ」
「俺との契約には諜報活動は入ってなかったはずだが?」トードがいやみを込めて言った。
「別にあの二人のプライベートな事まで報告しろとは言ってないわ」再び書類に目を通す。「あの二人の会話を注意して聞いていて。何か隠してるかもしれないから」
トードが皮肉な笑みを浮かべる。「結局のところ、他人を信用してないんだな…」
「そういうわけじゃないわ」長瀬はひとまずペンを置く。「彼らが私たちを信用してないのがわかってるだけ。まあ無理もないけど」
その一言にトードも沈黙した。
「ところで用件が済んだらさっさと出てってくださらない?私は今あなたの世間話に付き合う余裕はないのよ」
そう言われて、トードは長瀬のデスクの上に積み上げられた書類の束を見る。
「そう言えば忙しそうだな。何かあったのか?」
「いいわね、あなたは気楽で」そう言ってため息をつく。「先の戦闘による被害、その他に関して市議会警視庁環境庁農林水産省建設省大蔵省外務省防衛庁運輸省エトセトラ、一通りの苦情が来てるのよ。全く、自分たちの仕事は苦情を言うことだって勘違いしてるんじゃないかしら?」また書類に目を通し、眉を吊り上げる。「ちょっと!なんで沖縄開発局からも苦情が来てるのよ!」
ヒステリックに叫ぶ長瀬を尻目に、トードはすごすごと退散していった。
***
「ごめんね、今日はお父さんとお母さんが丁度留守なんだけど、構わないわよね?」
二人を玄関で迎えいれると、ユリはそう前置きした。
「いやまあ、構わないけど…」シンジにはそう答えるしかない。
「じゃ、ちょっと待ってね今から作るから」
そう言ってキッチンにかけていく。
「へえ、榊さん、料理できるんだ」シンジが感心して言う。
「ううん、したことないわよ」ユリは平然と答える。
「は?」
シンジとトードの顔が一瞬、同時に引きつる。
「うーん、母さんは店屋物頼みなさいって言ったんだけど、せっかく来てもらったのにそれじゃ味気ないでしょ?だから作るの。材料はちゃんとあるし…」
「あの、じゃ僕が手伝うよ…」
シンジがおずおずと申し出る。
「だーめ!お客さんはちゃんと待ってなきゃ!大丈夫、料理なんて結局のところ切って、煮たり焼いたりするだけなんだから」
「いや、まあそれはそうなんだけど…」
シンジが不安げな目でトードを見上げる。
「本当に大丈夫なのか?」
トードがシンジに耳打ちした。
食卓にはなんとか食べられそうなものが並んだ。といっても実際のところは見かねたシンジが手伝って、というよりほとんど一人で作ったのだが。
「ごめんね、碇君」ユリは手を合わせて頭を下げる。「せっかく呼んだのに、結局手伝わせちゃって」
シンジが乾いた笑いを上げる、「いや、いいんだ、楽しかったし…」
料理なんて作ったことのない人間が作ったのだからまともに行くわけがないのだが、ユリの奇妙なところは料理の本を見て、材料や調味料の量はきっちりと、きっちりとしすぎるくらい合わせるのだ。その他の手並みははっきり言ってまともに出来るわけがない。
「それにしてもまるっきり肉っ気のないメシだな。まるで精進料理だ」
トードがグラタンをフォークでつついて言う。
「ごめんなさい、私がお肉駄目だから…」
「いや、別に気を悪くしたわけじゃない」そう言って口に運ぶ。「ま、うまいしな…」
多分、と小さく付け加える。彼自身はあまり味覚が敏感な方でないから実際のところよく分からない。
「そう、よかった」ユリが安心する。殆どシンジ一人で作った料理なのだが。「ところでトードさんは料理できるんですか?」
「どうにか食える代物を作るくらいだがね」そう答える。「その代わり大体の物は食うな」
「大体のものって?」シンジが口をはさむ。
「そうだな」頭を掻きながら数え上げる。「鳥、獣、魚、トカゲ、カエル…」
「トカゲに、カエル、ですか?」シンジの顔が引きつる。
「カエルなんざ中華料理にだってあるだろ?」何がおかしいのか解らずに答える。「木の根をかじったこともあるし、しょうがないんでゴキブリを炒めて食ったこともあるな」
ユリがスプーンを置いて口に手を当てる。
「ちょっと、トードさん…」シンジが慌てて止めようとする。
「あ、すまん」さすがに言い過ぎたのに気が付いて、素直に謝った。「俺の育ったところは何でも食わなきゃ生きてけないところだったからな…」
「トードさんの育ったところって?」シンジは話題を変えようとする。「ご両親のことは覚えてなくても、育ての親はいるんでしょう?」
「まあ、いるけど」困ったような笑顔を浮かべた。「でも止めよう、あまり楽しい話しじゃない」
「そんなこと言わないで聞かせて」
ユリもそう言った。
「別に大したことじゃない」トードは手を振った。「十歳の時、ゲリラに拾われて、村に連れてかれたんだ。あんなご時勢に縁もゆかりもない餓鬼を養てたんだから、まあ奇特な人間だったんだな。もっとも十歳でも銃は握れるからな。そっちの方はみっちりと仕込まれて、頭数に加えられたよ。奇特と言えば、俺の養い親は熱心なクリスチャンで、子守り歌代わりに聖書を聞かされたな」
そう言って口をつぐむ。
「で、その後どうしたんですか?」
シンジは話を急かす。
「別に。たいしたことはないさ。ある日政府軍の空爆を受けて村ごと皆殺し、俺だけたまたま運良く生き残った。それだけだ」
全員が黙り込んだ。
いきなりトードが笑い出す。
「な?楽しくないって言ったろ?」ごまかす様に言った。
「その、ごめんなさい」
シンジが謝る。
「別に俺が勝手に話したんだ、俺の方こそ悪かった」今度はトードが話題を切り替えようとする。「ところで今まで何度俺の名前が変わったか知ってるか?20回は変わってるんだぜ?最初の名前はトーゴーだったんだ。何でかわかるか?」
いきなり尋ねられたシンジは戸惑う。「え?何でって…急に言われても…」
「デューク・東郷だよ、知らねえのか?」シンジとユリが思いっきり引く。「冗談だよ、俺の養父が日本人ってえとトーゴー・ヘーハチローしか知らなかったんだよ!」不機嫌そうな顔を作って言った。
「じゃ、今の名前はなんで?」ユリが尋ねた。
「ああ、トードって名前か?」トードは鼻の頭を掻く。「トードってのは、英語でどういう意味だ?」
「えっと…カエル、かな?」ユリが答える。
「じゃ、ちょっと見てろよ…」トードはポケットから丸眼鏡を取り出して掛けた。「何かに似てねえか?」そう言って自分の顔を指差した。
「ぷっ!」
シンジとユリは思わず吹き出した。日本人特有の目と目の間が離れた顔の造形につぶれぎみの鼻があいまってひき蛙そっくりの顔なのだ。
「な、わかったか?だから『トード』だ」
堪えきれずにシンジとユリが大声を上げて笑った。
同時刻、シンジの部屋の前で誰かが立ち止まる。カードキーを切ると、玄関の扉は苦もなく開いた。手袋をはめた手を伸ばし、灯りを点ける。玄関から上がろうとして、足元に小さな紙切れが落ちてるのに気付いた。足跡が付いている。
変だな、と彼は思った。この他にはちり一つ落ちてないのに、なぜ紙切れが落ちてるのだろう?しかしなるべく手を触れないでおいたほうがいい、そう判断して紙切れを避けていった。
さて、まず何処から探そう、彼は考えたが、取り敢えず探しやすいところから探すことにした。チェロのケースが置いてあるのを開き、中を見る。一応チェロの中も見てみたが何もない。慎重に元に戻すと、また先ほどと同じように立てかけておいた。
次に冷蔵庫が目に入った。まず冷凍庫を開ける。中を調べるが冷凍食品と氷以外には何もない。次に冷蔵室の扉を開けた。その次の瞬間、冷蔵庫からおこった爆発の炎が彼を包んでいた。
雰囲気が再びなごんで、歓談をしている時に消防車のサイレンの音が遠くでした。
「ん、なんだ?火事かな?」
トードがつぶやく。
「それより榊さん」シンジが話題を変える。「話したいことがあるって言ったよね。何なの?」
「ああ、そのこと」とたんにユリの顔から笑顔が消える。「ねえ、私の肌、どう思う?」
「どうって…」いきなり聞かれてシンジはどぎまぎしてしまった。「き、奇麗なんじゃないかな…すべすべしてそうで、白くて…」
「そう…」ユリが俯いた。「じゃ、今度はこれを見て」
そう言って暫く顔に手を当てていたかと思うと、再び顔を上げた。
「!」シンジは絶句した。
「おい、その目は…」トードも、シンジ同様にショックを受けていた。
紅い瞳、それがユリの顔から二人を見ていた。
「この髪もね」そう言って髪に手をやる。「染めてるの。本当はおばあちゃんみたいに真っ白。先天的に色素が欠乏してるんだって」ユリはさびしそうに言った。
「それは…生まれつき?」
シンジが尋ねる。
「ううん、わからない。私には三年前からしか記憶がないの」ユリは告白した。「ね、あなたの知ってる私にそっくりだって人、それはひょっとしたら私じゃないの?」
シンジには答えられなかった。それはシンジの持ってる疑念そのものだったから。
「わからないのね…」ユリは寂しそうに言った。「ならそれでもいい。せめてどんな人だったか教えて」
「それは…」言うのか?綾波レイは水槽に浮いていた存在だと。彼の母だと。言えるのか?言えるわけがなかった。「ごめん、言えない」
「そう…」ユリはうなだれた。
「でもこれだけは言える」シンジはあわてて付け加えた。「不器用な子だけど、優しい子だった…」
「ありがとう」
ユリは微かに笑った。
急に電子の呼び出し音がした。トードがコートの内側から携帯を取り出す。
「ん?なんだ?」あまり元気のない様子で対応する。「え?何言ってるんだ?はっきり言え!爆発?何の話だ?」
***
長瀬が現場検証の写真を投げてよこす。
「原因は老朽化して亀裂の入ったガス管からもれたガスが、何らかの原因で火花が引火し爆発」読んでいた報告書をトードに渡す。「と、公式の見解は発表してるけどね」
写真を眺めてたトードがしゃべりだした。「こんなもの、見る奴が見れば一発で嘘だってわかるぜ」
「じゃ、爆発の原因、わかる?」挑むように言う。
トードは写真をめくりながら見ていたが、その中から何点か選び出して並べた。
「古典的な手だ。冷蔵庫の中に爆発物、おそらく手榴弾だな、そいつを安全ピンをはずした状態で固定、テグスかなにかで冷蔵庫の扉とピンを結びつけておいて、冷蔵庫が開くと同時にどん」片手で手で爆発のジェスチャーをしてみせた。「あの世行き、ってわけだ」
「こっちも同じ結論よ。それを調べるのに自衛隊から爆発物処理班まで呼ぶ始末だったわ」長瀬は頭を押さえた。
「日本のテロリストっていうとテッポーダマの特攻だと思ったがな」
感心してるのか何なのかよくわからない口調で言った。
「それはヤクザよ」長瀬が呆れて訂正する。
「同じようなものだろ?」
「ヤクザはテロリストとは違う、マフィアよ。マフィアは損得で人を殺すの。イデオロギーでは殺さないわ」
「ニンキョーってのは一種のイデオロギーだと思ってたが?」
「今時任侠道なんてヤクザの間でも流行らないわよ」
「そんなもんかね」写真を机に投げ出した。「それはともかくとして、相手はテロリストってわけだ」
長瀬はうなずいた。
「ええ、犯行声明が警視庁に送られたわ。発表される前に押さえたけど」
「何で小僧を狙うんだ?」
トードがもっともな疑問を言う。
「どこかの国が意図的に情報をリークしたんじゃないかしら?手に入らないなら消した方がいいってね」
「おいおい、FBIの陰謀説かい?」
「FBI自身が手を下したわけじゃないでしょうね」長瀬は大真面目に答えた。「手口が素人臭いもの」
「これ見て」投げ出された写真の中から一枚を取り、トードに見せる。「それ、玄関付近に落ちてた紙なんだけど、ほら、足跡が付いてるでしょ?それは中で調査をしてたエージェントとは別の…」
「おい!」トードが急に叫んだ。「お前らやっぱり家捜ししてたんだな?おかしいと思ったぜ。勝手に冷蔵庫の扉が開くわけないからな!」
「そんなこと今言ってもしょうがないでしょ!ともかく犯人は私たちより先に潜入、爆弾を仕掛けて立ち去ったのね。多分清掃員か何かに変装して…」
「くそ!こんな事だったら教えときゃ良かった…」
トードの呟きに長瀬が喋るのを止めた。「何をですって?」
「この紙切れだよ!」トードは写真を示し、もう片方の手でそれを叩いた。「これは俺が玄関のドアの間に挟んでおいたんだ」
「何のために?」怪訝な顔をする。
「簡単なことじゃねえか、もし誰かが侵入して、この紙切れに気付かなきゃ紙切れは落ちたまま。一番原始的な警報装置だよ」
長瀬はため息をついた。
「まめな男ね。それさえわかってれば…」
「家捜しのことを黙ってたのはアンタたちだぜ?」
「わかってるわ。もうやめましょ。ともかくサードチルドレンの身の安全が第一よ。今新居はこちらで手配中だけど、それまでしばらく潜伏してもらうわよ」
トードは暫く黙ってた。
「仕方ないだろうな」やっと口を開いて言った。「ところで家捜ししてた奴は?」
「死んだわ」長瀬は珍しく怒りを顕わにして言う。「即死だったのが、せめてものなぐさめね」
***
novel page|prev|next