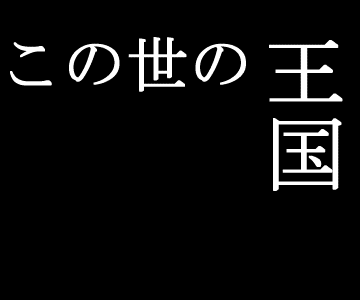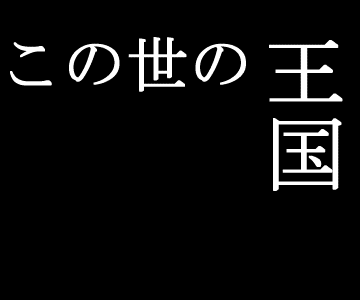
前章: この世の王国
”彼”のいるところからはその小高い丘の麓が一望出来た。緑の森は薄暗い月灯りに照らされ、限りなく網に近く見える。その中に無数に瞬く、微かな赤外の光こそか弱くもはかない命の灯であることを、彼は、他ならぬ彼こそがよく知っていた。
あともう少し時間が経てば彼はここから離れねばならない。おそらくは永久に、彼の愛してやまない生命たちに手の届かぬところへ。
彼らが進む道を与える…この惑星が太陽を幾億、幾兆も巡る間、それが彼の仕事だった。そして今、彼らをいきなり苛酷な運命へ放り出そうというのだ。
彼の去った後の彼らの運命を想うと彼の心に痛みが走る…しかし全ては決定してしまったことなのだ。彼らは自らの運命を自らの手で切り開かねばならない。彼らを創り出した者たち同様に。
彼は今まで目を向けていた丘に背を向け、空を見上げた。そこに輝く満月は、冷たく、ただ青白い光を照り返すのみだった。
「我々には時間がないのだ…」
月灯りが罪さながらに彼を射抜いていた…
***
「現時刻、2217。全員の配置が完了。目標に動きはありません」
携帯式の通信器に向かっている自衛官の声が路地裏に響く。
その声は男の耳にたいして感慨も与えなかった。他に何人かの自衛官たちが忙しく動き回っていたが、それほど気にはならなかっった。
男はトードと呼ばれていた。本名ではない。
その顔立ちは東洋人には違いないが、精悍でどこか日本人ばなれしてるようにも思えた。
彼の顔の中心にある鼻は少し押しつぶされたように広がっており、横に生々しい古傷の痕が残っている。それがなければハンサムと言えたかもしれない。
もしたまたま通りすがった通行人がこの光景を見れば奇妙に思うだろう…しかしその心配はない。この辺り一帯には避難命令が出ている。民間人は一人もいない。予告爆弾テロに対する戒厳令というのが表向きの理由…苦笑したくなるほどチンプだ。
恐ろしくないというわけではなかった。しかし焼けつくような、恐怖ではない。適度な緊張感。体中に不思議な充実感がみなぎっていた。
こういうときは旨くいく…
彼は今まで培った経験則で自分に喝を入れた。
男は着けていた赤外線スコープを外し、首にぶらさげると再度銃器の点検を始める。
こんなものがどこまで役に立つかは判らないが、備えあれば愁いなしだ。いつどのように命を救ってくれるかわからない。
見かけは普通の自動小銃と大差ないように見えるが、火薬式ではなく、劣化ウラン弾を機械式に射出する…貫通力は通常のものと比べものにならない。しかし、その反面、反動が大きく、長時間の使用では故障も多い。実験段階で実戦向きではない。こんなものを使うのは気が引ける。やはり使いなれた物の方が良いとも思う。しかし今回はそれでは危険すぎるのだ。これが合理的な選択だと自分に言い聞かせる。
「長瀬三佐より入電です」
急に先ほどの自衛官が呼びかけけてきた。銃の手入れの手を止め、そちらの方へと歩いていった。通信器を手渡される瞬間、自衛官が何とも言えない目で男を見た。自分と違い、組織に自衛隊という組織に属さず、多くの戦場で数え切れぬほど人を殺してきたであろう男に対する恐怖と嫌悪感、その罪を問われない連続殺人犯め、といった目で。
そんな目で見るなよ、男は心の中で呼びかけた。俺もあんたとたいして違いはしないさ。つまり金で雇われた人殺しってことさ。
「ミスター・トード」通信器から稟とした女性の声がした。「準備が終了次第作戦を開始します。作戦行動はブリーフィング通り、目標への誘導は随時こちらから無線で致します。なお本作戦は情報収集を主としたもので、近距離からのデータ収集を第一とし、不必要な武力行使は避けてください」
「りょうかい」今まで耳にタコができるほど聞いている。俺だってプロだ。作戦に必要な全ては頭に入ってる。もう少し信用して欲しいものだと思う。少なくとも作戦に関しては。
「ミスター、くれぐれも既約違反のないように。では」
通信が切れる。やはりいけすかない女だと思う。が、ま、これもお仕事さ、と嘘ぶいてみる。しかし自分の中のどこかで、それだけでないことを気付いている。しかし頭の中から感傷を締め出した。感傷は迷いを生むからだ。こういう時に迷いが生じるとろくなことはない。銃の点検を再開し、それがほぼ終った頃、再度通信が入ってきた。
通信器を受け取った。
「そちらの準備は?」
「たった今全配置の完了を確認したわ」
「では現時刻より行動を開始する」
わざと荒っぽく通信を切ると通信器を自衛官に返した。
一人で移動を開始してからも目標の位置は先刻よりさほど変わっていない。時々小型の無線から移動方向に関しての指示が入る、が位置の再確認をしているようなものだった。子供扱いされているようで、腹が立つよりむしろどこか滑稽だった。
ビルと食堂の合間の狭い路地の前に来る。
「その奥よ」指示が入る。
「反応は?」聞き返す。
「変化なし。未だにパターンオレンジとグリーンの周期的変動を示してるわ」
着けているスコープを再度しっかりと着け直し、肩に装着された小型カメラがきちんと正面を向く様に位置を直す。
夜空を見あげる。肉眼では見えないが高感度カメラにより、これからおこる接触の一部始終がどこかから収められてるはずだ。
同様に狙撃部隊、特殊武装部隊が万が一に備え防衛線を張っている。彼らが活躍するような羽目になった時は彼はもうこの夜にいないだろうから気にすることもないのだが。
何のへんてつもない商店街の路地裏。しかしそこにあの怪物−それ以外の呼び名は彼には思いつかなかった−がいる。深く息を吸うと、何処かすえたような熱帯夜の空気が喉を焼く。
じっと闇の奥を見透かそうとするように路地を見つめ、そして足を踏み出した。一歩、また一歩。地獄に向かって歩いている感覚さえ頭をかすめる。でもいままでだってこんなことがなかった訳じゃない。いままでだって生き延びて、そしてここにいるんだ。今度も生き延びてみせるさ…
奥に微かな人影が見える。近付いていくと、その姿は段々大きくなっていく。赤外線スコープ越しに見えるそれは人型のサイケなパッチワークにも見えた。座り込んだ膝の上に何か別の小動物がいるようだったが、大きさから猫だろうと判断した。
あと4、5mの距離まで近付いて、そして足を止める。スコープをずりあげ相手を見つめる。せいぜい10歳くらいの少年。膝の上にはやはり猫がいた…黒猫だった。
スコープ越しでは色までは判らなかった。少年の髪が白く、その瞳が紅いのが判らなかったのと同様に。一年前はそこまでしっかりと見る余裕はなかった。
少年が無感動にこちらを見るのと同時に、猫がいきなりの侵入者に警戒した。
しかし男には、このかわいらしい小動物の怒りにかかずらわってる余裕はなかった。
汗が流れるのは蒸すような熱さのせいだけではなかった。
彼はひりつくような暑さを感じながら、口を開いた。
「久しぶりだな、化けもの小僧」
***
彼女はふと自分がベッドの上で横になっているのに気付いた。
外からさす街灯の灯りが天井を薄暗く照らしている。見なれてるはずのその天井が、ひどく違和感があるものの様に映った。
”何故、私、ここにいるの?”心のどこかからそう問いかける。
わかりきってることだ。ここが彼女の家なのだから。
しかしその瞬間、彼女の回りの全てが虚構に過ぎないような錯覚を覚えた。
ふと彼女は自分が言い知れようのない喪失感を感じているのに気づいた。
「泣いてるの?私?」
少女は思わずつぶやいた。そう、彼女は泣いていた。たとえ涙は流してなくとも。
「何故泣いてるの?」
悲しいからだ。
「どうして悲しいの?」
それはわからない。
何故だか知らないけどとてつもなく悲しかった。彼女自身が涙の結晶から出来ているかの様に。
彼女は涙を流さずに泣き続けた。その間はこの世界と自分との違和感は彼女の中から消えている。
世界のどこにも自分の居場所などないことを思い出さないでいられる。
彼女はその紅い瞳で天井を睨み、泣き続けた…。
***
土曜の午後、外来の受け付けも終了した病院、普段は昔話を飽きもせず繰り返す老人たちでごったがえす受付前のロビーも今は閑散としている。
受け付けをしてる二人には、外からの来客よりも、今年の流行色についての話の方が重要といった様子で、とめどもなくおしゃべりを繰り広げていた。
急に病院の自動扉が開き、学生服姿の少年が入ってくる。
受付の女性の一人がそれに気付き、「あ」と小さな感嘆の声をあげる。「こんにちは」
少年はそれにはにかんだ会釈で答えると、急ぎ足で受付の前を通り過ぎていった。
「誰、今の子?知合い?」
突然の来客に話し相手を奪われたもう一人が聞いた。
ん?あの子?毎週二度は必ずお見舞いに来るのよ。えーっと名前はたしかね…」来客名簿を引っ張り出すと、ページをめくり、やがてあるページで止まった。「ヒガシ、東シンジくんね」
「ふーん」たいして興味なさそうに生返事をする。どちらかというとさっきまでの話題に話しを戻したがっていそうだった。「で、誰のおみまいなの?」
「えーと、あら、女の子ね。D−317に入院してる…」
「へえ」始めてわずかに興味が動いた表情をみせた。「彼女かなんかかな?」少し意地の悪いような笑みを浮かべて聞く。
「それはないみたいよ」苦笑して答える。「だって同じ名字だもの」そう言いながら名簿を示す。
おざなりにそのページをざっと見てから、「ところでさ…」さきほどから中断してた話題を再開し出した。彼女にとってはそのほうが重大事だったから。
少年は三階でエレベーターから降りると、歩きなれた通路を歩き始めた。途中、顔見知りの患者とその付添が挨拶をしてき、その度に少年は少しくすぐったそうに返事をした。
やがて一つの病室の前で足を止める。扉の前の患者の名札は「東」と書かれたものしかかかっていない。
軽く扉のパネルに手を触れると扉が開いた。
「あら、こんにちは」
部屋の中で患者に食事をさせている看護婦が彼に気付き、挨拶をした。
「こんにちは」少年は荷物をおきながらあいさつを返す。
「いつもいつも大変でしょう。無理することはないのよ」スプーンを置きながら看護婦が言う。
「いえ、こちらこそいつもお世話になってしまっって…」少年がそう答える。
「いいのよ。仕事なんだから…」もう少し気の効いた台詞が言えればいいのに、と内心歯がゆい思いをする。「でもね、あなたが来るとこの娘もとても機嫌がいいの。やっぱりお兄ちゃんがいいのかしらね」
「え?…いや…」困ったような照れた笑顔を見せる少年に、看護婦も思わず笑みをこぼす。「ここのところね、リハビリもとても順調だし、うまくいけば年内には通院に切替えられるかもしれないって先生もおっしゃってるわ」
「本当ですか?!」少年が嬉しそうに−心底嬉しそうに答えた。
「お兄ちゃんが励ましてくれたおかげよね。ねぇ、アスカちゃん?」
看護婦の呼びかけに、ベッドの上の、赤毛がかった髪の、少年と同い年くらいの少女がどこか虚ろな影のような笑みを返した…
PROLOGUE:Markuth END
novel page|next